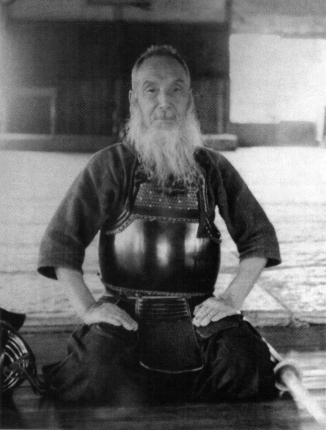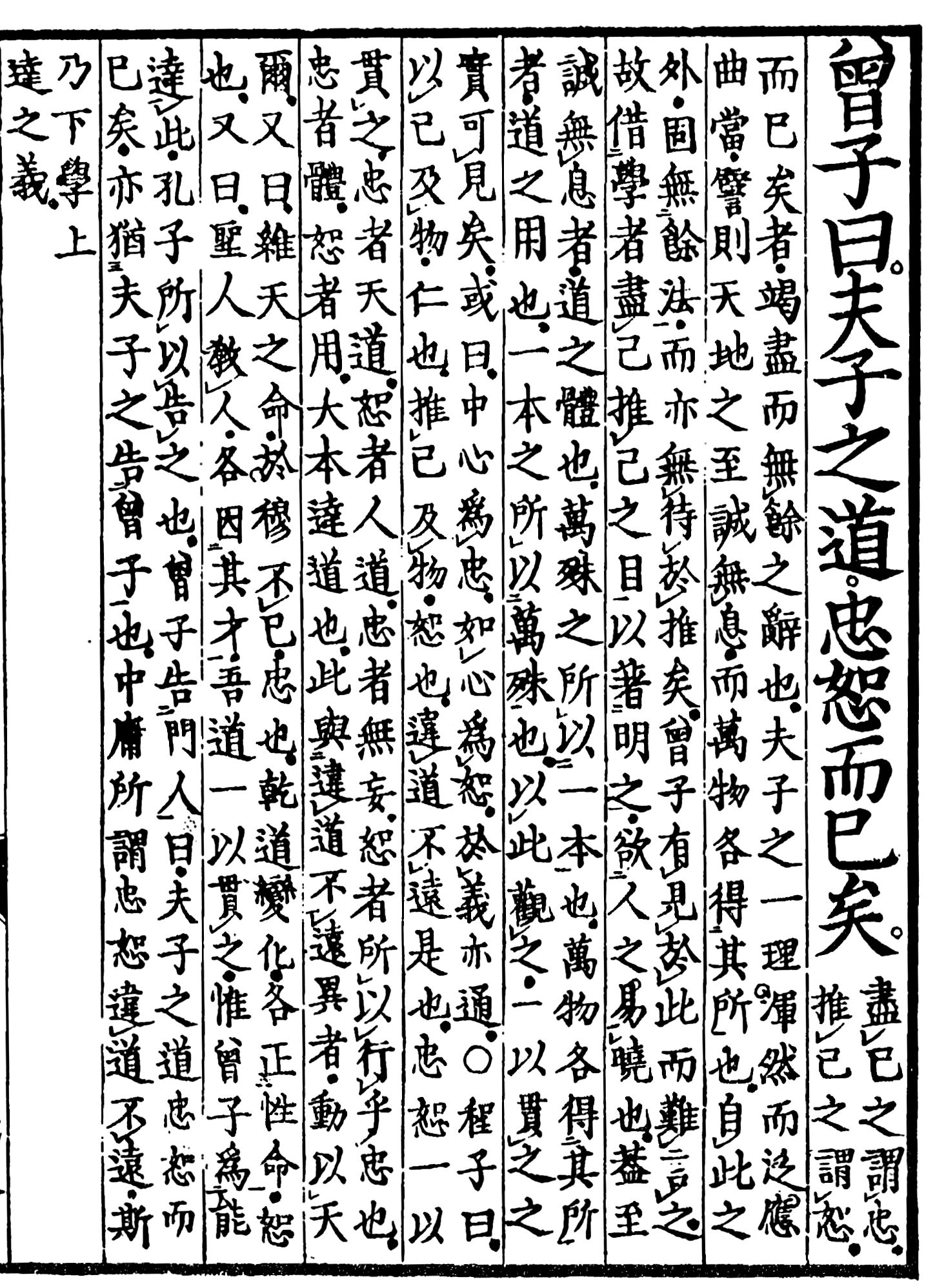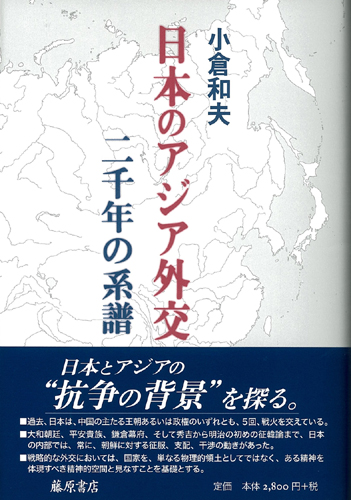「正義の法」による勝利
 寛容の精神を備えた指導者アショーカ王の精神は、インドの平和主義の理想として継承されてきた。
寛容の精神を備えた指導者アショーカ王の精神は、インドの平和主義の理想として継承されてきた。
例えば、インディラ・ガンジーは、著書『私の真実』において、次のように述べている。
「私たちの目標は、力の均衡を権力のためにではなく平和のために役立てることなのです。友愛の精神は、陰謀を挫折させる力です。印度の歴史を見れば、仏陀の、またアショーカ王の時代から、マハトマ・ガンジーの、および、ジャワハルラル・ネルーの時代まで、これこそが常にわが国の政策であったことがわかります」 続きを読む アショーカ王─友愛の精神による統治