 いま、幕末の志士・真木和泉が、奇妙な歴史解釈を売り物にする書物の中で貶められている。そろそろ、本格的な反撃に出なければならない。
いま、幕末の志士・真木和泉が、奇妙な歴史解釈を売り物にする書物の中で貶められている。そろそろ、本格的な反撃に出なければならない。
「一切の私心なし! 一族ともども理想の為に殉ずる覚悟」。それが真木の真髄である。
「とゝ様の打死悲しくは候へども、皇国の御為と思へばお互ひにめでたく……」
これは、真木の天王山自刃の報に接した、真木の娘・小棹が発した言葉だ。真木が討幕運動に挺身した時代、畏れ多くも孝明天皇の御意志は揺らいでいたという説もある。それでも、真木は信ずる道を突き進んだ。それは、決して己のためではない。なぜならば、彼は自らの死、一族の死を覚悟して事に臨んだからである。拙著『GHQが恐れた崎門学』の一節を引く。
〈真木が遺書として書いたのが、「何傷録」です。冒頭に「楠子論」を掲げ、さらに「楠子の一族、三世数十人、一人の余りなく大義に殉死せられしこと、大楠公の只一片の誠つき通りて、人世の栄辱などは、塵ほども胸中に雑らず」と、楠公精神を称えました。そして、十年の謫居を余儀なくされ行動できなかった自らの心情を吐露し、今や身を挺する覚悟を綴り、次のように一族に訴えかけたのでした。
「ゆめ吾子孫たるもの楠氏の三世義に死して、心かはらぬあとな忘れそ」 続きを読む 真木和泉の真髄①
「維新」カテゴリーアーカイブ
遠藤友四郎『国体原理天皇親政篇』目次
 以下、遠藤友四郎『国体原理天皇親政篇』(錦旗会本部、昭和8年)の目次を紹介する。
以下、遠藤友四郎『国体原理天皇親政篇』(錦旗会本部、昭和8年)の目次を紹介する。
序文
序篇 世変の前兆たる世相と我等の危惧
一、 明治維新には王政復古の形式獲得・昭和維新には皇国日本への復帰完成
二、 世の大多数者は常に前兆を前兆として感知し得ぬ
三、 前兆は必ず心ある者をして危機を思はしむ
四、 罪人に対する昔の拷問・国民全部に与へられる今の生存苦
五、 我が日本には今や毎日平均百人以上の自殺者がある
六、 徳川時代の日本と仏蘭西と露西亜の虐政ぶり
七、 今の生存苦は果して社会的拷問に非ざる乎?
八、 学校はカントの倫理を教えて社会はマルクス指摘の通り
九、 恐るべき片手落ち!今の我が滔々たる外国化の風潮
十、 幕末の大義名分!日本にのみ有つて外国に無きもの
十一、 忠義の的は天子様の外に何者も無いと云ふ不動の信念
十二、 ああ「陛下の赤子」が「資本の奴隷」とは何事ぞ!
十三、 昭和維新そのものの前に先づ精神的に「日本人の日本」の獲得 続きを読む 遠藤友四郎『国体原理天皇親政篇』目次
「賊臣」となった明治政府─萩の乱・前原一誠檄文
 明治9年10月24日、熊本県で神風連の乱が、同月27日に福岡で秋月の乱が、そして同月28日に山口で萩の乱が起こった。萩の乱を指導したのは、前原一誠ら維新の精神を守らんとする志士たちであった。鎮圧直後の11月10日付の『朝野新聞』には、前原の檄文が掲載されていた。
明治9年10月24日、熊本県で神風連の乱が、同月27日に福岡で秋月の乱が、そして同月28日に山口で萩の乱が起こった。萩の乱を指導したのは、前原一誠ら維新の精神を守らんとする志士たちであった。鎮圧直後の11月10日付の『朝野新聞』には、前原の檄文が掲載されていた。
この檄文は、昭和6年に梅原北明が編んだ『近世社会大驚異全史』(白鳳社)の附録「近世暴動反逆変乱史」に収められていた。40年余りを経た昭和48年、海燕書房が同書新装版を刊行。もとの檄文はすべて漢文。海燕書房編集部が付した大意を引く。
○前原一誠檄文(徳山有志諸君宛て、日付不明)
「昔、我が忠正公(第十二代長州萩藩主、毛利敬親。一八一九~七一)は、朝廷が政権を失っていることを歎き、徳川の遺命に憤り、薪に坐し、胆を嘗め、戈に枕して時代の夜明けを待った。藩士もまた藩主の誠心に感じ、血をすすり、誓いを立てあって、死を決意して我身をかえりみずに(王政復古のために)働き、ついに国内を一つに安定させ、諸事を天皇の手に返すことに成功した。このような時になって、○○○○等の者たちは、天子のそば近くに出入りし、くらべようもなく高い位を得て、先君の偉業を自分の功績とし、自分の思う通りを通し、祖宗の土地をすべて天皇に献じ、そのやっていることといえば、法律をもって詩経・書経となし、収奪をもって仁義とし、文明を講じて公卿を欺き、外国の力を借りて朝廷を脅かす。これを要するに、外国人が幅をきかし、国内は疲弊し、神国日本の安危は、朝に夕も量り難い有様である。(○○○○等は)単に先君(忠正公)に対する反逆人であるばかりでなく、朝廷に対する賊臣でもある。最近、熊本の人人が、正義によって万事を断じ、一戦して鎮台の兵を殲滅し、その余勢が九州を風靡したことは、荒廃した世の中にあって実に一大事であった。諸君は先君の賜った衣を衣とし、朝廷より賜わる食を食として、長年を生きてきた。乱賊の人が誅されないままで、それを心の中で耐え忍ぶことがどうしてできようか。事を起こす点では、すでに他県の人々におくれをとりはしたが、成功を収めるかどうかは、まだこれからで、諸君次第である」
このように、前原は明治6年の西郷南洲下野以降の明治政府の姿勢を、「収奪をもって仁義とし、文明を講じて公卿を欺き、外国の力を借りて朝廷を脅かす」と厳しく批判し、「朝廷に対する賊臣」と断じている。
「明治維新」と「明治という時代」の切断
二つの明治─大久保路線と西郷路線

「明治の時代」と一口に言うが、明治維新の精神は、西郷南洲が西南の役で斃れる明治10年までに押し潰されてしまったことに注意する必要がある。
明治維新の原動力となった思想は、本来明治時代の主役になるはずであった。ところが、実際にはそうならなかった。拙著『GHQが恐れた崎門学』にも書いた通り、早くも明治4(1871)年には、崎門派の中沼了三(葵園)、水戸学派の栗田寛、平田派の国学者たちが新政府から退けられている。
こうした新政府の姿勢について、崎門学正統派を継ぐ近藤啓吾先生は「維新の旗印であつた神道立国の大旆を引降して、外国に認めらるべく、文明開化に国家の方針を変じ、維新の功労者であつた崎門学者、水戸学者、国学者(特に平田学派)を中央より追放せざるを得なくなった」と書いている。
さらに、明治6年には、対朝鮮政策(敢えて征韓論とは言わない)をめぐる対立によって西郷南洲が下野する。それをもたらした明治政府内部の対立の核心とは、野島嘉晌が指摘している通り、維新の正統な精神を受け継いだ南洲と、維新の達成と同時に早くも維新の精神を裏切ろうとした大久保利通の主導権争いだった。
明治7(1874)年2月には、南洲とともに下野した江藤新平によって佐賀の乱が勃発している。さらに、西南の役に先立つ明治9年には、大久保路線に対する反乱が各地で続いた。まず10月24日に熊本県で神風連の乱が、同月27日に福岡で秋月の乱が、さらに同月28日に山口で萩の乱が起こった。
神風連の乱の引き金となったのは、明治9年3月に布達された廃刀令とそれに追い打ちをかけるように同年6月に発せられた断髪令である。文明開化の名の下に、神州古来の風儀が破壊されるという反発が一気に爆発したのである。
萩の乱で斃れた前原一誠は、政府の対外政策にも不満を抱いていたが、特に彼が問題視していたのが、地租改正だった。彼は、地租改正によって、わが国固有の王土王民制が破壊されると反発していた。南洲とともに下野した副島種臣らも、王土王民の原則の維持を極めて重視していた。そして、明治10年に南洲は西南の役で斃れ、大久保路線は固まる。
大東塾の影山正治は、「幕末尊攘派のうち、革命派としての大久保党は維新直後に於て文明開化派と合流合作し、革命派としての板垣党は十年役後に於て相対的なる戦ひのうちに次第に文明開化派と妥協混合し、たゞ国学の精神に立つ維新派としての西郷党のみ明治七年より十年の間に維新の純粋道を護持せむがための絶対絶命の戦ひに斃れ伏したのだ」と書いている。
つまり、明治国家は明治10年までには、大きく変質したということである。むろん、欧米列強と伍してわが国が生き残っていくためには、大久保的な路線が必要であった。しかし、それは維新の精神を封じ込める結果をもたらした。この悲しみを抜きに「明治の栄光」を語るべきではない。 続きを読む 「明治維新」と「明治という時代」の切断
グローバル化に利用される政府の「明治150年」事業─王政復古の意義を封印
 明治維新150年を迎えるに当たり、政府は平成28年10月に「『明治150年』関連施策推進室」を設置して検討を進め、同年末に関連施策推進の方針をまとめた。ところが、政府の捉え方は、またしても「明治維新」ではなく、「明治」である。
明治維新150年を迎えるに当たり、政府は平成28年10月に「『明治150年』関連施策推進室」を設置して検討を進め、同年末に関連施策推進の方針をまとめた。ところが、政府の捉え方は、またしても「明治維新」ではなく、「明治」である。
明治維新100年を控えた昭和41年、佐藤栄作政権は「維新百年に回帰しようなどと大それた考えを持っているのではありません。戦後二十年の民主主義の側に私どもも立っております。…ことさら明治維新を回想するというわけではございません」(官房長官談話)という立場に立っていた。
これに対して、昭和41年3月、憲法憲政史研究所長の市川正義氏は、佐藤首相に質問主意書を提出し、「明治百年の重要性は明治維新にある」と糺している。また、大日本生産党も「明治維新百年祭問題」において、「政府の考え方は〈明治維新百年祭〉ではなく単なる〈明治百年祭〉であって、単なる時間の流れの感慨にしかすぎないのである」と批判していた。安倍政権は、再び50年前の過ちを繰り返そうとしているのか。
しかも、政府の方針には、明治維新最大の意義である王政復古、天皇親政への回帰という視点が皆無である。ひたすら、「明治」という時代の近代化と国際化を強調しているに過ぎない。
明治維新100年を控えた時期には、先述の大日本生産党文書は「明治維新百年祭は単なる懐古的行事ではなく、昭和維新の前哨戦としての役割を持つ」と説いていた。また、安倍源基氏は「明治維新の意義と精神を顕揚して、衰退せる民族的自覚、愛国心の喚起高揚を図る有力なる契機としなければならない」と、福島佐太郎氏は「明治維新を貫く精神は建武の中興、大化の改新と、さらに肇国の古に帰るという王政復古の大精神であった」「われわれは懐古としての明治維新でなく、維新が如何なる精神で行なわれたかを三思し、現代日本の恥ずべき状態に反省を加え、もって未来への方向を誤らしめてはならぬ」と主張していた。50年を経た今日、改めてこれらの意見に耳を傾けるべきではないのか。
政府はわずか二カ月の検討を経て、「明治150年」関連施策推進の方針をまとめてしまった。第1回(平成28年11月4日)の会議では、東京大学名誉教授の山内昌之氏が意見を述べた。同氏の用意した資料には〈「明治維新と明治150年の歴史的意義。270の藩つまり「半国家」「准国家」が独立割拠して個別に外国と条約を結ぶ事態が避けられ、統一国家としての近代日本を立ち上げた意義に尽きる。廃藩置県・徴兵制・地租改正の実施によって、ヨーロッパをモデルとした主権独立国家体制を築き上げた〉とある。王政復古という言葉はない。山内氏は、記念プロジェクトの一例として、お雇い外国人に関する海外との交流行事を挙げた。
第2回会議(平成28年12月1日)では、帝京大学文学部長の筒井清忠氏が意見を述べた。筒井氏は、明治維新の基本理念は「五箇条の御誓文」だと指摘しつつも、そこから王政復古の意義を導こうとはしない。筒井氏は、明治時代の意義として、①立憲主義・議会政治、②国民主義・民主主義(身分制を越えた発言権の称揚)、③人材登用(平等主義)、④進歩主義、⑤世界主義を挙げる。驚くことに、筒井氏もまた山内氏と同様に、記念プロジェクトの一例として、お雇い外国人にちなむ外国との交流イベントを挙げている。
第3回会議(平成28年12月26日)では、内閣官房副長官の野上浩太郎氏が、それまでの検討結果を踏まえ、「『明治150年』関連施策の推進について」を取りまとめたと報告した。
この政府方針にも王政復古の文字はない。しかも「明治維新」の文字すらない。ただ、「明治以降、近代国民国家への第一歩を踏み出した日本は、この時期において、近代化に向けた歩みを進めることで、国の基本的な形を築き上げていった」(明治以降の歩みを次世代に遺す)、「明治期においては、従前に比べて、出自や身分によらない能力本位の人材登用が行われ、機会の平等が進められた」(明治の精神に学び、更に飛躍する国へ)と述べている。
そして、山内氏、筒井氏の意見を踏まえる形で、施策の方向性として、「明治期の若者や女性、外国人などの活躍を改めて評価する」ことなどが挙げられた。
王政復古という維新の本義が封印されたまま、明治維新150年という極めて重要な機会が、グローバル化の推進、女性の社会進出の促進のためだけに利用されることになるのだろうか。
先帝陛下の御学問─杉浦重剛「倫理御進講草案」大義名分
 先帝陛下(当時皇太子殿下)が学習院初等科をご卒業されたのを機に、大正3(1914)年5月、東宮御学問所が設立された。歴史担当・白鳥庫吉、地理担当・石井国次など、16科目の担当が決まったが、肝心の倫理の御用掛が決まらなかった。帝王学を進講する倫理担当には、和漢洋の知識に通じ、高い識見人格を備えていることが求められた。
先帝陛下(当時皇太子殿下)が学習院初等科をご卒業されたのを機に、大正3(1914)年5月、東宮御学問所が設立された。歴史担当・白鳥庫吉、地理担当・石井国次など、16科目の担当が決まったが、肝心の倫理の御用掛が決まらなかった。帝王学を進講する倫理担当には、和漢洋の知識に通じ、高い識見人格を備えていることが求められた。
東郷平八郎総裁、波多野敬直副総裁らが慎重な協議を続け、元第一高等学校長として名声の高かった狩野亮吉の名が挙がったが、狩野はその任務の重さを恐れ辞退した。このとき、杉浦重剛の真価を知るものは、御進講の適任者として彼のことを考え始めていたのである。御教育主任の白鳥庫吉から相談を受けた澤柳政太郎は「杉浦さんがよいではないか」と杉浦の名を挙げた(『伝記』二百六頁)。これに白鳥も賛同、東郷総裁の意を受けて小笠原長生子爵が改めて杉浦の人物について調査した結果、「杉浦といふ人は命がけで事に当る人だと思ひます」と報告した。東郷は「それだけ聞けばよろしい」と言って、直ちに決定したという。 続きを読む 先帝陛下の御学問─杉浦重剛「倫理御進講草案」大義名分
平泉澄先生『明治の源流』結び─感激と気魄は承久・建武の悲劇より
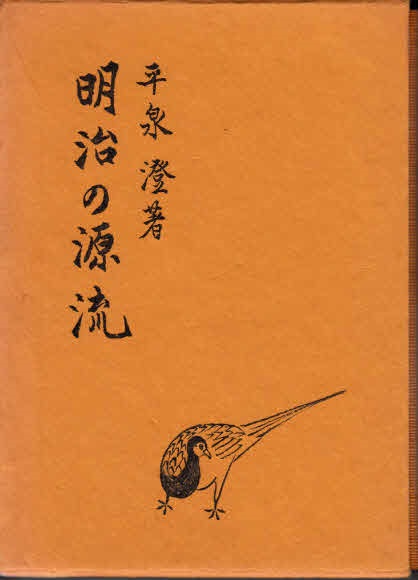 平泉澄先生は『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)を以下のように結んでいる。
平泉澄先生は『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)を以下のように結んでいる。
〈明治維新は、最後にその規模を高揚して、神武天皇建国創業の初めにかへるを目標としたものであつたが、あらゆる苦難を突破して國體の本義を明かにしようとする感激と気魄とは、之を承久・建武の悲劇より汲み来つたのであつた。就中、後醍醐天皇崩御にのぞんでの御遺勅に、
玉骨はたとひ南山の苔に埋もるとも、魂魄は常に北闕の天を望まんと思ふ。もし命を背き義を軽んぜば、君も継體の君に非ず、臣も忠烈の臣に非じ。
と仰せられた事は、申すもかしこし、楠木正成が最期に当つて、
七生まで只同じ人間に生れて、朝敵を滅さばや。
と願を立てた、あの剛気不屈、大義を守つて一歩も後へは引かぬ精神に、人々は無上の感動を憂え、不退転の勇気を與へられたのであつた。〉
『GHQが恐れた崎門学』書評6(平成28年12月5日)
皇學館大学教授の松本丘先生に『神社新報』(平成28年12月5日)で、拙著『GHQが恐れた崎門学』の書評をしていただきました。心より感謝申し上げます。
受け継がれる崎門学 現代的な意義も詳述
 崎門学、すなはち江戸前期の儒学者で、垂加神道を唱へた山崎闇斎の学問と、GHQといふ取合せに、やや意外の感を受ける向きもあるかも知れないが、本書を読み進んでゆけば、すぐにその理由が理解されるであらう。それほどにわが国の歴史における崎門学の存在感が大きいといふことである。
崎門学、すなはち江戸前期の儒学者で、垂加神道を唱へた山崎闇斎の学問と、GHQといふ取合せに、やや意外の感を受ける向きもあるかも知れないが、本書を読み進んでゆけば、すぐにその理由が理解されるであらう。それほどにわが国の歴史における崎門学の存在感が大きいといふことである。
著者の坪内氏は、これまで『月刊日本』誌上にて、近代志土たちの評伝や、明治維新の先駆となった先哲たちについての記事を長く連載され、また、崎門学研究会を開いてその顧問を務め、崎門重要書の精読を続けられてゐる。
さて本書では、「志士の魂を揺さぶった五冊」として、浅見絅斎の『靖献遺言』、栗山潜鋒の『保建大記』、山県大弐の『柳子新論』、蒲生君平の『山陵志』、頼山陽の『日本外史』が取り上げられてゐる。それぞれの内容はもとよりであるが、これらの書に崎門学が如何に滲透してゐるのかが明快に説かれてゐる。その記述には、高山彦九郎、真木和泉、吉田松陰をはじめとする勤王家はもちろん、近代の高場乱、権藤成卿といった人物まで登場してをり、明治の王政復古は、崎門学無くしては成らなかったことを改めて認識させられる。
これは、著者が説かれるやうに「君臣の大義の貫徹に支えられるわが國體が、自らの覚悟と実践に宿る」と信ずる崎門学徒の辛苦の営みによってもたらされたものであった。
著者は、本書にて強調せんとしたことを「大義によって時代が切り開かれた歴史であり、先人の行為を高みに立って批評家として論うのではなく、その尊さを仰ぎ見る謙虚な姿勢、さらに言えば國體護持に挺身した先人に自ら連なるうとする日本人としての自覚です」と纏められてゐる。かうした著者の真摯なる筆致からは、崎門の学脈が現代にも確乎として受け継がれてゐることを確信することができる。
なほ、補論では大宅壮一氏や最近の原田伊織氏の明治維新観が俎上に上げられ、痛烈な批判が展開されてゐる。さらに、著者と共に崎門学を研究されてゐる崎門学研究会代表の折本龍則氏による「いま何故、崎門学なのか」も附載されてゐて、崎門学の現代的意義も述べられてゐる。
本書の発刊に同学の一人として敬意を表すると共に、多くの有志によって繙れんことを祈る次第である。
原田伊織氏『明治維新という過ち』、『官賊と幕臣たち』徹底批判─維新の本義
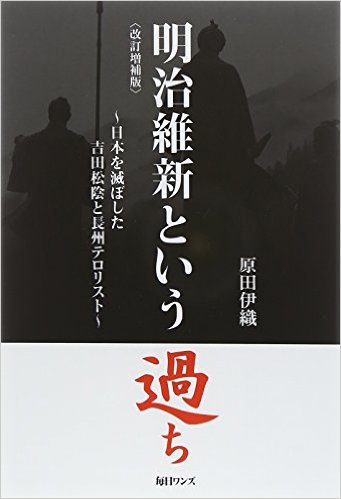 京都市では、「大政奉還150周年記念プロジェクト」が始動しました。いまこそ、明治維新の意味を日本人が見つめ直すときです。
京都市では、「大政奉還150周年記念プロジェクト」が始動しました。いまこそ、明治維新の意味を日本人が見つめ直すときです。
ところが最近、「明治維新という過ちを犯したことが、その後の国家運営を誤ることになった」という歴史観が流布されています。その代表的な著書が、原田伊織氏の『明治維新という過ち―日本を滅ぼした吉田松陰と長州テロリスト』、『官賊と幕臣たち―列強の日本侵略を防いだ徳川テクノクラート』、『大西郷という虚像』 です。
これまでも、「薩長による天皇の利用」や「薩長とイギリスの協力」という側面については、多くの論者が指摘してきたところであり、「薩長の権力奪取」という問題は、さらに探究されるべきテーマだとは思います。ただし、明治維新そのものを、大義なき権力奪取の物語として描こうとする史観が持て囃されることは大きな問題です。しかも、「七百年に及ぶ幕府支配を終わらせ、皇政復古を実現した」という明治維新最大の意義を無視した明治維新論が広がることは誠に憂うるべきことです。
水戸義公の『大日本史』編纂事業は、國體思想発展に重要な役割を果たしました。その過程で、『保建大記』を著した栗山潜鋒が義公に招かれて水戸藩に出仕し、崎門学の真髄が水戸学に導入されました。『保建大記』に象徴される、皇政復古を目指す潜鋒の國體思想は、藤田幽谷に継承され、やがて東湖へと引き継がれ、水戸学発展を牽引しました。そしてこの水戸学から、多くの幕末の志士たちが強い影響を受けました。
ところが、原田氏は水戸学を冒涜して憚りません。例えば、『明治維新という過ち』では、〈長州テロリストたちがテロリズムを正当化する論拠とした「水戸学」とは、実は「学」というような代物ではなかった。空疎な観念論を積み重ね、それに反する「生身の人間の史実」を否定し、己の気分を高揚させて自己満足に浸るためだけの〝檄文〟程度のものと考えて差し支えない〉と書いています。
さらに、〈『大日本史』という「こうあらねばならない」という観念論による虚妄の歴史書編纂に血道を上げた。その元凶ともいうべき存在が水戸光圀…〉、〈水戸の攘夷論の特徴は、誇大妄想、自己陶酔、論理性の欠如に尽きる〉などと、言いたい放題のことを言っています。
原田氏の吉田松陰に対する批判は、引用するのも憚られるほど酷いものです。
〈ひと言でいえば、松陰とは単なる、乱暴者の多い長州人の中でも特に過激な若者の一人に過ぎない。若造といえばいいだろうか。今風にいえば、東京から遠く離れた地方都市の悪ガキといったところで、何度注意しても暴走族を止めないのでしょっ引かれただけの男である。…思想家、教育者などとはほど遠く、それは明治が成立してから山縣有朋などがでっち挙げた虚像である〉
松陰は水戸学によって國體思想に開眼し、さらに浅見絅斎の『靖献遺言』をはじめとする広範な書物を読破するなど、獄中にあっても精進し続けました。
原田氏の暴論は、國體思想に対する彼の無理解からくるのでしょうが、國體を守るために挺身した先人に対する畏敬の念の欠如を恐ろしく感じます。
不断の実践によって國體が維持されてきた歴史を歪めるこうした原田氏のような言説が流布することは看過できません。(さらに詳しくは『GHQが恐れた崎門学』)
明治維新の本義
 明治維新の本義について書いた、拙著『GHQが恐れた崎門学』のまえがきの一部を紹介する。
明治維新の本義について書いた、拙著『GHQが恐れた崎門学』のまえがきの一部を紹介する。
〈崎門学に連なる志士たちは、このわが国本来の姿が容易には実現されないことを理解していました。多くの先覚者たちが天皇親政の理想に目覚め、その理想の実現を志したものの、それを阻まれ失意のうちに斃れたことに深い思いを抱いていました。
遡れば、後鳥羽上皇、後醍醐天皇、楠正成らの忠臣、徳川幕府全盛時代に弾圧された竹内式部や山県大弐らの先覚者──。困難な状況において孤高の戦いを挑み、敗れてもなお、その志だけは歴史に留めようとしたこれらの先覚者に、自らも連なろうとしたのです。この思いこそが、幕末の志士たちの鉄のような意志を支えていたのです。本書では、この意志の継承の具体的事例を描きます。巻末に掲載した年表からも、斃れてもなお遺志を継がんとする志士たちの魂のリレーの歴史が浮かび上がってくると思います。
例えば、崎門に連なる高山彦九郎の魂を継ごうとする強烈な思いこそが、蒲生君平の『山陵志』だけではなく、頼山陽の『日本外史』執筆の原動力となっていたようです。
残念ながらいま、「天皇親政こそがわが国のあるべき姿だ」という認識は失われています。敗戦後、「天皇親政はわが国の歴史の例外だ」という主張が幅を利かせてきたからです。津田左右吉の「建国の事情と万世一系の思想」(『世界』(昭和二十一年四月)以来、「天皇不親政論」が流布し、石井良助氏らの研究によってさらに強化されていきました。これに対して、平泉澄は、昭和二十九年の講演において次のように語っています。
「藤原氏が摂政、関白となつたこともありますし、武家が幕府を開いたこともありますし、政治は往々にしてその実権下に移りましたけれども、それはどこまでも変態であつて、もし本来を云ひ本質を論じますならば、わが国は天皇の親政をもつて正しいとしたことは明瞭であります。(中略)従つて英明の天子が出られました場合には、必ずその変態を正して、正しい姿に戻さうとされたのでありまして、それが後三条天皇の御改革であり、後鳥羽天皇倒幕の御企てであり、後醍醐天皇の建武の中興であり、やがて明治天皇の明治維新でありましたことは申すまでもありません」(「國體と憲法」『先哲を仰ぐ』所収)
この立場に立たなければ、明治維新の意義を正しく理解することは到底できません〉(6~7頁)
