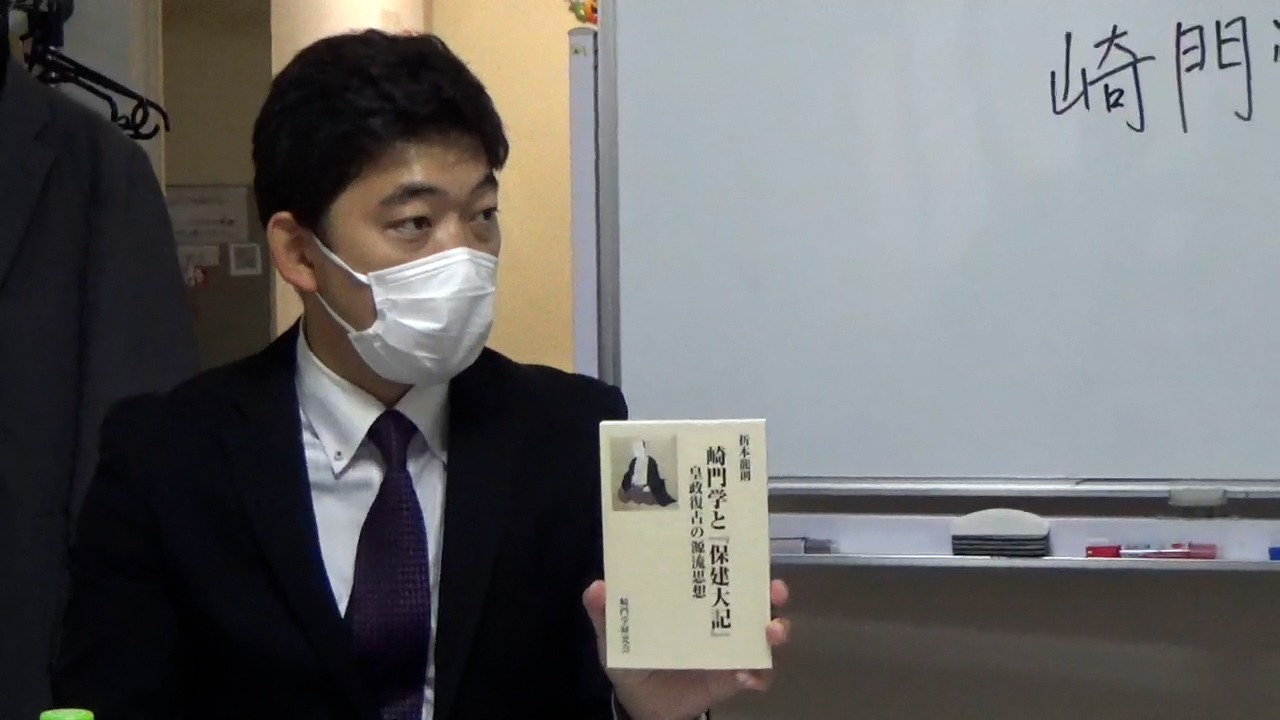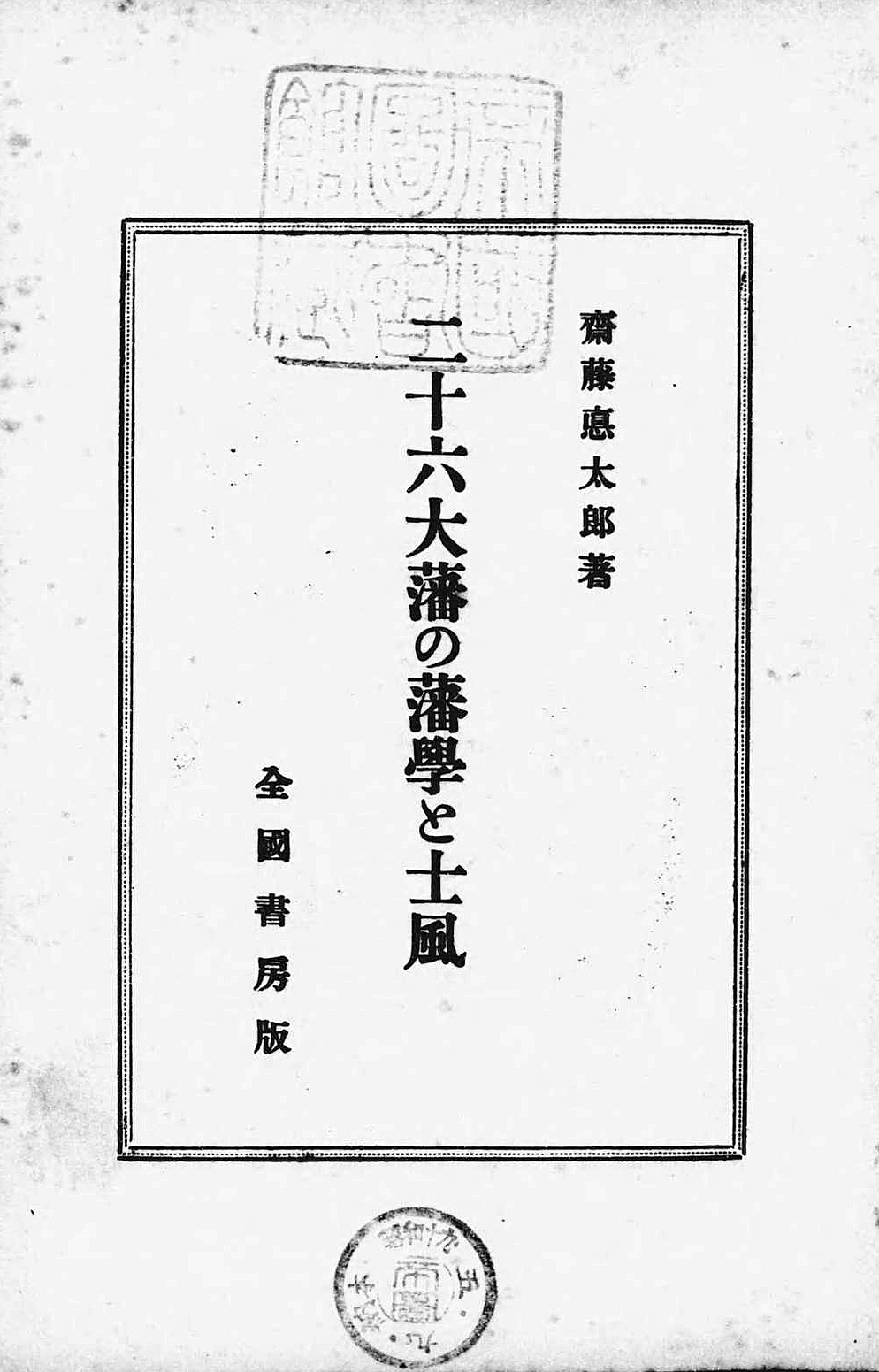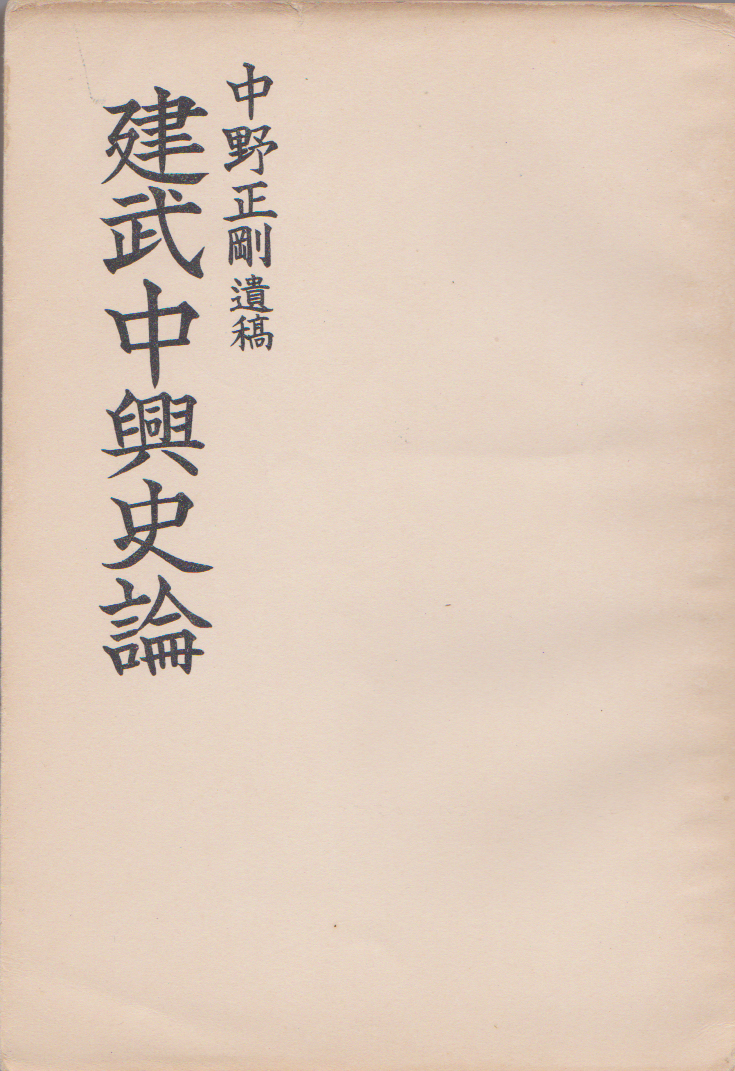井尻千男氏は、『歴史にとって美とはなにか 宿命に殉じた者たち』において、醍醐天皇の土地政策について以下のように書いている。
井尻千男氏は、『歴史にとって美とはなにか 宿命に殉じた者たち』において、醍醐天皇の土地政策について以下のように書いている。
〈醍醐帝の勅によって誕生した『古今和歌集』について語る前に、醍醐帝の土地政策について語らねばならない。なぜならば、日本史における土地政策の原型とも言うべきものが、この帝によってつくられたと思えるからである。それは延喜二年(九〇二)に出された「荘園整理令・勅旨開田および荒田・山野占有禁止令」と言われるものである。
土地所有に関する再検討は、わが国史において何度か行われているが、それはみな天皇の名によってこそ可能だったことであり、それこそが「天皇親政」の一大事業だったと言える。
醍醐帝は、その一大事業を即位して六年目に実行された。勅撰和歌集編纂とともに特筆大書されるべきことである。天皇陛下の「御製」というものが特別の意味を持つことと並んで、土地なかんずく農地に関する詔勅は、「大御宝」たる国民との太い絆だったと言える。つまり「大御心」と「大御宝」の信頼関係の再構築にほかならず、その意味において土地政策は「天皇親政」という政治形態の核心に位置づけなければならない。そしてこの「大御心」と「大御宝」の信頼関係は、わが国史において一貫して流れているものである。例えば時代がくだって明治維新の時の「版籍奉還」(明治二年)も錦の御旗あってのことであり、大東亜戦争後の被占領期における「農地解放」も、天皇陛下のご存続あってのことである。ついでに言えば国史に何度となく記されている「徳政令」も天皇の名のもとに行われてこそ意義があるのであって、その典型的事例が、後醍醐天皇が発した「徳政令」(建武元年、一三三四年)である。そして、この徳政令という形での世直しも、わが国独特のものである。
醍醐帝のこの世直しのための土地政策は、まさに「親政」の大号令と言ってよいだろう。先帝宇多は譲位直後に剃髪して上皇(法皇)になられておられるから、その土地政策にどこまで関与しているかは不明であるが、自ら抱いた「親政の夢」がここで大きく花ひらいたと、よろこばれたことは疑いようがない。そして後代の我々としては、宇多・醍醐両帝の理想主義の連続性におどろかされるのである。
その土地政策すなわち「延喜の荘園整理令」の骨子は次のようなものである。
①当代以降の勅旨田設置の全面禁止。すなわち皇室の私有地を増やしてはならない。
②諸国百姓の田地、舎宅の寄進および売与を禁止。つまり百姓からの寄進も受けてはいけない。
③院宮王臣家が閑地・山野などを占有することを禁止。閑地とは耕さずに荒れはてた農地のことだが、それすらも占有してはならないというのである。
④院宮王臣家が、百姓の私宅を荘家と号して稲穀を蓄積してはならない。すなわち宮の倉庫に納めるべきものを隠してはならない、ということ。脱税防止策にほかならない。
以上四点が「延喜荘園整理令」の骨子であるが、これを単なる徴税のための改革と見てはいけない。その整理令につづけて、「班田を十二年に一度とする」という令を出していることからして、かつての「班田収授法」(白雉三年・六五二年)の理想に戻ろうとしていると解釈せねばならない。つまり、「大化改新」(六四五)に始まり、大宝律令(七〇一)によってほぼ完成したところの、わが国における理想の土地政策を復元しようとしたのだと見なければならない。
そのように解釈してみると、表面的には土地政策ではあるが、その精神に内在するものは「復古革命」だったのではないか。そう解釈することによって、見えてくるものがある〉(119、120頁)