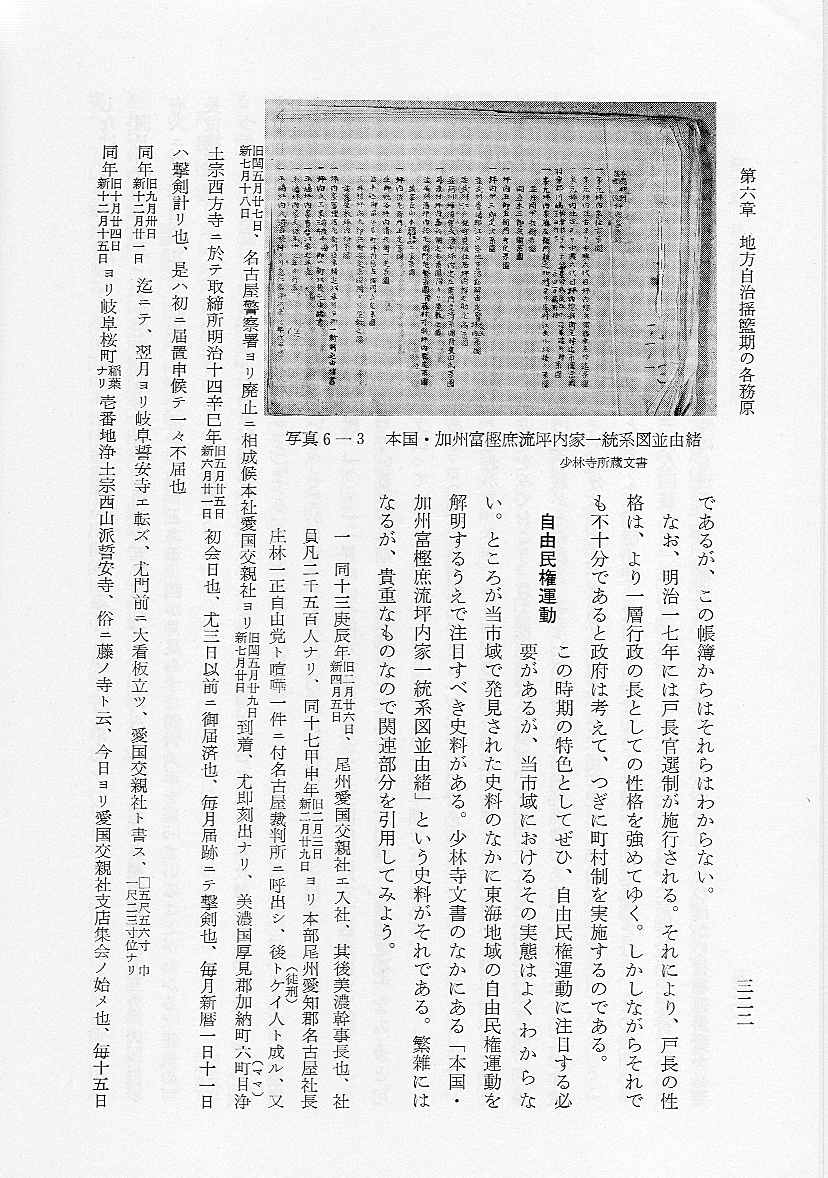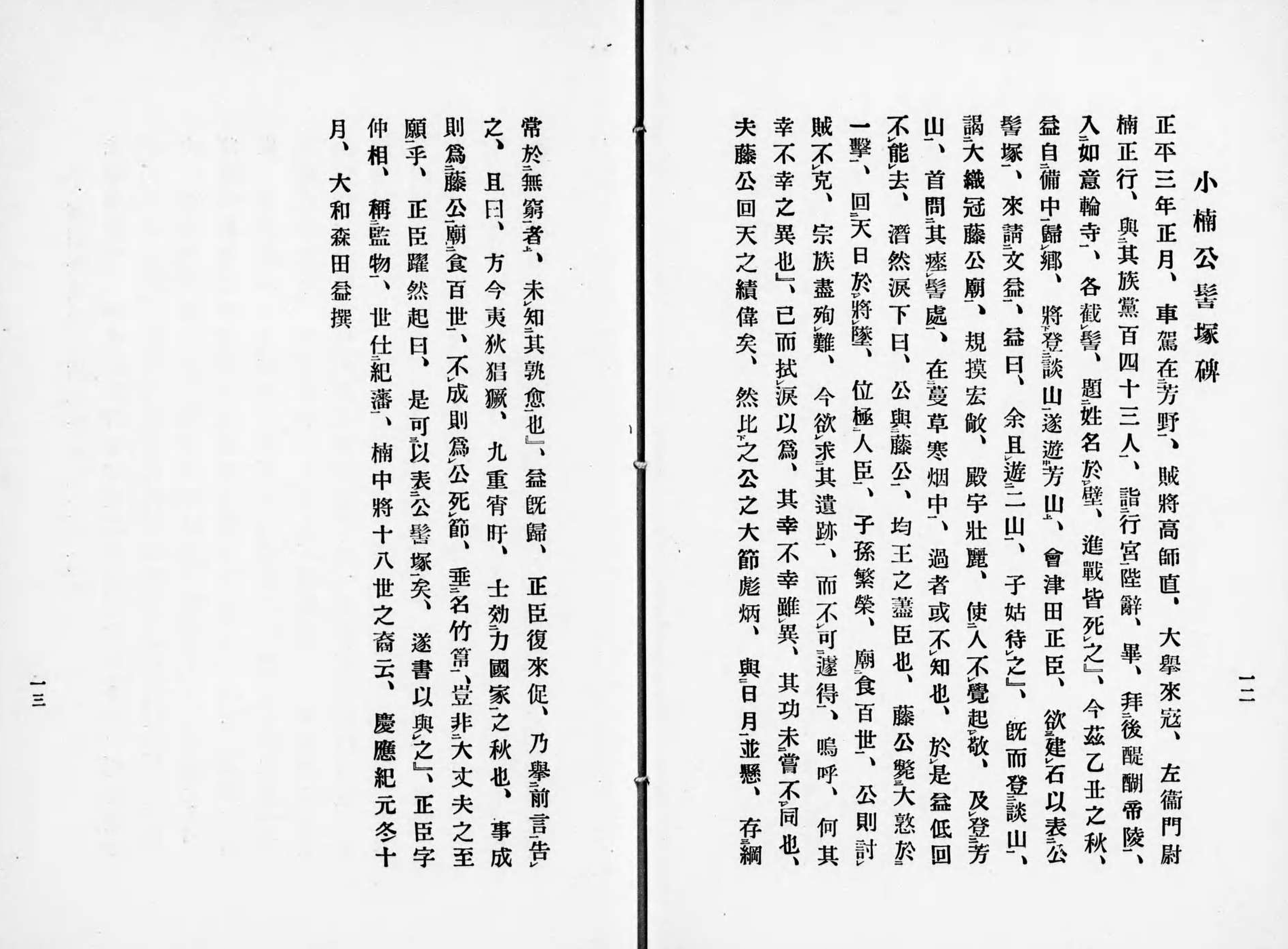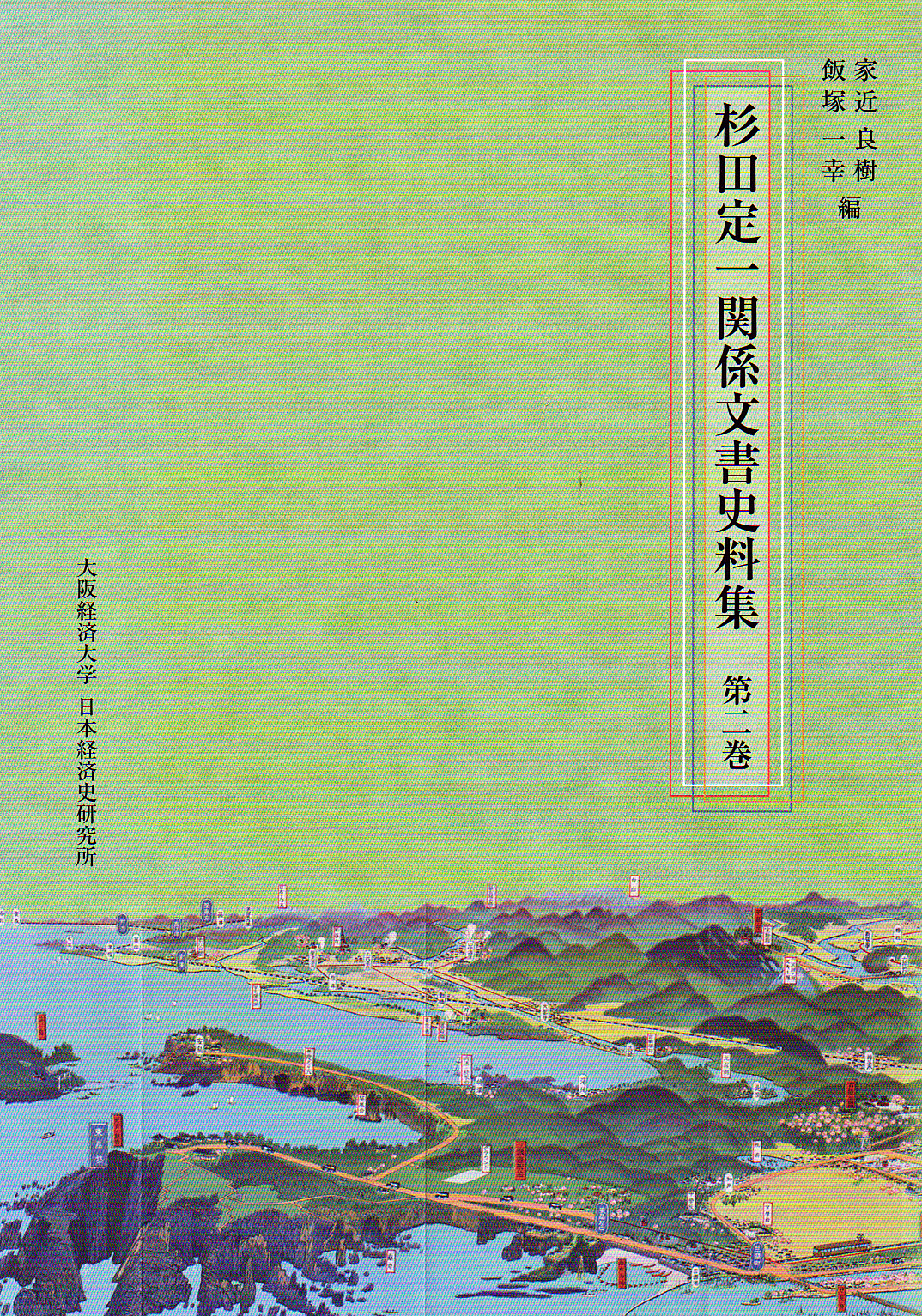 家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
家近良樹・飯塚一幸編『杉田定一関係文書史料集 第2巻』(大阪経済大学日本経済史研究所発行、平成25年)には、杉田定一と愛国交親社との関係を示す資料が収録されている。内藤魯一が杉田定一及び村枩才吉宛てに送った書簡「北陸七州有志懇親会欠席及び庄林一正・村松愛蔵へ出席」(明治16年2月5日)である。
〈北陸懇親会ノ義ニ付御照会ノ趣ハ社会ノ為メ慶賀ノ至ニ候、然ルニ小生事ハ盟兄御承知ノ通り上京ノ都合ニも相成リ、殊ニ二月下旬三月上旬迄ニハ高知ゟ島地正存来訪ノ筈ニ有之、過日来態々中来候趣も有之、又且ツ三月上旬ニハ我地方ノ党員ハ岡崎ニ会シ候手筈ニ客年十一月中予テ申合有之、旁遺憾ナカラ此段御承知被下度、但シ庄林ハ是非ニ相拝候様申入置候、且ツ外ニ村枩愛蔵氏ニハ多分出席仕リ度旨拙者迄申越居候間、尚相勧可申候、実ハ過日当懇親会ニも遠路之気嫌も無ク御出会被下候、交義上ニ於テモ是非出会可仕筈ナレ共、如何セン前陳ノ通リニテ生義ハ繰合都合相兼候、御推察ヲ乞、尚御来会諸君ニ可然御通声是祈ル
追白、天下ノ事ハ只タニ表面上ノミノ働ニテハ遂ニ目的ヲ達ス可カラザル事ハ歴史ノ裁判ニ於テ明カナリ、故ニ以来ハ別テ御注意、神出鬼没兎角○○ノ意外ニ出テ秘々密々御計画アレ、嗚呼御互ノ任も亦大ナルカナ、書意ヲ尽サス否ナ尽サヽルニアラス、尽スコト能ハサレハ也〉