木戸孝允は、すでに明治二(一九六九)年九月時点で、古松簡二、河上彦斎、大橋照寿、初岡敬二の四人に対する警戒感を高めていた。
初岡は秋田藩勤皇派の代表的人物であり、幕末から活動、藩校明徳館の本教授を務めた。戊辰戦争で苦戦する中で上京し、公務人として政府出兵のため強力な要請運動を行った。
 明治二年七月初め、初岡は招魂社大祭にキリストを踏みつけている武者像の大幟を秋田藩から献納しようとした。幟には「天涯烈士皆垂涙、地下強魂定嚼臍」と書かれていた。しかし、軍務局から献納を却下されている。
明治二年七月初め、初岡は招魂社大祭にキリストを踏みつけている武者像の大幟を秋田藩から献納しようとした。幟には「天涯烈士皆垂涙、地下強魂定嚼臍」と書かれていた。しかし、軍務局から献納を却下されている。
九月になると、初岡は「奸可斬、夷可払」とうたいながら剣舞するという事件を起こした。いわゆる「剣舞事件」である。ここで言う「奸」とは、木戸孝允、大村益次郎、後藤象二郎を指したものと解釈されたのである。実際、同月大村は暗殺されている。
宮地正人氏は、次のように書いている。
〈このような対立は月が進むにつれてより深刻なものとなり、ますます維新政府の権力基盤を不安定化させてゆく。「集議院廃セラレザレドモ、公議人ハ皆帰休ヲ命ゼラレタル由、弁官ニテ議ヲ発スレバ集院之ヲ討テ非トシ、集議院建白スレバ弁官害アリトシテ不行、毎事ニ途ニナリテ不一揆、政事是ガ為ニ壅滞シ、両党相争ノ姿アリ、不可両立勢也卜云」と、一八七〇年一月段階では受けとめられるようになる。まさに「両党相争」の事態である。これが同年九月段階にいたると、権力基盤の不安定化は極限状態に達する。同月一〇日集議院が閉会、その後の見込が立たなくなるのである〉
「開国和親」カテゴリーアーカイブ
中沼了三から十津川郷士への通信─洋癖批判
宮地正人氏の「廃藩置県の政治過程」によると、明治二(一八六九)年六月十日、十津川郷士に以下のような通信があったという。
「朝廷ニハ追々御変革ニて、議院は頗る正論、屹度国家ノ柱礎と相成申侯、洋癖は大ニ折れ侯……段々有志ノ者ニも沸騰ニ付、驕奢ノ体は大ニ相折れ」
洋癖と驕奢に対する批判の高まりを示すものである。
これを書いたのは、崎門学派の中沼了三らしいと見られている。中沼は、明治四年には明治政府から排除される。
日本の歴史を棄てた明治政府
平泉澄先生は「日本精神について(下)」(『日本』平成十八年正月号所収、二~三頁)において、次のように述べている。
〈明治五年に教育制度が発動されてをります。驚くべきことに明治五年の学制には日本の歴史を教授するといふことが出てをらない。一国の教育がその国の歴史を無視してなされるといふことは実に驚くべきことであります。
これは明治元年の大精神には断じてないことであります。明治元年の大精神が四、五年ですっかり崩れてをります。明治維新の精神はその時は日本の古典を用んとして、一方に支那の漢籍、一方に西洋の学問、それを両翼として進まうといふことを新定学制に示されてをります。
実に偉い精神でありますが、これは間もなく崩れて、明治五年の学制においては日本の歴史は教育から棄てられてしまった。その後小学校においてその非を悟って、国史を加へましたのは明治十四年のことであります。十四年に初めて日本の初等教育に日本歴史が入って来たのであります。これは明治天皇の特別の御注意を戴いて出来たことださうであります。
しかしそれ以上の学校においては、まだ日本歴史は加へてをりませぬ。中等以上の学校においてはバーレーの「萬国史」が用ひられてをりました。その後高等の学校に初めて日本歴史が入って来たのは明治十六年であります。これはドイツ語の先生のグルートといふ人が注意をしたので、初めて国史が入って来た。ただし大学にはまだ国史は出てをりませぬ。大学において国史、日本歴史が一科として立てましたのは明治二十一年になります。
さうしてその翌二十二年に国史科が新設されてをります。この時に渡邊総長の意を受けて色々案を立て、これを実施する上において努力しましたのがドクトル・リースの力であります。その時までは国語を棄てようとしたほどでありますから、日本歴史を棄ててしまって、外国人から注意されなければ日本の歴史は閑却してしまってゐた〉
明治新政府の屈辱外交─神戸事件の処理
 慶応四(一八六八)年一月十一日、岡山藩兵が神戸行軍中、英仏米の兵士と紛争を起こし発砲した。外国軍隊が一時神戸中心部を占領するまで発展したが、発砲責任者の岡山藩士・滝善三郎を切腹させて事件は解決された。
慶応四(一八六八)年一月十一日、岡山藩兵が神戸行軍中、英仏米の兵士と紛争を起こし発砲した。外国軍隊が一時神戸中心部を占領するまで発展したが、発砲責任者の岡山藩士・滝善三郎を切腹させて事件は解決された。
内山正熊は『神戸事件―明治外交の出発点』において、次のように指摘している。
「もしこの事件が幕末年間に起ったとしたならば、生麦事件のように外国人を殺傷したわけでもないこの事件は、単なる一渉外事件として片づけられたであろう。……
しかし、神戸事件の場合には開国和親の新政府声明がだされる前に勃発したものである。そこで、仮に日本側が外国人を殺傷したとしても、維新政府は攘夷の国策をいまだ続けていたのであるから、備前藩兵を処罰する根拠がなかったわけであって、本件での責任者は切腹する必要はなかった。したがって、責任者瀧を新政府が処断したのは、いわば超法規的措置によったことになる。それは、維新政府が、理不尽な外国の要求の前に一も二もなく、ただ平身低頭して陳謝屈伏した屈辱的外交にほかならない。……
明治維新は、対内的にこのような矛盾痛恨を包蔵した大変革であったが、対外的にもまたまさに鷲天動地の大改新であった。なぜならば、朝廷が倒幕の旗印であった尊王攘夷をすてて、開国和親へと百八十度の基本国策転換を行なったからである。その転拠の契機となったのが神戸事件であった。そして、その転換の過程で犠牲となったのが瀧だったのである」
「攘夷から開国和親」への反応
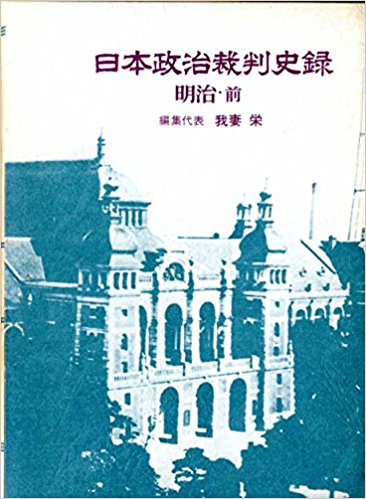 我妻栄編『日本政治裁判史録 明治・前』(昭和四十三年)は、備前・土佐藩兵発砲事件(神戸事件・堺事件)を以下のように説明している。
我妻栄編『日本政治裁判史録 明治・前』(昭和四十三年)は、備前・土佐藩兵発砲事件(神戸事件・堺事件)を以下のように説明している。
「尊皇攘夷運動の指導者たちは、列国の軍事力に対抗できないと覚った時、尊王倒幕に転じて王政復古政府を樹立し、開国和親政策への転換を志しつつあったことは周知である。けれども、士族層の間に広く浸透して来た攘夷主義が、一朝の政策転換によって消滅するものではなかった。従って、外国人が国内を通行する度ごとに、外国人襲撃事件が発生する危険性はたえず伴なっていた。新政府が慶応四年二月、開国和親政策を宣言する以前はもとより、それ以後においても、いくつかの外国人襲撃事件がおこっている。
このうち、開国和親の宣言以前におこった攘夷事件として大規模なものが、すなわちここで取り上げる相つぐ二つの外国人殺傷である。一つは、神戸事件と呼ばれて、慶応四年正月十一日、備前藩兵がアメリカ人およびフランス人に対して威嚇もしくは発砲したもの、ついで堺事件と呼ばれて、同年二月十五日、土佐藩兵がフランス水兵に発鉋した事件である」
「万一異人に京都をとられたら、先帝へ対してそれこそ申訳がない」─後宮に対する東久世通禧の説得の論理
 慶応4(1868)年2月15日、天皇が西洋諸国の公使を謁見されることが公にされると、朝廷内では後宮が騒然となった。東久世通禧の談話記録「竹亭回顧録・維新前後」には、次のようにある。
慶応4(1868)年2月15日、天皇が西洋諸国の公使を謁見されることが公にされると、朝廷内では後宮が騒然となった。東久世通禧の談話記録「竹亭回顧録・維新前後」には、次のようにある。
〈奥の宮女が大反対で、中山慶子が主動者で、奥は総体に於て根本から不同意、第一異人を御所へ召す事から不服で、天皇御対面なぞは以ての外の事と皆泣て騒ぎ立てる。……宮中の反対は大きな問題から割出して居る。先帝はあれほど異人をお嫌ひなされた。然るに、其御子として異人を御所へ入れ謁見を賜つては、先帝へ御不孝である。天子様を不孝にしては相済みますまいと云ふ。三条はもと攘夷論の本家で、先帝へも攘夷親征をお勧め申した人であるから、宮女を説諭する資格が乏しい。また誰にしても、女がガヤガヤ騒ぎ立てるのを説付るは困難であるから、吾進んで説諭しやうと云ふ者は一人もない。廟堂では大に持余した時、岩倉がコレは東久世がよい、外の者では迚もいくまいと卿(東久世を指す)を招ぎ〉
〈中山慶子初め尚侍、典侍など云ふ重立た宮女を呼び出し、先づ一通り彼等が主張する処をきゝ、いかにも御尤な意見である。吾等も実は異人大嫌ひで、彼等に面会するのは穢しく存ずる事なれば、陛下謁見を賜はると云ふこと甚だ好ましからぬ事である。然るに、之を断れば、彼等は外国の天子の名代を軽蔑されては、自国の天子の御恥辱になる。君辱めらるゝ時は君死すべき筈なれば、六ケ国の兵隊を引つれ、直に京都へ打て入ると云ふ次第で、是には殆ど当惑いたしてゐる。当節諸藩の兵皆関東へ下り、京都は至つて御手薄である処、六ケ国の兵隊は大軍であるから一日も防ぐ事は出来ぬ。万一京都へ乱入いたせば、日本の女をば捕へて外国へつれてゆくかも知れぬ。その上京都は焼き立てらるゝは必定也。御所も無事ではあるまいと思ふ。其でも一切異人は御所へ入れぬと云ふ訳には行かず、余儀なく各国普通の例によつて謁見を賜り、無事を繕ふ外あるまいと思ふ。万一異人に京都をとられたら、先帝へ対してそれこそ申訳がないと懇ろに話されて、さしも大反対の宮女も返す辞がない。とうとう泣寝入りの姿で、奥の方は忽ち鎮静に及んだのである〉
