佐藤清勝は『世界に比類なき天皇政治』緒言冒頭で、西洋人の不幸な歴史は、彼らが理智ばかりを重視し、感情を軽視してきた結果だと断じる(二頁)。
西洋人の歴史は、佐藤によれば、苦難の連続だった。まず、教権全盛時代には法皇僧侶などの人情なき抑圧に苦んだ。そして、君権全盛時代には、君主貴族などの愛情なき虐政に苦んだ。民権全盛となってからも、政党者や金権者の恩恵なき強圧に苦しんできた。
西洋人は「理智的反抗心」により、信仰の自由を叫んで僧侶の暴圧を絶呼し、天賦の人権を叫んで君主権の非理を主張し、階級争闘を叫んで資本家の専横を怒号するというように、絶えず現状を打破して、新しい境遇を得ようとして、大声で激しく叫んできた。佐藤は、それこそが西洋の政治思想だと説き、次のように書く。
「彼等は常に現状を打破し、現社会を改造して新正面を開かんとする努力は、益々彼等を躯つて奈落の底に沈淪せしむるものである、而して、今や彼等は国家を否認し、民族を忘却し、政治を嫌悪し、而して、世界主義に傾きつつあることは、即ち、彼等民族自滅の深渕に向つて急ぎつつあるのである」(四頁) 続きを読む 佐藤清勝『世界に比類なき天皇政治』(昭和十八年六月)読書ノート①
「著作/文献」カテゴリーアーカイブ
ある書棚から
書籍
| 著者 | 書籍写真 | 書名 | 出版社 | 出版年 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 片岡鉄哉 |  |
“黒船待ち”の日本―ゴーリズム国家をめざして | 日本教文社 | 1982年1月 | |
| 田中正明 |  |
アジア独立への道 | 展転社 | 1991年7月 | |
| 竹内好 | 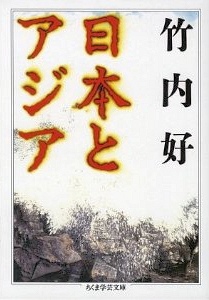 |
日本とアジア | 筑摩書房 | 1993年11月 | |
| ムハンマド・バーキルッ=サドル著、黒田寿郎訳 |  |
イスラーム経済論 | 未知谷 | 1993年12月 | |
| マハティール、石原慎太郎 |  |
「NO」と言えるアジア―対欧米への方策 | 光文社 | 1994年10月 | 続きを読む ある書棚から |
ドキュメンタリーDVD(歴史・戦争)
| 写真 | タイトル | 価格(円) | 枚数 | 時間(分) | 販売元 | 発売日 | 内容 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
 |
NHKスペシャル 日本海軍 400時間の証言 DVD-BOX | 8,777 | 3 | 251 | NHKエンタープライズ | 2012/03 | 日本海軍のエリートたちによる告白とは――1980(昭和55)年から11年、130回余りにわたり、かつての日本海軍の参謀たちが密かに集い、議論を重ねていた。「海軍反省会」 |
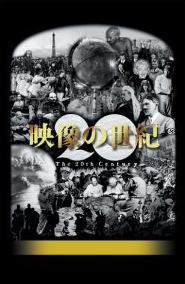 |
NHKスペシャル 映像の世紀 SPECIAL BOX | 64,328 | 12 | 873 | NHKエンタープライズ | 2005/11 | 激動の20世紀を映像で記録したロングセラー作品が、豪華解説書とDVD別巻を加えてリニューアル! |
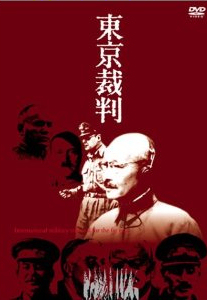 |
東京裁判 | 3,135 | 2 | 277 | キングレコード | 2004/08 | 小林正樹監督。昭和23年、東京都市ヶ谷の旧陸軍省参謀本部において開かれた「陸軍国際軍事裁判」の模様を収めた米国防総省の記録フィルムを基にしたドキュメンタリー映画 続きを読む ドキュメンタリーDVD(歴史・戦争) |
祖国自己確認の歴史における『中朝事実』
 わが国の歴史は、国体論の確立を目指した持続的な営みであった。その中で、国際情勢の変化、特に対外的危機意識の高まりは、常に祖国日本の自己確認を促してきた。
わが国の歴史は、国体論の確立を目指した持続的な営みであった。その中で、国際情勢の変化、特に対外的危機意識の高まりは、常に祖国日本の自己確認を促してきた。
永安幸正は、「何れの国民でも同じであるが、国民集団としてある種の危機が迫っていると感づく秋には、祖国あるいは民族を世界の中に位置付け、他国と比べて祖国自民族の歴史、実力、可能性を確かめなければならぬものである」と指摘する。
山鹿素行の『中朝事実』もまた、繰り返されてきたわが国の自己確認の歴史の一時代として位置づけられる。永安は、『中朝事実』執筆の目的を、①国家創設及び創設後の政治における要点の解明、②国際関係において、日本列島上のわが国こそが中朝・中華・中国(なかつくに)であることの主張──に整理した上で、次のように『中朝事実』を、繰り返されてきた祖国自己確認の試みの歴史の中に位置づける。 続きを読む 祖国自己確認の歴史における『中朝事実』
『中朝事実』の評価①
 昭和八年に文部省社会教育局が「日本思想叢書第八編」として刊行した『中朝事実』の解題には、次のように書かれている。 「…儒学の主張する名分や祭祀の義は我が国に於て完全に実現されてゐる。国典と儒学とを並び究むれば此の事が分明して、我が国を以て世界無比の国体となし、天皇の尊厳なるを覚るのである。先生(素行=引用者)は徳川初期に生れ、国学尚ほ未だ勃興せす、水戸学尚ほ未だ興起せざる以前、我が国体の美を称揚し、我が国を中華中国といつた識見の高邁には驚くではないか。是れ先生が大に我が国民道徳に貢献した所以である」(同書二十二頁) 続きを読む 『中朝事実』の評価①
昭和八年に文部省社会教育局が「日本思想叢書第八編」として刊行した『中朝事実』の解題には、次のように書かれている。 「…儒学の主張する名分や祭祀の義は我が国に於て完全に実現されてゐる。国典と儒学とを並び究むれば此の事が分明して、我が国を以て世界無比の国体となし、天皇の尊厳なるを覚るのである。先生(素行=引用者)は徳川初期に生れ、国学尚ほ未だ勃興せす、水戸学尚ほ未だ興起せざる以前、我が国体の美を称揚し、我が国を中華中国といつた識見の高邁には驚くではないか。是れ先生が大に我が国民道徳に貢献した所以である」(同書二十二頁) 続きを読む 『中朝事実』の評価①
佐藤清勝『世界に比類なき天皇政治』コンテンツ
佐藤清勝『世界に比類なき天皇政治』コンテンツ
緖論 1
第一篇 西洋政治の論評 8
第一章 西洋政治学に対する批判 8
第一節 総説 8
第二節 国家観に対する批判 10
第三節 法律説に対する批判 12
第四節 君主政治説に対する批判 17
第五節 民主政治説に対する批判 22
第六節 共産政治説に対する批判 25
第七節 批判の綜合 30
第二章 西洋政治学の欠点 31
第一節 総説 31
第二節 政治反抗の思想 33
第三節 権力統制の思想 36
第四節 為政者人格無視の思想 40
第五節 法律統治の思想 43
第六節 道德感情無視の思想 46
第七節 理智偏重の害 49
第三章 西洋政治の実際 50
第一節 総説 50
第二節 西洋政治史の梗概 52
第三節 英国憲法の成立過程 61
第四節 議会政治の実際 71
第五節 議会政治の本質 75 続きを読む 佐藤清勝『世界に比類なき天皇政治』コンテンツ
佐藤清勝『世界に比類なき天皇政治』
大井一哲『建国由来と皇道政治』⑦
大井一哲は『建国由来と皇道政治』結論において、教育勅語、戊申詔書、大正天皇の御即位式における勅語、昭和天皇の御即位式における勅語など、明治から昭和初期の詔書・勅語を引いた上で、次のように政府の姿勢を糺した。
「是等の勅語を奉戴したるその当時の総理大臣以下国務大臣は、恐懼して相戒しめ、謹んで聖旨の全国に普及徹底するやう鞠躬尽瘁(きっきゅうじんすい)すべきであつた。しかも彼等は放縦に流れ傲慢に傾き居れる一部国民の歓心を買うことにのみ急であつて、自ら率先して模範となり、忠孝の道、信義勤倹の実、忠実奉公の誠、敬忠奉上の義を国民に訓ゆることを忘れて了つた」
大井は、結論として、全国民が一心同体となり、日本精神を発揮して、政党政治を全滅しつくすべぎだと主張するのである(159―165頁)。
大井一哲『建国由来と皇道政治』⑥
皇道政治の理想を追求大井一哲は、明治維新後のわが国の政治形態をどのように見ていたのであろうか。
彼は、慶応4年 (明治元年) 3月14日(1868年4月6日)に明治天皇がお下しになった五箇条の御誓文を高く評価した。
一、広ク会議ヲ興シ万機公論ニ決スヘシ
一、上下心ヲ一ニシテ盛ニ経綸ヲ行フヘシ
一、官武一途庶民ニ至ルマデ各其ノ志ヲ遂ゲ、人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス
一、旧来ノ陋習ヲ破り、天地ノ公道二基クヘシ
一、知識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スヘシ
大井は御誓文について「実に国是の大本を確定せられた大文字であつて、憲法の制定も、議会の開設も、みなこの中に含蓄されてゐることは云ふ迄もない。斯の如くにして君民一如、一君万民の政治は茲に恢復せられたのである」ととらえた(120―121頁)。
ところが、その後の展開は大井の期待を大きく裏切るものだった。彼は概要以下のように述べている。
藩閥内閣、官僚内閣は、いずれも官権万能を守持して、天皇政治の目標とする下層多数国民に圧迫を加えたことにおいて同じだった。富豪と結託し、政商の請託を容れ、彼らに特別の保護を与えることも同じだった。このような事態に直面し、自由民権論者は藩閥政府、官僚政府の打倒に向かい、官権と民権とは随所で衝突し、藩閥と政党は互いに反目するに至った。やがて、大正七年に純然たる政党内閣として原敬内閣が成立したが、事態はさらに悪化していった(118―123頁)。
そして大井は、次のように激しく政党政治の実態を批判した。
「その富豪と結託し、政商を保護する点において、藩閥よりも、官僚よりも、その弊一層甚だしきを加へ、権勢を利用して限りなく利権を漁り、私曲を逞うして縦ままに自個を肥やすといふ醜状が暴露された。選挙の際にこそ『選挙第一主義』から、如何にも尤らしく一生懸命に、政見や政策をならべ立てて、あつぱれ国士の体面を装ふが、運よく当選して議会に入るや、忽ち仮面をかなぐり棄て、野獣のやうな本性を現はして、啀み合ひ、噛み合ひ、擲り合ひを演じて、神聖な議場を修羅の街と化して了ふ醜状は毎年議会の常例となつた」(126、127頁)
さらに大井は、政党政治は天皇御親政の反逆であり、皇道政治の賊だと断じ、君国のために一身を捧げる覚悟のある誠忠の人でなければ、天皇政治の下において内閣を組織して、輔弼の責任を全うすることはできないと強調する。
大井一哲『建国由来と皇道政治』⑤
大井一哲は、天皇親政時代に光耀いた大御心を、具体的事例を挙げて示した。
では、天皇非親政時代には、天皇の大御心はいかなる状況にあったのであろうか。
大井は『建国由来と皇道政治』第六章「天皇非親政時代の皇道政治」において、やはり具体的事例によってそれを明らかにしている。
まず、藤原氏が専横を極めるに至り、奈良、平安朝時代における皇道政治の影は薄れていった。その後、源平時代を経て、鎌倉幕府が成立する。以来七百年間、日本の政治は全く天皇の御手を離れ、武臣の掌中に帰していた、というのが大井の見方である。
だが、大井はこの時代にあっても、国家を思い、国民を憐れむ大御心は少しも変わらなかったと見る。
例えば、わが国が未曾有の国難に直面した弘安四年の蒙古襲来の時、亀山上皇は石清水八幡宮に行啓あらせられ、国家の安全を祈念し給い、敵国降伏の大額を筑前箱崎神宮に献じて、外敵撃退を祈念し給い、さらに手書を伊勢大廟に奉納して、身をもってこの国難に代わろうと祈らせ給うた。
だが、歴代天皇が堅持された大御心を実現することはかなわなかった。大井は、これは天皇非親政時代の歴代天皇の御製から窺い知ることができると説き、次のように書いている。
「もし之が御親政時代であつたなら、……仁徳溢るゝ詔勅となり、慈恵深き救恤となり、愛憫限りなき大赦特赦となつて現れたであらうことは、何人も容易に想像し得らるゝところである」(79―105頁)

