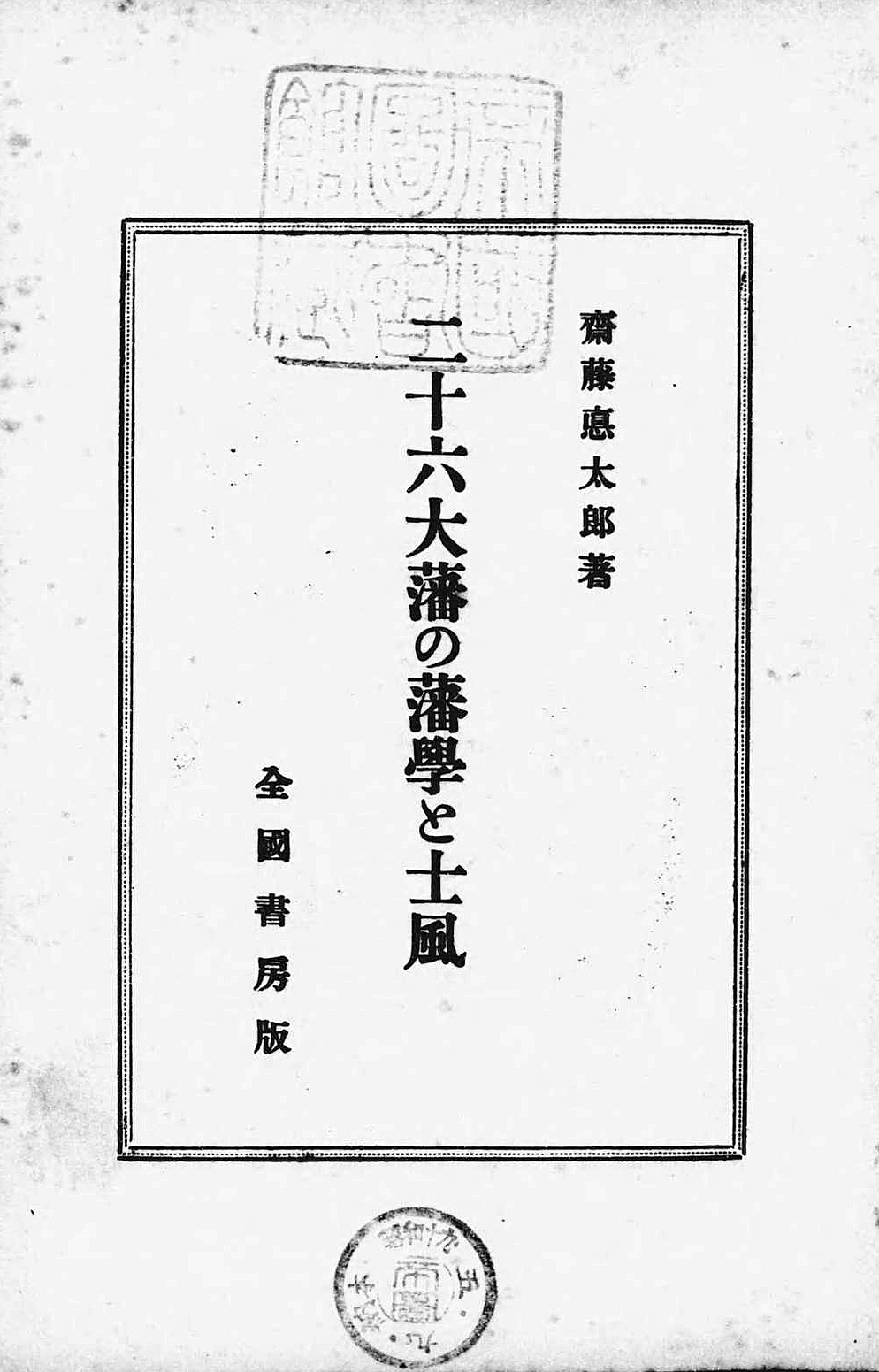 斎藤悳太郎『二十六大藩の藩学と士風』(全国書房、昭和19年)は、尾張藩の明倫堂について、以下のように書いている。
斎藤悳太郎『二十六大藩の藩学と士風』(全国書房、昭和19年)は、尾張藩の明倫堂について、以下のように書いている。
〈嘉永六年、尾張徳川家十四代の君主慶勝は、藩学明倫堂における文武修業について、藩士に対しこれを激励する九箇条の直書を発したが、武技稽古場に貼り出されたものは次のごときものであつた。
一、方今皇国の形勢不容易厄運に当り日々切迫に趨り不安之時節に候。然ば当家之儀は随一の親藩として諸藩の標的共可相成国柄に候処、昇平年久しく殊更四通八達之地故に自然之習士林之風気
柔情に移り易く、義勇発奮之武断は却而諸藩に謨候様相成侯而は、皇武祖先に奉対、忠孝之瑕瑾、万世不磨之恥辱と可相成誠以国家之苦心此事に止り候。就夫学校は一国士風之亀鑑に付先是より流弊一新之源を可開申存念侯間、何も此主意を身に体し発奮可有之事。
一、尾籍国校学生たる者、天下に押出して、夫程の人体に無之侯ては、可恥之至也。以来は文武之嗜、其格に叶侯者ならでは、学生は取立間敷侯。―─
時に明倫堂の督学は阿部松園であつたが、前年江戸に出て水戸の弘道館総裁となつた。前年督学正木梅谷の頃から校運やや振はず、一藩の士風また因循して進取の気を欠くものがあるので、慶勝座視するに忍びず、つひに直書を下して藩学を督励し、士気を鼓舞せんとしたものである〉
同書はまた、外国船が日本に頻繁に来るようになった文化年間(一八〇四~一八一八年)の明倫堂について、次のように書いている。
〈近年外国の艦鉛が来航して以来、物情騒然人心沸騰、天下漸やく事有んとする形勢になつたので、一藩の士人はいふに及ばず、学内の生員でも、すでに壮年以上のもの、また心ある教師らもひそかに『靖献遺言』や『新論』を読まざるものなきにいたつた〉
「『新論』」カテゴリーアーカイブ
大楽源太郎の私塾「西山書屋」規則、授業内容
大楽源太郎は慶応二年に私塾「西山書屋」(敬神堂)を開設した。塾規則、授業の日割は以下の通り。
●西山塾規則
一、第一君公の御主意を相守り、寮中親睦致し、練武学文懈怠なく勉強肝要之事
一、喧嘩口論高声堅く禁止之事付而俗曲同断之事
一、猥に外出堅く禁止の事但し難容用事之れ有候節は頭役座元へ相届外出致すべく侯
一、朔日十の日休日の事
一、朝六ツ時より五ツ時まで撃剣稽古の事
一、六ツ時より七ツ時まで読書稽古の事
一、暮六ツ時より四ツ時まで同断の事
一、二四六九日銃陣稽古のこと、但し四九日は九ツ時より七ツ時迄の事 其の余は諸稽古勝手次第の事
正月 敬神堂
右の条々堅相守侯事
●授業の日割
朔 日 休業
ニノ日 会読(論語、弘道館記述義)
三ノ日 同(外史)
四ノ日 同(靖献遺言、新論)
五ノ日 同(論語、弘道館記述義)
六ノ日 同(弘道館記述義)
七ノ日 同(外史)
八ノ日 同(靖献遺言)
九ノ日 同(弘道館記述義、新論)
十ノ日 休業
十一日/二十一日 詩文国詩随意
高須芳次郎の会沢正志斎評
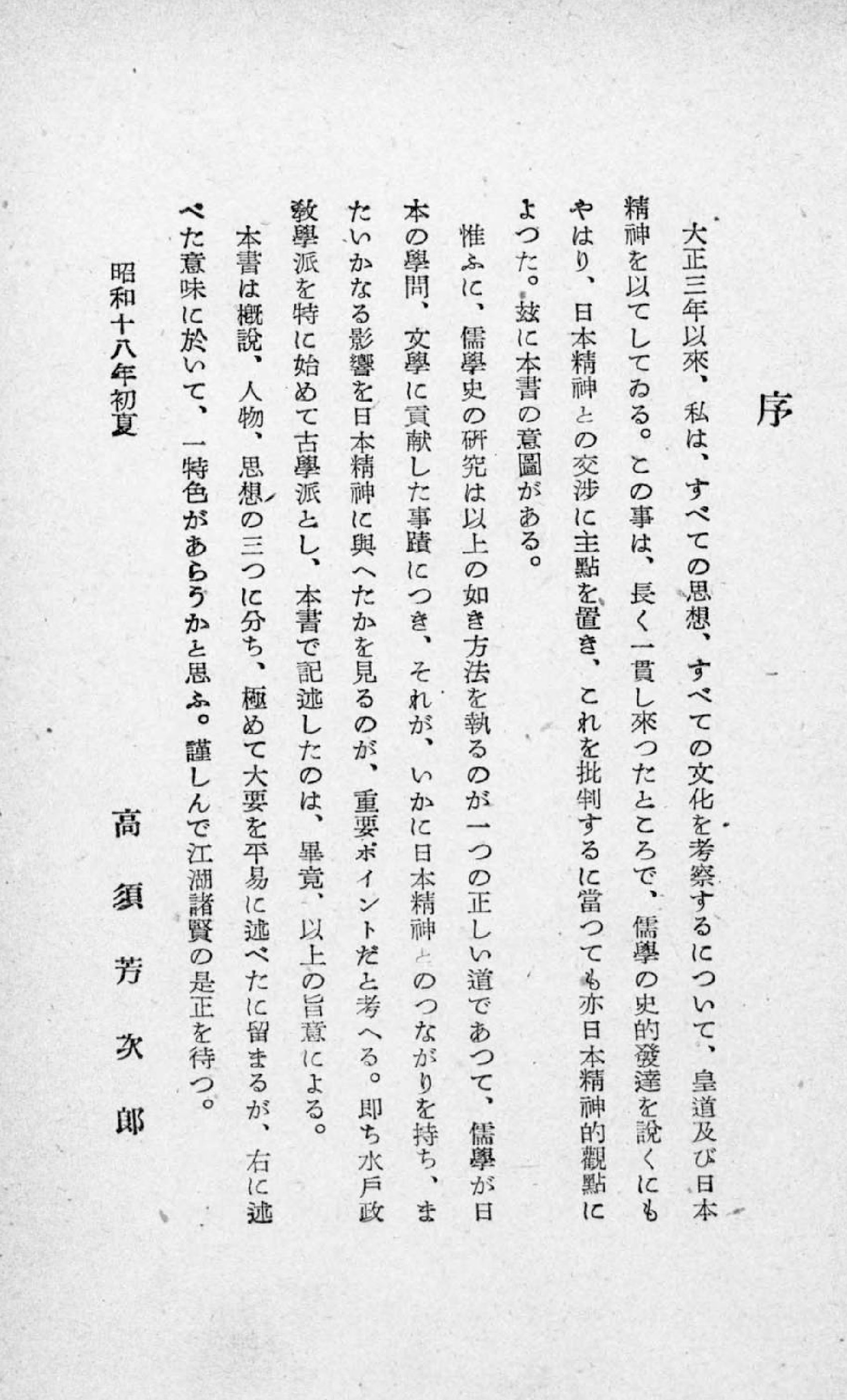 高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。
高須芳次郎は『近世日本儒学史』(越後屋書房、昭和18年)において、会沢正志斎について次のように評している。
〈就中「新論」は……日本國體の尊厳を理論の上から詳しく説いた最初の書であつた。それと共に農本主義を叫んで、士民の経済的行詰りを打開し、忠孝一本主義を唱へて、国民の思想的立場を強力ならしめることにつとめた。その国防論の如きも、軍事科学の知識を本にして、詳しく陸海軍の新設備を論じ、頗る当時に適切だつた。
それ故天下の志士、国士を以て任ずる人々は争うて「新論」を読んだのである。真木和泉、平野次郎、安達清風らはいづれも「新論」から少からぬ感銘を得た。その他、薩長と土肥諸藩の人々のうちには「新論」愛読者が多かつたのである。かうして「新論」一篇は正志斎の名を全日本に伝へ、彼の風采を想望して水戸へくる有為の青年がなかなか多かつた。吉田松陰も亦正志斎を崇拝してその教へを受け「会沢先生は、人中の虎だ」と感嘆した。
(中略)
正志斉はまた文章に長じ、精力に富んで頭脳が明快であつたから、水戸学精神を世に普及するために年々著述を出した。中にも「下学遺言」「及門遺範」の二書は、水戸政教学の本旨をよく伝へ、後人を感奮せしめる力が強い〉
神宮皇学館惟神道場『日本精神』目次
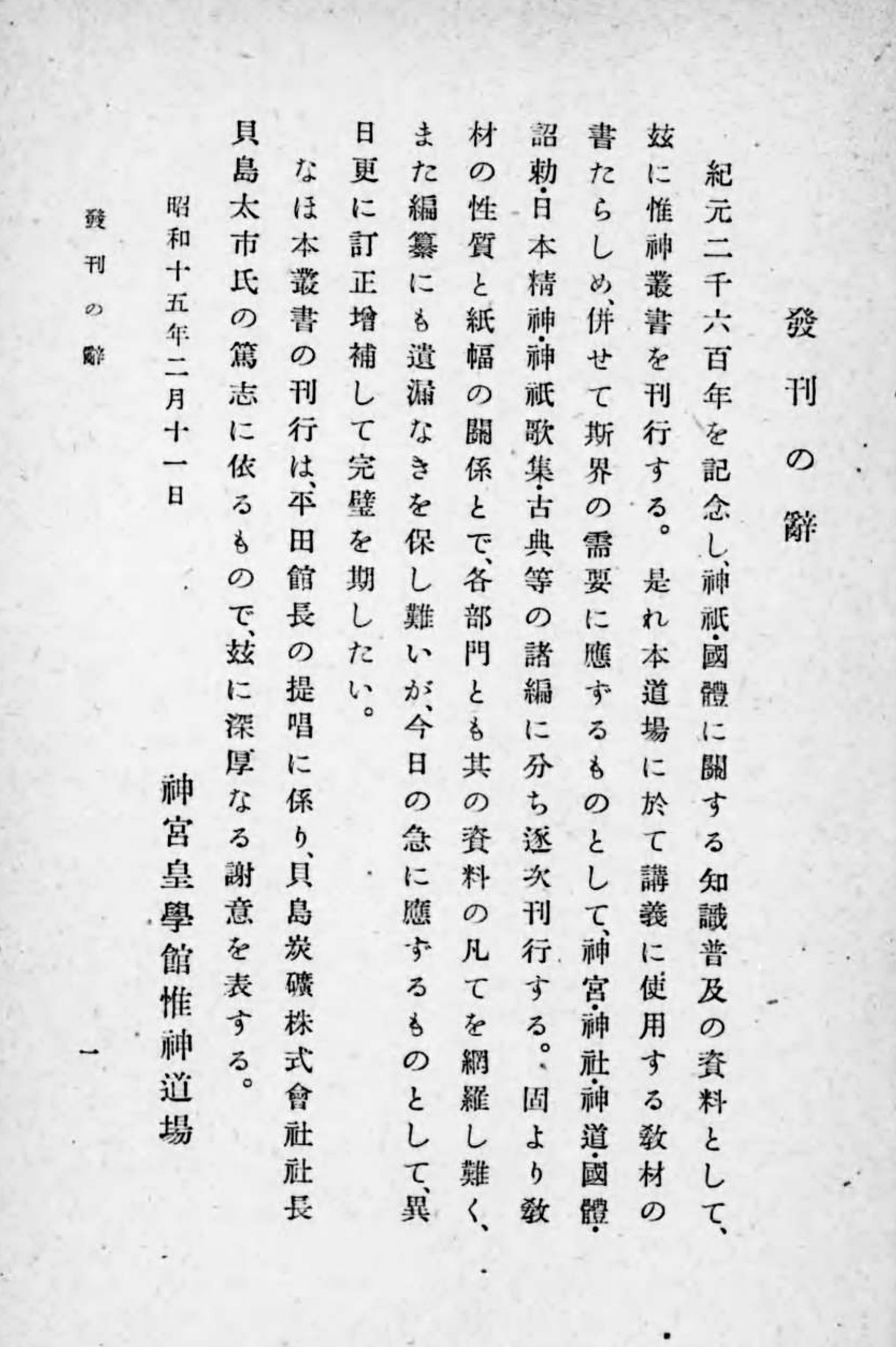 昭和15年に刊行された神宮皇学館惟神道場『日本精神』(惟神叢書 第5編)の目次を紹介する。崎門系あるいは崎門の影響を受けた著書には★。
昭和15年に刊行された神宮皇学館惟神道場『日本精神』(惟神叢書 第5編)の目次を紹介する。崎門系あるいは崎門の影響を受けた著書には★。
一 天神の詔命(古事記)
二 伊邪那岐命の詔命(古事記)
三 三種の神器と天孫降臨の神勅(日本書紀)
四 神武天皇帝都の御経営(日本書紀)
五 調伊企儺の勇武(日本書紀)
六 文武天皇即位の宣命(続日本紀)
七 大伴家持の長歌並に短歌(万葉集)
八 火長今奉部与曽布の歌(万葉集)
九 大伴家持の歌(万葉集)
一〇 蟻通し明神の故事(清少納言枕草子)
一一 藤原光頼の意見(保元物語)
一二 平重盛の諌言(平家物語)
一三 朝敵素懐を遂げず(平家物語)
一四 夙夜忠(宴曲抄)
一五 大日本は神国なり(神皇正統記)
一六 日本と印度・支那との比較(神皇正統記)
一七 楠木正成の奉答(太平記)
一八 楠木正行最後の参内(太平記)
一九 承久変に対する批判(増鏡)
二〇 日本記(舞の本)
二一 白楽天(謡曲)
二二 鷺(謡曲)
二三 弓箭とりの心得(竹馬抄)
二四 君に仕へたてまつる事(竹馬抄)
二五 中朝事実著述の由縁(中朝事実)
★二六 山崎闇斎と門人との問答(先哲叢談前編)
★二七 方孝孺の精忠(靖献遺言)
二八 源親房伝賛(大日本史賛薮)
★二九 正名論(柳子新論)
★三〇 神州は太陽の出づる所(新論)
三一 本居宣長の長歌(鈴屋集)
★三二 楠氏論(日本外史)
★三三 筑後河を下る(山陽詩鈔)
★三四 封冊を裂く(日本楽府)
三五 侠客伝著述の主旨(開巻驚奇侠客伝)
三六 皇国が万国に優れる理由(大道或問)
★三七 國體の尊厳(弘道館述義)
日立市立市立記念図書館が「瀬谷義彦氏寄贈図書展示コーナー」を設置

日立市立市立記念図書館(同市幸町)は、平成28年12月1日に「瀬谷義彦氏寄贈図書展示コーナー」を2階参考図書室に設置した。日立の郷土研究のみならず、水戸の尊皇攘夷運動、水戸学の研究に寄与することになりそうだ。
瀬谷氏は、大正3年に茨城県多賀郡鮎川村(現・日立市)で生まれた。茨城県立日立中学校(現・茨城県立日立第一高等学校)教諭、水戸中学校(現・茨城県立水戸第一高等学校)、茨城師範学校教授、多賀工業専門学校教授を経て、茨城大学教授に就任した。定年退官後は、茨城キリスト教大学短期大学部教授、茨城キリスト教大学教授を務めた。

瀬谷氏は、茨城県の地方史研究の第一人者として、歴史資料の保存・研究・人材育成・交流に尽力した。昭和34年に瀬谷氏が執筆、監修した「日立市史」は、茨城県内初の自治体史となった。平成18年には名誉市民に選ばれている。
一方、水戸学研究としては、『水戸学の史的考察』(東京中文館、昭和15年)などがあり、『日本思想大系〈53〉水戸学』(昭和48年)には、解題と「水戸学の背景」を書いている。
同図書館によると、生前に寄贈の申し入れがあり、約1800冊の資料が寄贈された。
『毎日新聞』(2016年11月28日地方版)によると、職員4~5人が7カ月間かけて、月に2回ほど瀬戸氏の自宅を訪問し、本棚の中から本を選定した。職員は「台所と応接間以外は本棚だらけで、その中から本を選ぶのに苦労した」と振り返っている。
瀬戸氏は、2015年11月20日に逝去された。101歳だった。12月15日には、市葬が同市の市民会館大ホールで営まれ、葬儀委員長の小川春樹市長が「本県の地方史研究の第一人者として歴史資料の保存、研究に尽力され、自治体史の編さんに大きな足跡を残しました。数々の功績に対し敬意と感謝の意を表します」と追悼の言葉を述べた。
「儒教を排することはわが神道を矮小化することである」─本居宣長 vs. 藤田東湖
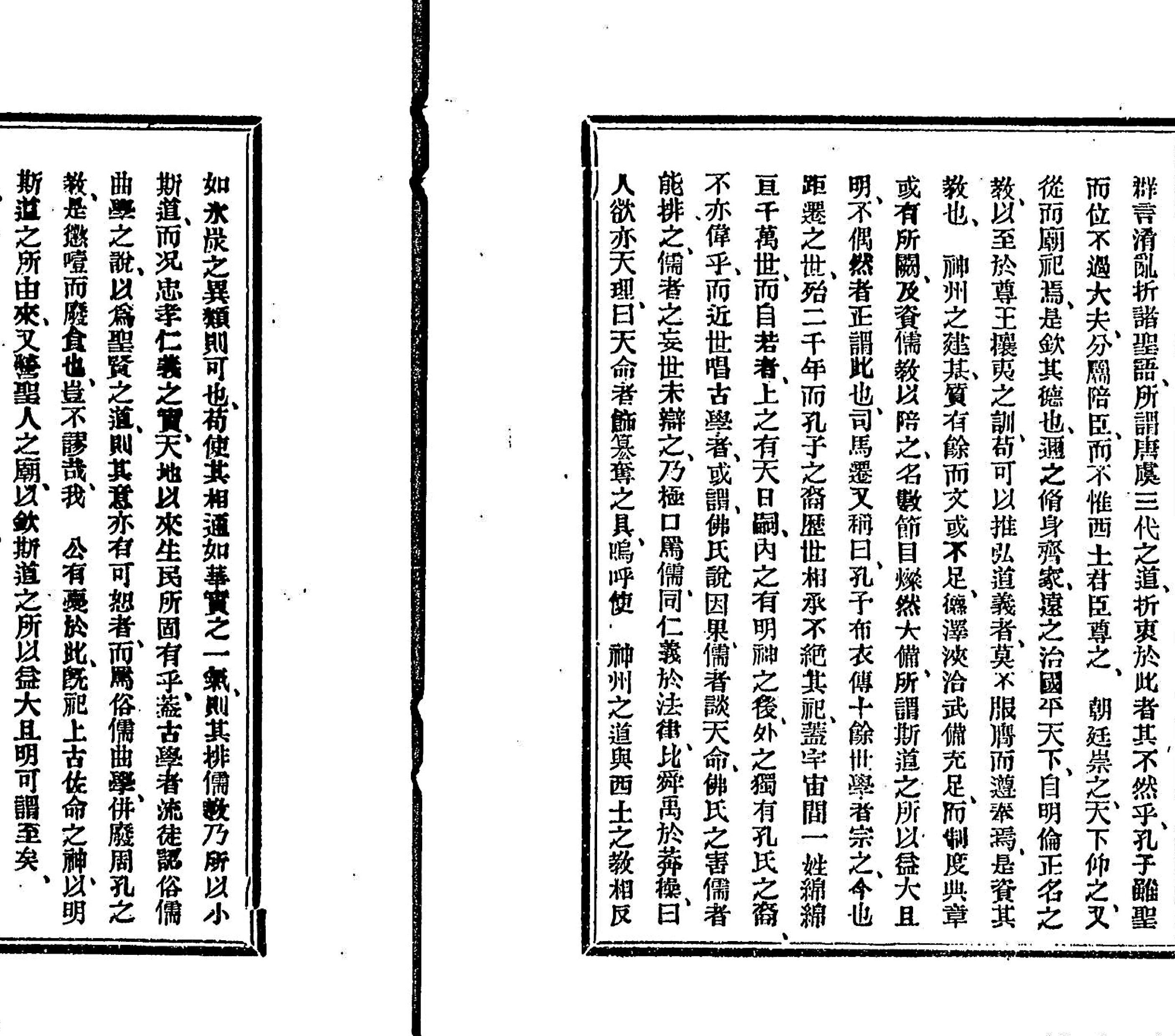 「現在も続く直毘霊論争」(『月刊日本』平成26年1月号)で、本居宣長に対する会沢正志斎の反論を取り上げたが、藤田東湖もまた正面から宣長を批判し、「儒教を排することはすなわちわが神道を矮小化することである」と言い切っている。
「現在も続く直毘霊論争」(『月刊日本』平成26年1月号)で、本居宣長に対する会沢正志斎の反論を取り上げたが、藤田東湖もまた正面から宣長を批判し、「儒教を排することはすなわちわが神道を矮小化することである」と言い切っている。
以下は東湖の『弘道館記述義 巻の下』の一節である。
〈…最近、古代の学問を唱えるものがあって、「仏教はすべて因果で説明し、儒教は天命によってすべてを解釈する。仏教の弊害は儒者がたくみに批判するけれども、儒教の間違いは世間にまだ説明するものがいない」(宣長『直毘霊』)などというものがある。このような人は口を極めて儒教を罵倒し、仁義の徳などというのは後世の法律命令のようなものであり、舜・禹は王莽か曹操と同じような簒奪者であるとなし、「人間の欲望もまた人間の道である」とか、「天命というのは簒奪を合理化する口実である」(同)などといっている。もし、わが国の神道があたかも氷と炭のように儒教とまったく相反するものである、とするならばそういってもいい。しかしもし、わが国の道と儒教が同じ気から生じた花と実のように共通したものであるとするならば、儒教を排することはすなわちわが神道を矮小化することである。そればかりでなく、忠孝仁義という実質は天地はじまって以来、人類の生れつきに備えたところのものである。思うに古代研究を唱える者たちは、俗流の儒者たちの説くところを先王の道と思いこんでいるのだから、なお許すべき点がある。しかし俗流儒者を罵倒するとともに、周公・孔子の真の教えをも抹殺しようとするのは、食物が喉につまって苦しみむせぶのを聞いて、自分も食うことをやめてしまうのと同じである。非常な誤りというほかはない。わが斉昭公は、この点を心配あそばされ、建御雷神を祭って斯の道の由来を明らかにしたまうとともに、あわせて孔子の廟を造営され、斯の道がますます大きく、かつ明らかとなったのは、何によるかというその根本に対して敬意を表したもうたのである。実に完璧な御配慮というべきである〉
國體についての国民的合意が求められている─中村武彦氏『尊皇攘夷』
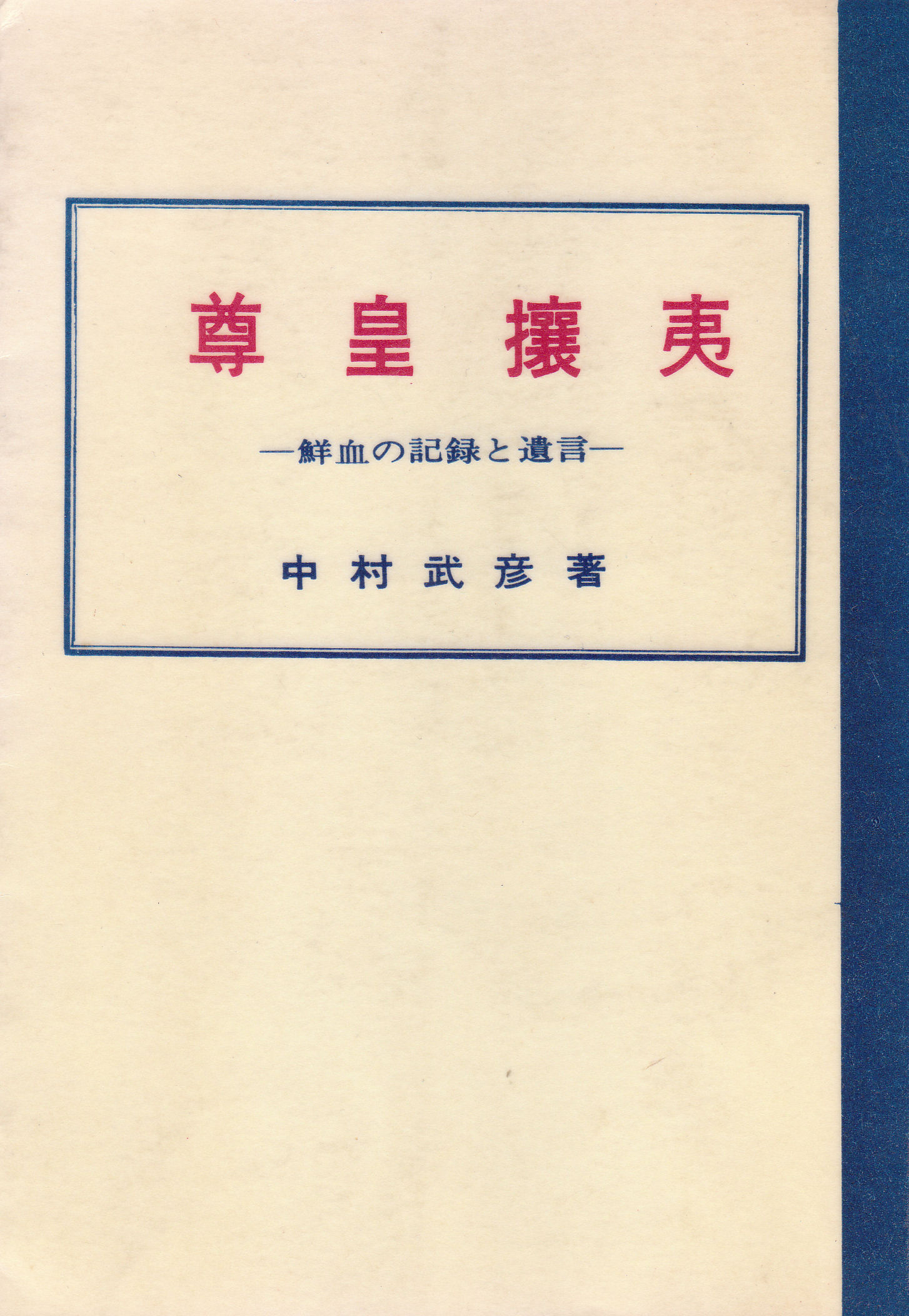 対米従属から脱し、國體を回復するための本物の維新が、いま求められている。その際、重要になってくるのが、國體についての国民的合意にほかならない。
対米従属から脱し、國體を回復するための本物の維新が、いま求められている。その際、重要になってくるのが、國體についての国民的合意にほかならない。
民族派の重鎮中村武彦氏は『尊皇攘夷』(今日の問題社、昭和44年)において、次のように指摘していた。
〈尊攘派と対立した形の開国論者及び佐幕派の人々も、尊皇攘夷の基本精神においては共通していた。意見として対立したのは、開国へ持って行く時期、順序、方法の違いだけであった。当時の日本人はみな常識として日本の歴史を知り、国体観念を持っていた。頼山陽の日本外史や会沢正志斎の新論は、幕末、書物を読むほどの者なら、武士だけでなく、全国の農民商人の間でもひろく読まれ、共鳴されていた。
幕末の尊攘維新運動の背後には、このような、いわば広汎なる国民的合意のあったことを見落してはならない。さればこそ、一たび大政奉還から皇政復古への道が決定するや、待っていましたとばかりに国を挙げて維新開明の大行進が始まり、全世界が瞠目する明治の奇蹟的な飛躍発展が行はれたのである。現代日本との根本的な違いが此処にある。
現代日本には頼山陽なく、水戸学なく、ただ圧倒的なる共産主義の宣伝と、所謂三S政策の影響のみがある。占領下に植民地教育を強制されて以来、今なお日本人、殊に若い世代の歴史と国体に関する無知には、救い難いものがある。肇国の神話も明治維新の歴史も教えられず、楠正成も乃木希典も知らない。世界の何処にこのような自虐的な教育をしている国家があろう〉
中村氏がこう書いてから45年あまりを経た現在も、状況は変わっていない。
山本七平『近代の創造』の中の『靖献遺言』
 山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。
山本七平は『近代の創造』(PHP研究所、昭和62年)において、渋沢栄一の従兄弟で、その師でもあった尾高藍香のことを論じているが、藍香も手にしたと推測される『靖献遺言』を次のように位置づける。
〈『靖献遺言』『保建大記』『中興鑑言』が、さらに『大日本史』の通俗版ともいえる『日本外史』『日本政記』が明治維新を招来した「思想教科書」であるとは確かに言える。このうち前の三冊は朱子学の系統の崎門学であり、『中興鑑言』の著者三宅観瀾と『保建大記』の著者栗山潜鋒は水戸彰考館の一員で、共に闇斎・絅斎系すなわち崎門学系の思想家である。そしてこの浅見絅斎こそ山崎闇斎の弟子で尊皇の志士のバイブル『靖献遺言』の著者である。だが、これらの人々の思想は……朱子学系統であり、朱子の正統論を絶対化し、正統を護持するためには殉死も辞せずという強い正統論者であったことは共通している。一方水戸には光圀が招聘した中国からの亡命学者朱舜水がおり、その弟子が安積澹泊で水戸彰考館の総裁、要約すればこの二系統を統合したのが初期の水戸学である。しかし観瀾の後は余りたいした学者も出ず、このころは日本の思想に強い影響力をもっていたわけではない。
ところが藤田幽谷とその子東湖、さらに会沢正志などが出、斉昭がこの東湖によって水戸藩主となり、東湖を側用人、正志を侍読とすると共に、水戸は「思想的権威」のような様相を呈して来た。……だが会沢正志であれ、藤田東湖であれ、本来の姿は水戸藩の「お抱え学者」であり、藩に従属して禄をもらっている以上、浅見絅斎のような完全に自由な思想家ではあり得ない。彼らは「尊皇攘夷」は声を大にして口にしたが、「藩」そのものの否定はもちろん、幕藩体制否定の「倒幕」さえ明確には口に出来ず、その点、決して「倒幕のアジテーター」とはいえない。……尊皇思想を研究された三上参次博士は「一方に於て是書(『新論』や『常陸帯』)を読み一方に於て『靖献遺言』の所信を実行せば、皇政復古の大業の明治維新の際に於て成功せるも強ち異とするに足らざるべし」と記されている。いわば「発火点」は『靖献遺言』であって、水戸学はそれにそそぐ油のようなもの、そして外圧はこれを煽ぎ立てる風のようなものであって、油と風だけでは何も起らないわけである。
そして発火点とは……「思想の真髄」いわば、天動説を地動説に変えてしまうような「心的転回」を起したときである。そうなれば『新論』も『常陸帯』も激烈な行動へと燃えあがる油にはなりうる。
そして多くの人の場合は発火点が『靖献遺言』であった〉
会沢正志斎墓参(平成26年7月8日)
平成26年7月8日、茨城県水戸市千波町2367の本法寺跡地にある会沢正志斎の墓にお参りに赴き、『新論』執筆の志に思いを馳せた。
墓表「旌正之碑」は青山延光撰。以下のURLに書き下し文が載っている。
http://www.geocities.jp/sybrma/458seishisaibohyou.kundoku.htm
[flagallery gid=6]
会沢正志斎『新論』の二面性
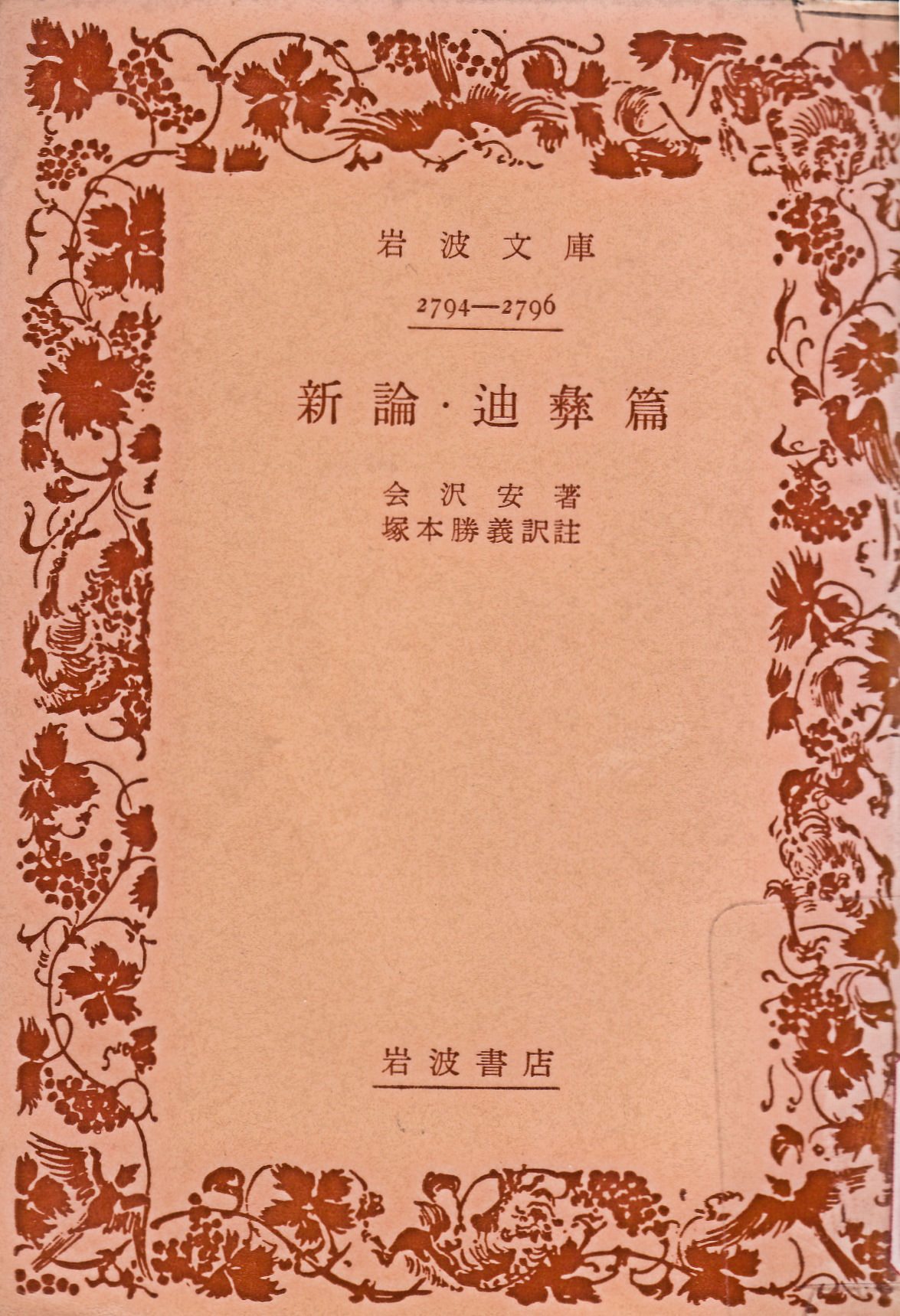
尾藤正英は『新論・迪彝篇』(会沢安著、塚本勝義訳註、岩波文庫)の解説(昭和43年)で、次のように書いている。
〈この思想体系は、本来の性格として支配のための思想であり、「上から」の政治改革の思想であった。しかしそれが過激な現状変革の運動に挺進した青年志士たちの心をとらえ、あたかも革命のイデオロギーとして現実に機能したかのようにみえるところに、大きな問題がある。現在の学界において、本書の思想の性格に関し、対立する二様の見解が成立して、平行線を描いているのも、その微妙な性格のとらえ難さによるのであろう。しかしこれを「封建的支配秩序の合理づけとしての名分論」にすぎないとし、専ら保守的性格のものとみる見解(遠山茂樹氏「尊王攘夷思想とナショナリズム」『尊攘思想と絶対主義』所収)も、逆にこれを「抵抗権」の論理をふくむ下からの革命思想と評価する見解(上山春平氏『明治維新の分析視点』)も、いずれも一面に偏した理解であるように私には思われる。前者では、この政治論にふくまれた革新性が見落される結果となり、後者では、これが支配の思想であったことに注意が向けられていないからである。むしろ本質において支配の思想であったものが、革命運動の主たるイデオロギーとして機能したところに、私たちは明治維新という特異な政治革命の性格を考察するための手がかりを見出すことができる筈であり、本書の内容は、そのような問題を追求するための一つの素材を提供しているのではないかと考えてみたい〉
