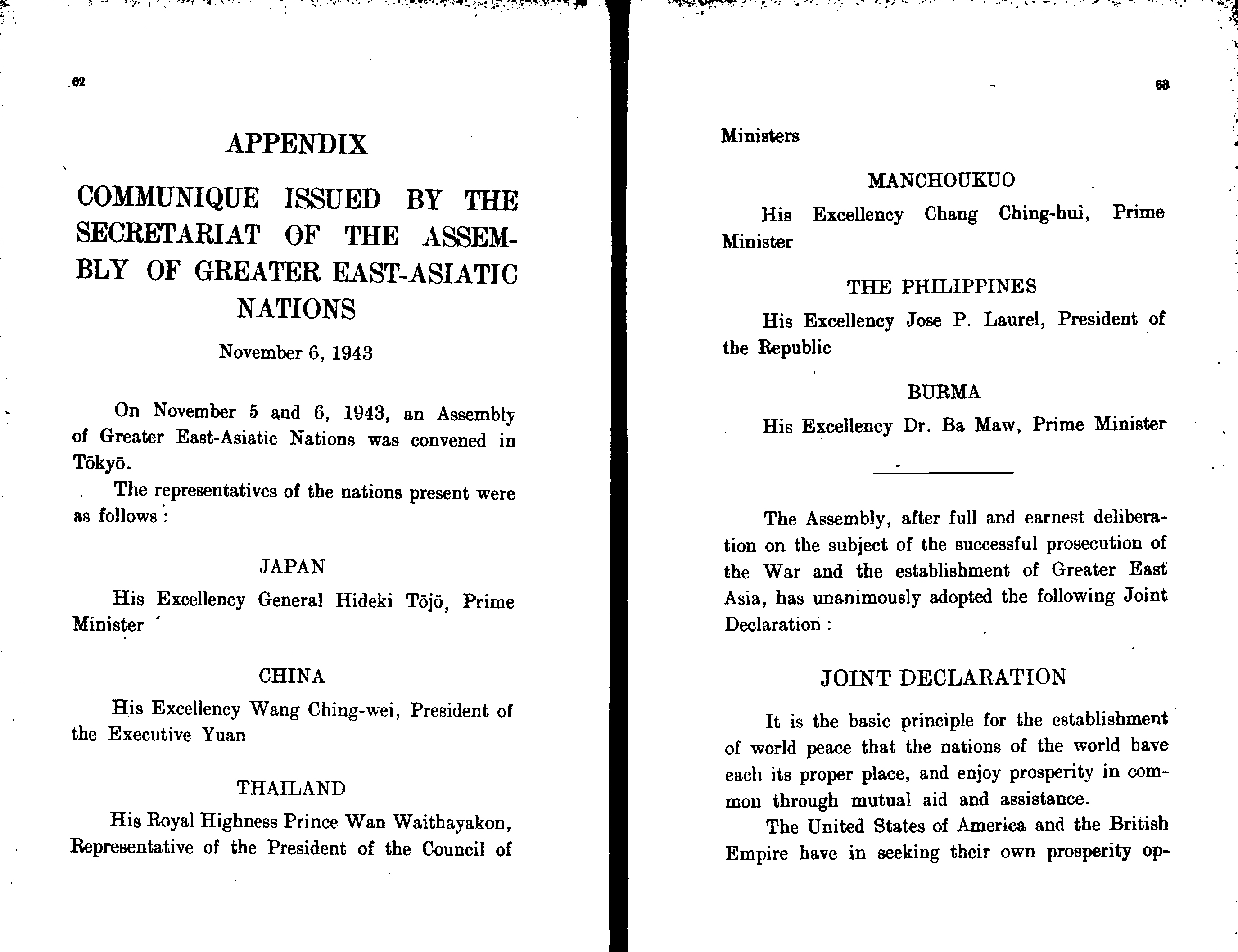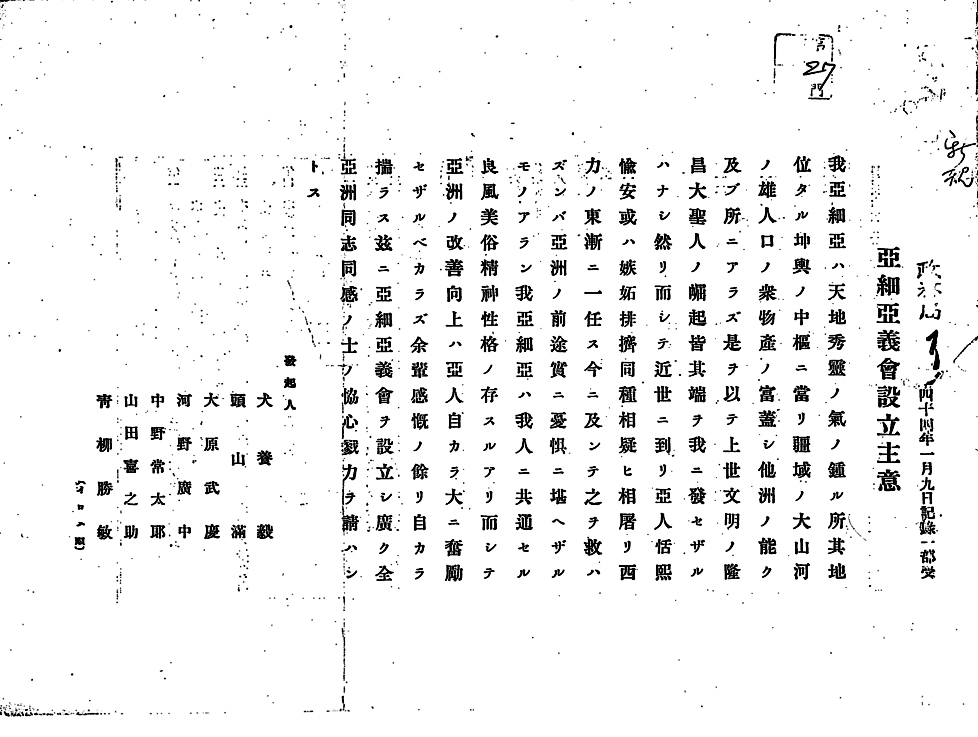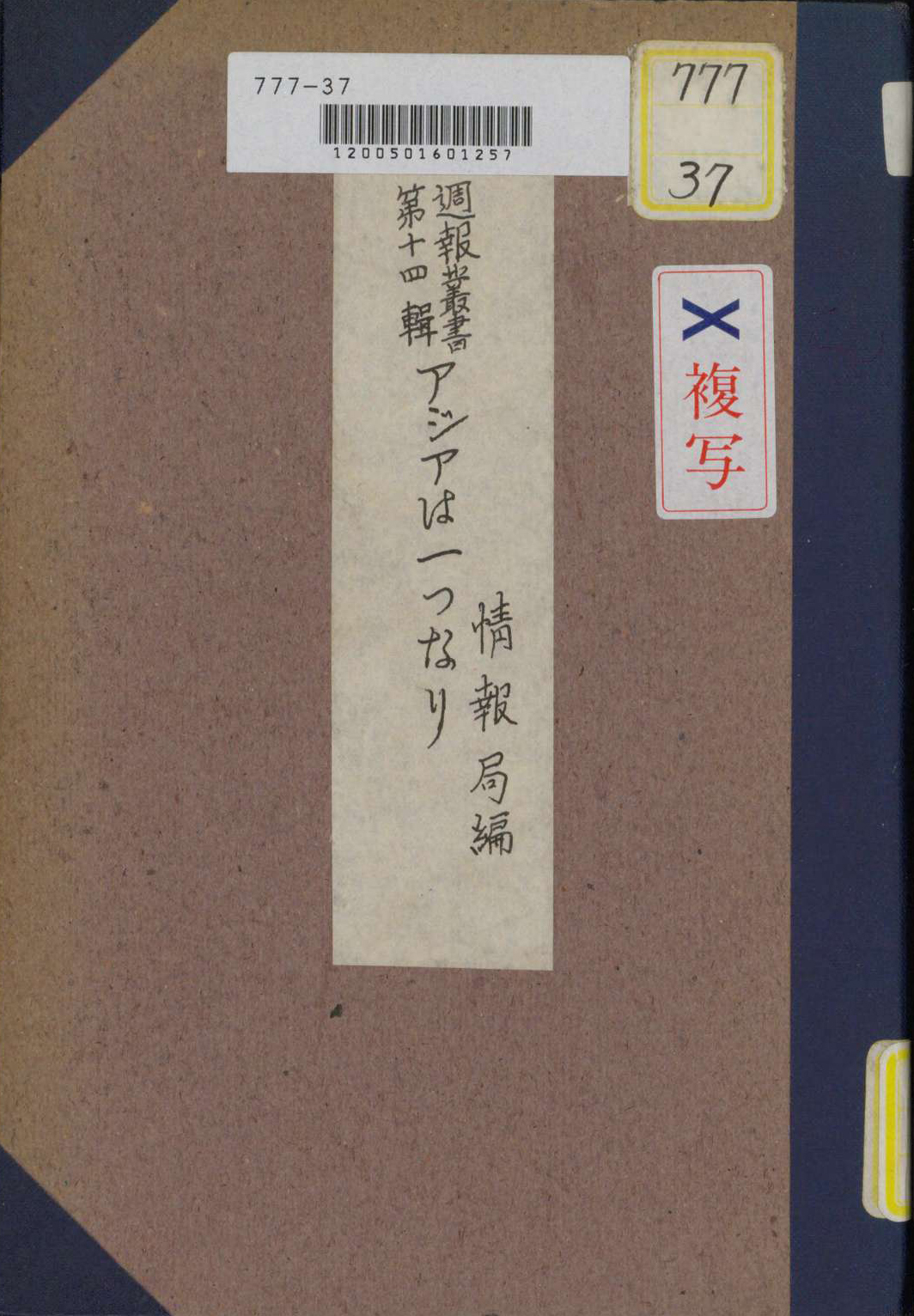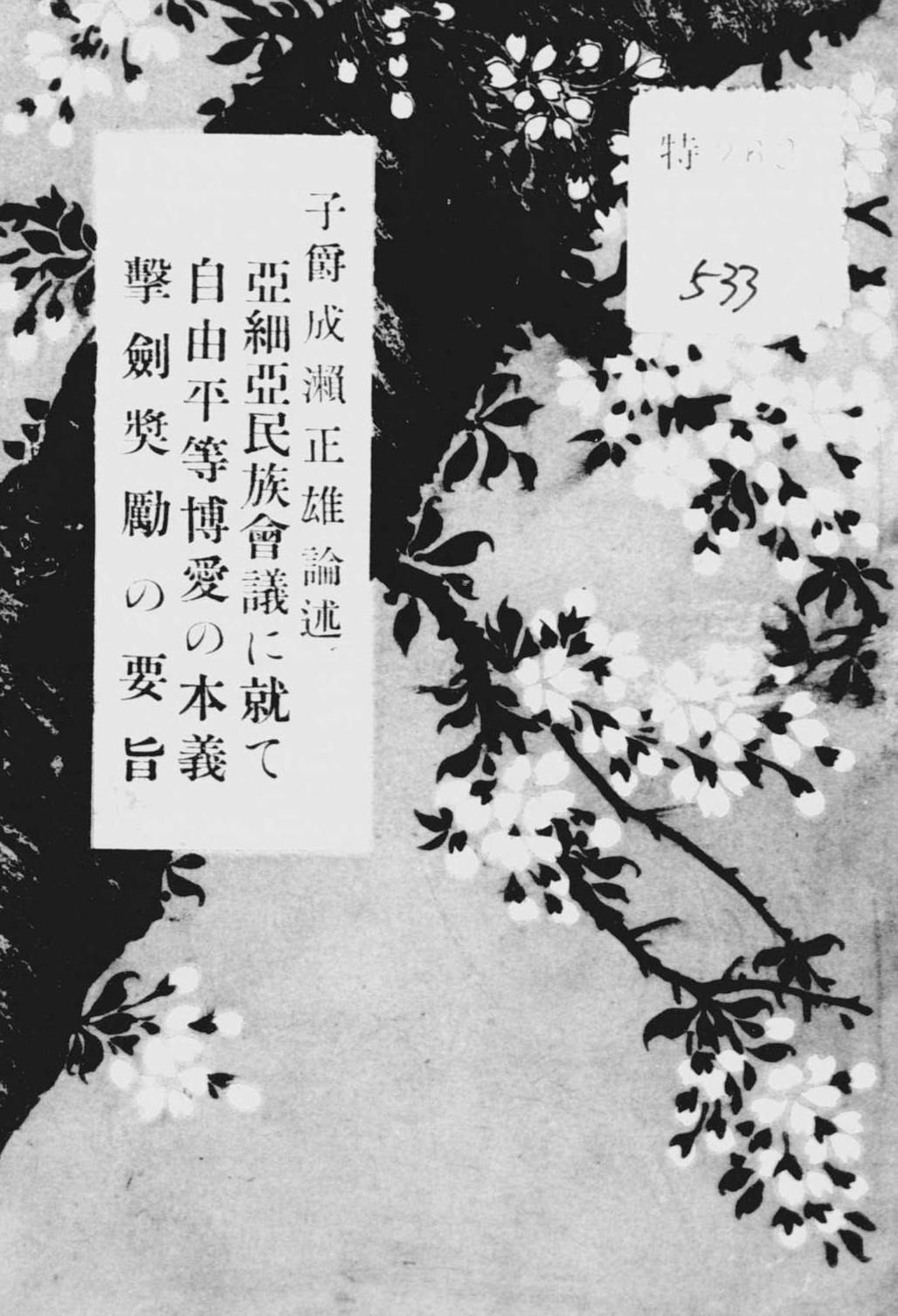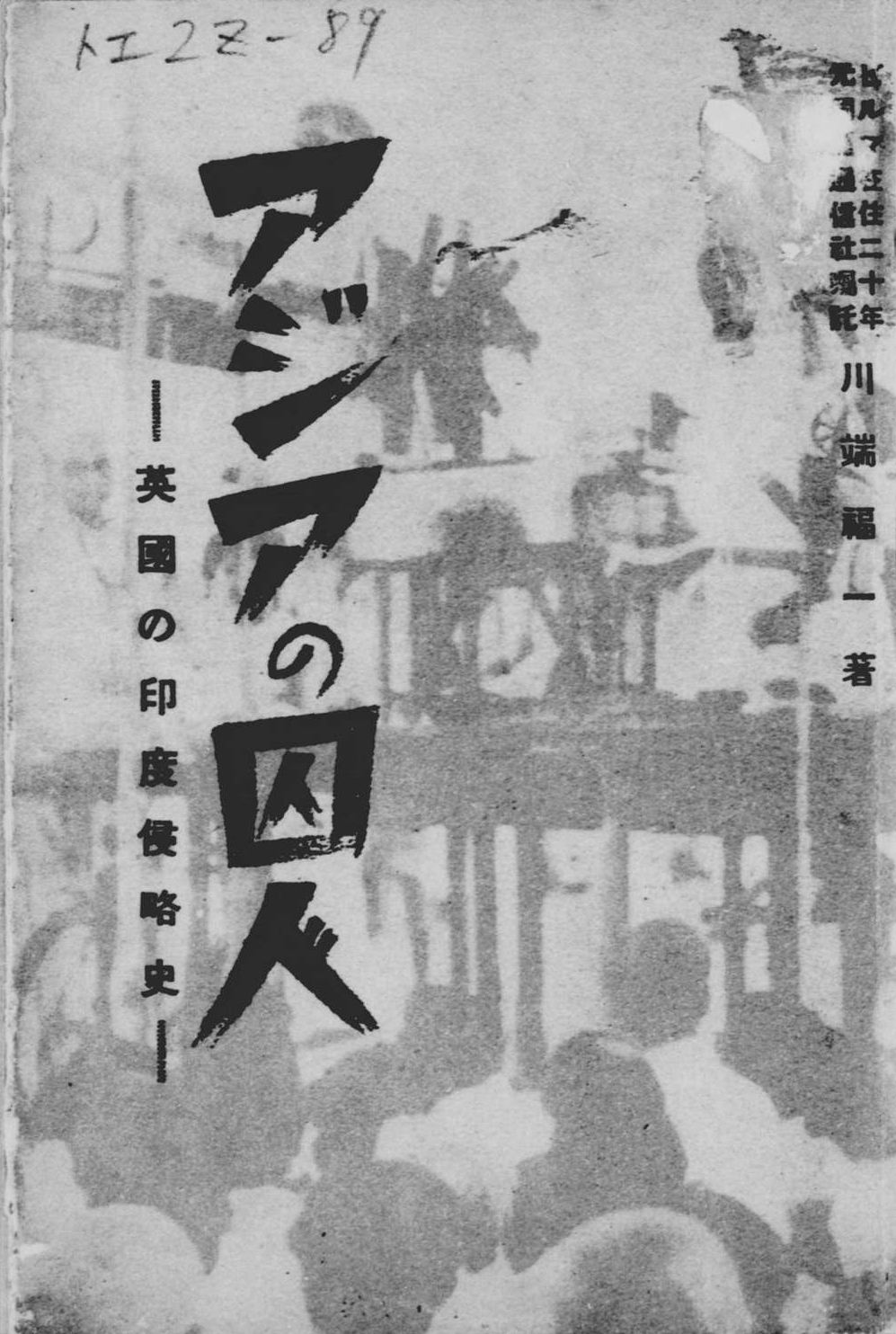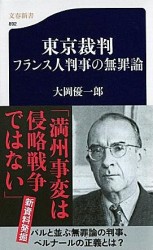筆者は、日本外交の課題は対米追従から脱却して自主外交を確立することだと考えている。その際、中国の覇権主義を制御しつつ、東アジア共同体のリーダーシップをとることが極めて重要な課題となる。
筆者は、日本外交の課題は対米追従から脱却して自主外交を確立することだと考えている。その際、中国の覇権主義を制御しつつ、東アジア共同体のリーダーシップをとることが極めて重要な課題となる。
こうした中で、東アジア共同体研究所理事長を務める鳩山由紀夫元首相は、2013年7月13日にマレーシアで開催された第10回ASEANリーダーシップ・フォーラムで「Towards a Common Future & Shared Prosperity」と題して講演した。
以下に、同研究所HPに掲載された日本語訳の一部を転載させていただく。
〈私は総理時代に、「東アジア共同体の創造」を新たなアジアの経済秩序と協調の枠組み作りに資する構想として、国家目標の柱の一つに掲げました。東アジア共同体構想の思想的源流をたどれば、「友愛」思想に行き着きます。「友愛」とは自分の自由と自分の人格の尊厳を尊重すると同時に、他人の自由と他人の人格の尊厳をも尊重する考え方のことで、「自立と共生」の思想と言っても良いでしょう。そして今こそ国と国との関係においても、友愛精神を基調とするべきです。なぜなら、「対立」ではなく、「協調」こそが社会発展の原動力と考えるからです。欧州においては、悲惨な二度の大戦を経て、それまで憎み合っていた独仏両国は、石炭や鉄鋼の共同管理をはじめとした協力を積み重ね、さらに国民相互間の交流を深めた結果、事実上の不戦共同体が成立したのです。独仏を中心にした協力の動きは紆余曲折を経ながらその後も続き、今日のEUへとつながりました。この欧洲での和解と協力の経験こそが、私の構想の原型になっています。
すなわち、私の東アジア共同体構想は、「開かれた地域協力」の原則に基づきながら、関係国が様々な分野で協力を進めることにより、この地域に機能的な共同体の網を幾重にも張り巡らせようという考え方です。 続きを読む 鳩山由紀夫氏「Towards a Common Future & Shared Prosperity」 →