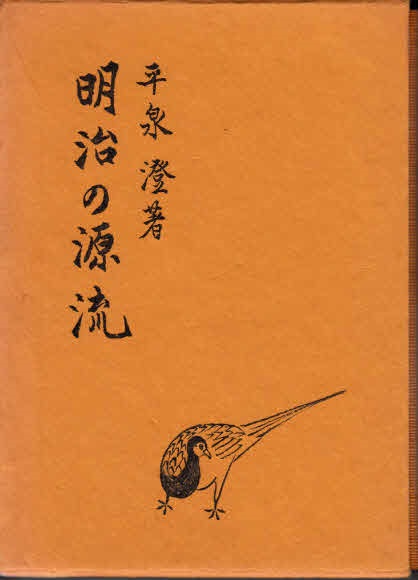 崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。
崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。
〈ここに殆んど不思議と思はれるのは、水戸の大日本史編修と時を同じうして、山崎闇斎が倭鑑の撰述に着手した事である。一つは江戸であり、今一つは京都である。一つは水戸藩の総力をあげての事業であり、今一つは学者個人の努力である。大小軽重の差はあるが、その目ざす所は一つであり、そして国史上最も困難なる南北の紛乱を、大義を以て裁断した点も同趣同様であった。但し問題は、処士一個の事業としては、あまりに大きかった。闇斎は、明暦三年の正月より筆を執り、そして少くとも二十数年間、鋭意努力したに拘らず、完成に至らずして天和二年(西暦一六八二年)九月、六十六歳を以て歿し、倭鑑の草稿もまた散逸してしまった。只その目録のみ、門人植田玄節によって伝へられた。それによれば、後醍醐天皇を本紀に立て、光厳、光明紀を之に附載し、後村上天皇を本紀に立て、光明、崇光、後光厳、後円融、後小松紀を之に附録し、そして明徳二年十月二日、三種神器入洛の事を特筆大書したといふ。して見れば是れは、水戸の大日本史と同じ見識であったとしなければならぬ。
闇斎の此の識見は、そのままその門下に伝はった。たとへば正親町公通は、無窮記を著して、後醍醐、後村上、長慶、後亀山を正統の天子とし、光厳院は北条高時の私に立てたるお方であって、北畠親房は「是れ偽主なり」と断じた事、光明院は足利高氏の私に立てたお方であって、それより明徳三年までは、之を北朝といふ事を記してゐる。吉野には、之を天皇と書いて神武天皇以来の代数を標示し、京都には、之を何々院と記して代数を書いてゐない事、すべて水戸の大日本史と期せずして同一である。
闇斎の門流、迎へられて水戸に仕へ、大日本史の編修に参加する者幾人かあって、その特に有名な者は、三宅観瀾であるが、それよりも識見のすぐれてゐる者は、栗山潜鋒であらう。三宅は中興鑑言を著して、建武の中興を評論し、栗山は保建大記を作って、政権の武門に移るに至った原因を究明した。いづれも明治維新の前後によく読まれた書物である。両人は、吉野を正統の天子とする点は一致してゐたが、その判定の規準を、栗山は神器の所在に置き、三宅はむしろ義理を主とすべしと論じた。それぞれ稍頑固であり、議論の為の議論におちいった感じがするが、いづれにせよ足利を許さない点に於いて、同一の陣列に在った。
闇斎の門流は、その一部水戸に仕へて大日本史に協力する事、かくの如くであったが、主流は京都もしくは其の附近に在り、幕府に仕へず、諸侯に仕へず、困苦して学を講じ、以て王政復古の機会を待った。闇斎の門人浅見絅斎、その門下若林強斎など、是れである。浅見の著作靖献遺言は、初め楠木、新田、菊池等、建武の忠臣の事蹟より集録し評論しようとして、中途に方向をかへ、材料を支那の歴史に求めて、道義の最高最深、人の標的とし、理想とすべきものを集めたもの、之を読めば人々感激して王事に一命を捧げようと冀はない者は無い程であった。それは幕府が頗る此の書を忌み嫌ひ、之を公卿に講じた点を糾明し難詰して、竹内式部を追放した事によっても察せられるであらう。
その門人若林強斎に至って、その書斎に名づけて、望楠軒といったのは、楠公を理想とし、その遺志を継がうとする精神を端的に表したものである。享保十五年秋、門人廣木忠信の死を悼み、望楠軒に於いて其の霊を祭った時の祭文に、
夏も扇がず、冬も炉に近づかず、艱難窮乏、日を合せて食ふもの、時に之あり。(中略)雪の朝、月の夕、相ともに茶をに酒をあたため、経を議し義を論じ、今を悲しみ古を慕ひ、憤歎慷慨、心肺傾けつくし、相責むるに死生を以てす。
といふもの、我国臣子の道、目標とすべきは楠公の外に無しとし、楠公を仰ぎ望むといふ意味に於いて、書斎を望楠と号した志士の風格を偲ぶに足るであらう。
若林強斎歿して後も、望楠軒は存続して幕末に至った。道統を継いで講主となった者は、小野鶴山であり、西依成斎であり、その他数人を経て、やがて梅田雲浜に至った。即ちあの有名な詩、
妻は病床に臥し、児は飢えに泣く
身を挺して直に戒夷に当らんと欲す、
今朝、死別か、生別か、
唯、皇天后土の知るあり、
の作者であり、そして安政大獄の劈頭第一の犠牲者であった。雲浜はまた、単に楠軒とも号したといふ。此の道統を一貫するものが、楠公景慕の精神であった事、此の点でも察せられるであらう。〉
