 江戸時代初期には天皇の地位が脅かされる危機にも直面していたようだ。『明治維新で変わらなかった日本の核心』(PHP新書)において、磯田道史氏は以下のように書いている。
江戸時代初期には天皇の地位が脅かされる危機にも直面していたようだ。『明治維新で変わらなかった日本の核心』(PHP新書)において、磯田道史氏は以下のように書いている。
〈家康が天下人となった幕初の頃、勢いをかって、徳川家のなかで、「なぜ天皇を徳川幕府は必要とするのか」という議論になったことがあった。なかには家康の側近・天海のように、「『メイド・イン・徳川』の官位をつくれば、天皇は必要ない。伊勢神宮の神主にして押し込めてしまえ。そうすれば天皇をおかしなことに利用される危険もなくなる」という意見も出ます。
これに対し、伊勢の藤堂高虎が、いやそれではいけない。やはり「天朝(天皇)の御羽翼(補佐)となってこそ、諸大名も屈服し、万民も将軍を仰ぐ」といって諌めたといいます。この話は江戸後期の藤堂藩の史料に出てくるので、真偽ははっきりしませんが、ありえることです〉
「国体思想」カテゴリーアーカイブ
霊元天皇宣命─「国家静謐、万民和楽」を大神に祈願
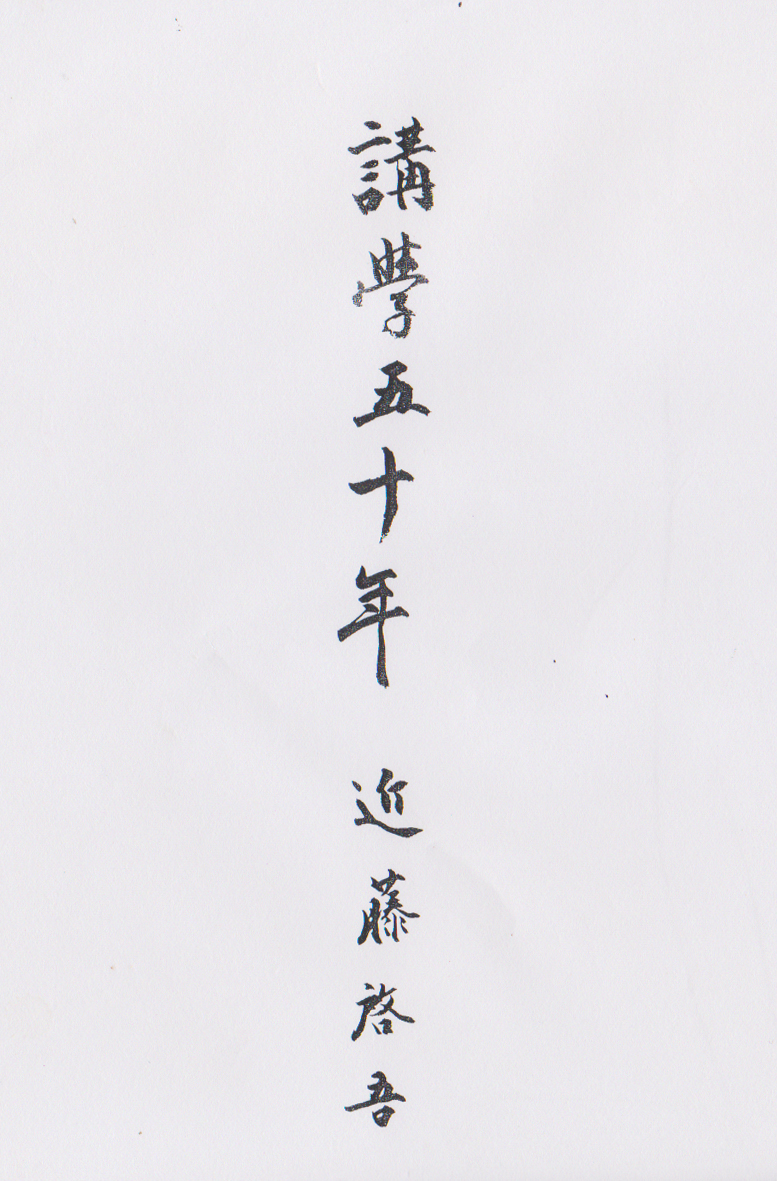 明治維新の本義を考察するとき、幕末以前から存在した尊皇論の展開を重視する必要がある。そして、徳川幕府初期の尊皇論の展開を考えるためには、幕府発足以来の朝廷と幕府の微妙な関係、特に大御心を発揮できない悲劇的な御境遇にあった後水尾天皇や霊元天皇への思いが決定的に重要と思われる。崎門学正統派の近藤啓吾先生は、『講学五十年』(平成二年)において、以下のように書いている。
明治維新の本義を考察するとき、幕末以前から存在した尊皇論の展開を重視する必要がある。そして、徳川幕府初期の尊皇論の展開を考えるためには、幕府発足以来の朝廷と幕府の微妙な関係、特に大御心を発揮できない悲劇的な御境遇にあった後水尾天皇や霊元天皇への思いが決定的に重要と思われる。崎門学正統派の近藤啓吾先生は、『講学五十年』(平成二年)において、以下のように書いている。
〈葺原や茂らば茂れおのがままとても道ある世とは思はず
世の中はあしまの蟹のあしまどひ横にゆくこそ道のみちなれ
右は後水尾上皇が徳川幕府の専横を憤り給ひて詠ぜられた御製である(拙稿『垂加神道樹立の苦悩』。『神道史研究』三五の三、参看)。その父天皇の御憤りを受けられ、朝威の振興を志された豪邁英鋭の天子、後光明天皇は御年二十二歳にて急に崩御になり、ついで立たれた御弟後西天皇は、幕府の強圧によつて御譲位の外なくなり、朝威振興の機なきままに、同じく後水尾天皇の御子である霊元天皇が御即位になるのである。
霊元天皇は、即位せられた寛文三年には御年わずかに十歳にましましたから、御自身のことに叡慮を運らし給ふべくもなかつたが、やがて御成長されるにつれ、天皇としての強い御自覚を持たれるやうになられたことは、天和二年正月二十九日、(御年二十九歳)、伊勢神宮に献ぜられた宣命(その御宸筆の案、『宸翰英華』所収)に
「朕、軽才薄徳の性を以て天日嗣を受伝へたる事は、誠に冥慮の広き御助けなるに、動もすれば輒ち安居を思ひて帝位を忝しめ、治天剰へ二十年に及べるは、偏へに是れ皇太神の深き御護り厚き御恤みに依りてなり。然るに世已に澆季に及びて、帝道爰に漸く衰へぬれば、本より神事の久しく絶えたるを継ぎぬる功も無く、且又朝政の已に廃れたるを興せる務も無きを、毎に恐み毎に愁ふる事になむ。」
「神威ますます耀き、朝廷再び興り、宝祚の隆なること天壌と窮り無く、常磐堅磐に夜の守り日の守りに護幸給ひて、国家静謐、万民和楽、五体安穏、諸願円満に護り恤み給へと、恐み恐みも申して申さく。」
とあることによつて拝することができる。乃ち天皇は幕府の強い干渉抑圧のもとに「神事の久しく絶えたるを継ぎぬる功も無く、且又朝政の已に廃れたるを興せる務も無」しと深く餓悔せられながら、なほ不屈の御意志をもつて、「国家静謐、万民和楽」を、大神に祈願してをられるのである。右は霊元天皇の宣命であるが、実はこれ天皇御一人の祈願に止まるものでなく、御歴代天皇の御志であつたのである。その証拠には、皇室の衰微最も甚しかつたのは戦国時代末、後奈良天皇の御代であつて、紫宸殿の築地の破れから内侍所の灯火を望見せられたと伝へられるが、そのうちにあられて、天文十四年八月二十八日、伊勢大神宮に、天子の位に昇りながら
「大嘗悠紀・主紀(主基)の神殿に、自ら神供を備ふること、其の節を遂げず。敢て怠れるにあらず。国の力の衰微を思ふ故なり。」
とその御苦衷を訴へられるとともに
「急に威力を加へて、上下和睦し、民戸豊饒に、いよいよ宝祚長久に、所願速かに成就することを得しめて、神冥納受を垂れ給へと、恐み畏みも申す。」(後奈良天皇宸翰宣命案)
と祈願せられてゐることが挙げられる。まことに、朝政古に復し暴逆行はれず、万民その所を得て楽しむ世を作ることが、皇室の御目的であり御理想であつたのである。
そしてその御目的、御理想を、霊元天皇の御製に、私共は明確に拝察申上げることができる。〉
霊元天皇と垂加神道
 貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。
貞享四(一六八七)年四月、霊元天皇は、御子である東山天皇に譲位され、同年十一月に大嘗祭を挙行しようとした。大嘗祭は、後土御門天皇の文正元(一四六六)年以来二百二十余年の間中絶していた。
崎門学正統派の近藤啓吾先生は『講学五十年』(平成二年)において、以下のように書かれている。
〈天皇のこの大嘗祭の復興は、幕府の冷淡と無理解とのために幕府より全く援助を受けられることなく、されば万事御不自由な費用で、規模を極めて縮小、例へば三日を要する日程を一日に切りつめて実行されたのであるが、その縮小に対してさへ、それでは非礼であり、神は非礼を受けられぬと反対する方もあり(御兄堯恕法親王)、また廷臣の多くも幕意を憚って消極的態度を示したが、そのやうなうちにあつて天皇は毅然として御自らの責任として親しくこれに当られたのである。但、摂政一条兼輝(冬経)一人がよく輔佐申上げてゐることが注目せられるが、兼輝もまた貞享二年、正親町公通より、垂加神道の伝授を受けてゐるのである。
このやうに見て来ると、延宝の末より天和を経て貞享の初めにかけ、垂加神道が有志の廷臣の間に浸透しつつあつたことがうかがはれるが、しかしそのやうな気運が生れたことは、上にある天皇がこのことを容認せられ、乃至は推奨せられたのでなくては、実現困難であつたらう。そしてそれを知る上の最大の事実として、後西天皇の御遺子にして桂宮家(八条宮家)を紹がれた弾正尹尚仁親王の師として、闇斎の高弟桑名松雲、および松雲の門人栗山潜鋒がお仕へしたことを指摘せられる。天皇は御甥尚仁親王に深く慈愛を注がれ、親しく親王の御歌を添削批評してをられることは、親王が筆録せられた『仙洞御添削聞書』(『列聖全集』第五巻)を拝することによつて明らかである〉
【書評】 折本龍則『崎門学と「保建大記」―皇政復古の源流思想』(三浦夏南氏評)
 崎門学研究会代表の折本龍則氏の『崎門学と「保建大記」―皇政復古の源流思想』の書評が、大東塾・不二歌道会の機関紙『不二』(令和元年8月号)に掲載された。ひの心を継ぐ会会長・三浦夏南氏による堂々たる書評だ。
崎門学研究会代表の折本龍則氏の『崎門学と「保建大記」―皇政復古の源流思想』の書評が、大東塾・不二歌道会の機関紙『不二』(令和元年8月号)に掲載された。ひの心を継ぐ会会長・三浦夏南氏による堂々たる書評だ。
〈新しき御代の訪れとともに、明治維新という大業の精神的支柱となった崎門学の入門書が発刊されることは、維新より時の流れること百五十年、表層の雑論より飛躍して、我が国の淵源に着目し、根本的な研究と実践が求められる我々令和の皇民にとって、誠に得難き手引きとなるものと思う。崎門学が土台とするところの朱子学は、哲学的、宇宙論的内容を多分に含み、一般に難解とされ、崎門学の必読書とされる『靖献遺言』、『保建大記』等も漢文で記されていることから、現代の日本人にとって、重要とは知りつつも親しみ難いものとされて来た。本書は著者一流の解説により崎門学の持つ「難解」の固定概念に風穴を開け、崎門先哲の求道の炎を現代に再燃させる発火点となる一冊である。
(中略)
底の浅い保守思想、国体解釈が横行する現代にあって、己の魂の深奥に沈潜して練成された真の国体学とも言うべき崎門学が持つ影響力は計り知れない。崎門の先生方が強調された「己の為の学」に背かぬよう、自らが学び続けることを誓うとともに、この入門書を通して多くの日本人が崎門の純烈なる精神に直接されることを切望する。最後に浦安市議会議員として崎門の学を政界に体現されている著者の折本氏に敬意と感謝を表して擱筆させて頂きたいと思う〉
裕仁親王殿下に伝授された『中朝事実』
 乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。
乃木希典大将は自決する二日前の明治四十五(一九一二)年九月十一日、東宮御所へ赴き、皇太子裕仁親王殿下(後の昭和天皇)にお目にかかりたいと語った。殿下は御年満十一歳、学習院初等科五年生だった。そのときの模様を大正天皇の御学友、甘露寺受長氏の著書『背広の天皇』に基づいて紹介する。
乃木は、まず皇太子殿下が陸海軍少尉に任官されたことにお祝いのお言葉をかけ、「いまさら申しあげるまでもないことでありますが、皇太子となられました以上は、一層のご勉強をお願いいたします」と申し上げた。続けて乃木は、「殿下は、もはや、陸海軍の将校であらせられます。将来の大元帥であらせられます。それで、その方のご学問も、これからお励みにならねばなりません。そうしたわけで、これから殿下はなかなかお忙しくなられます。──希典が最後にお願い申し上げたいことは、どうぞ幾重にも、お身体を大切にあそばすように──ということでございます」
ここまで言うと、声がくぐもって、しばらくはジッとうつむいたきりだった。頬のあたりが、かすかに震えていた。
顔をあげた乃木は、「今日は、私がふだん愛読しております書物を殿下に差し上げたいと思って、ここに持って参りました。『中朝事実』という本でございまして、大切な所には私が朱点をつけておきました。ただいまのところでは、お解りにくい所も多いと思いますが、だんだんお解りになるようになります。お側の者にでも読ませておききになりますように──。この本は私がたくさん読みました本の中で一番良い本だと思いまして差し上げるのでございますが、殿下がご成人なさいますと、この本の面白味がよくお解りになると思います」
乃木の様子がなんとなく、いつもと違った感じなので、皇太子殿下は、虫が知らせたのだろうか、「院長閣下は、どこかへ行かれるのですか」とお尋ねになった。
すると、乃木は一段と声を落して、「はい──私は、ただいま、ご大葬について、英国コンノート殿下のご接伴役をおおせつかっております。コンノート殿下が英国へお帰りの途中、ずっとお供申し上げなければなりません。遠い所へ参りますので、学習院の卒業式には多分出られないと思います。それで、本日お伺いしたのでございます」と、お答えした。
それから六十六年を経た昭和五十三年十月十二日、松栄会(宮内庁OB幹部会)の拝謁があり、宮内庁総務課長を務めた大野健雄氏は陛下に近況などを申し上げる機会に恵まれた。大野氏が「先般、山鹿素行の例祭が宗参寺において執り行われました。その際、明治四十年乃木大将自筆の祭文がございまして、私ことのほか感激致しました。中朝事実をかつて献上のこともある由、聞き及びましたが……」と申し上げると、陛下は即座に、「あれは乃木の自決する直前だったのだね。自分はまだ初等科だったので中朝事実など難しいものは当時は分からなかったが、二部あった。赤丸がついており、大切にしていた」と大変懐しく、なお続けてお話なさりたいご様子だったが、後に順番を待つ人もいたので、大野氏は拝礼して辞去したという。
【書評】 小野耕資『資本主義の超克―思想史から見る日本の理想』
「保守派」がグローバル企業の擁護者でいいのか
評者は、共同体を破壊し、格差拡大をもたらす新自由主義に対して「保守派」が沈黙していることに、強い違和感を覚えてきた。なぜ、「保守派」は種子法廃止、水道法改正、漁業法改正など、グローバル資本や大企業の要請によって強行される制度破壊に抵抗しないのか、と。
「保守」の立場に立つ著者の問題意識も、そこにあるようだ。「冷戦が終結して久しい今、明治時代の論客に立ち返って、国民精神の観点から弱者救済や格差の是正を訴える議論がもっと出てきてもよいし、それを当然とみなすように変わっていかなければならない」(210頁)
著者が指摘するように、戦後の「保守派」が冷戦的価値観から資本主義と妥協したことには理由があるが、それでも彼らの中にすら、資本主義を克服する萌芽は見られた。ところが、いまや「保守派」の多くがグローバル企業、大企業の擁護者に転落してしまったかに見える。
そもそもわが国において、先人たちが目指してきた理想的な社会のあり方、さらに言えば國體は資本主義と相容れるものなのだろうか。著者は、國體こそが守るべき価値だと言う。
〈経済体制は経済体制でしかなく、國體はそれを超えて存在するものであるという。言い換えると、経済体制は守るべき価値ではなく、國體こそが守るべき価値の源泉ということにもなろう。経済体制は国家の実情、国家そのものが目指すべき方向、そして国家が伝統的に培ってきた価値観に従って決められるべきなのだ〉(8頁)。
〈資本主義の問題点は、それが日本社会に導入された明治期から既に一部の先覚には自覚されていた。戦前、戦後の心ある思想家の論考は、資本主義と共産主義の双方の欠点を自覚し、それに依らない國體への確信に満ちている。したがってわれわれは彼らの真摯な論考に耳を傾け、学び続ける中で日本社会のあるべき姿を描かなければならないだろう〉(7頁)
著者は、数多くの戦前の思想家の言説を紹介し、右翼、国粋主義者と呼ばれてきた人物に一人として資本主義者はいないと説く(167、168頁)。そこで挙げられるのは、西郷隆盛、頭山満、内田良平、陸羯南、三宅雪嶺、権藤成卿、北一輝、大川周明、葦津珍彦、野村秋介、三島由紀夫といった人物だ。
國體を語る「保守派」が、グローバル企業の擁護者でいいのか。本書は「保守派」の奮起を強く促している。
水戸学ゆかりの地を訪問(令和元年7月7日)
古今集・源氏物語・職原抄の役割─平泉澄『物語日本史 中』より
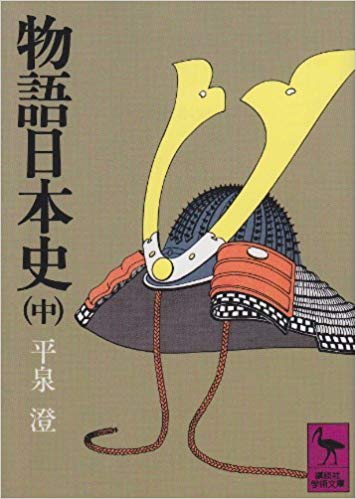 平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。
平泉澄先生は『物語日本史 中』「室町時代」において、以下のように書いている。
〈将軍として責任のあるのは、義政でしたが、義政の一生は、ただ遊楽のために費されていました。あれほどの大乱が起っても、少しも反省するところなく、東山に風流な別荘を建て、それができ上がったので、文明十五年夏、そこに移りました。今残っている銀閣が、それです。そしてその費用のためには、文明十四年、山城一国に課税して、きびしく取り立てるとともに、翌年には、明国に対して卑屈にも窮乏を訴え、寄贈を依頼するなどの恥ずべき態度をとりました。
将軍が、かようなふうでありましたから、その権力が、管領に移るのは当然ですが、しかし管領の権力もまた、その下に移りました。たとえば、管領の細川は、執事の三好によって振り回されましたが、その三好の力はまたその家老である松永に移り、松永久秀は、永禄八年に将軍義輝を殺すに至りました。かように中央が無力でありましたから、地方が群雄割拠の状態となったのは、やむを得ないところです。そこで関東には北条氏、駿河には今川氏、越後には上杉氏、越前には朝倉氏、山陰道には尼子氏、山陽道に初め大内氏、後に毛利氏、四国に長曽我部氏、九州に大友氏、島津氏、東北に伊達氏などが勢力を振いました。しかしそれらの群雄は、いずれも足利の下風にあったもので、日本国の本質を考え、その中興に貢献しようとの意志は、まだなかったのでありました。
しかるにこの紛乱の百数十年の間に、何の権力もないままに、大きな働きをしたものがあります。それは書物です。たとえば古今集です。源氏物語です。職原抄です。これらの書物は、あの戦乱の世にも、驚くべき熱情をもって、人々の愛読するところとなりました。そして、応仁の大乱によって、京都の邸宅を焼かれ、その収入もなくなった公卿たちが、それぞれ縁故をたよって地方に移住するに及んで、これらの人々によって、上にあげたような古典の知識も、いっそうひろく地方にひろがるに至ったのは、いわば予期せざる効果といってよいでしょう。
当時学者として尊敬せられ、古典の理解及び伝授の上に、大きな貢献をした人には、関白一条兼良(応仁元年には六十六歳)、内大臣三条西実隆(応仁元年には十三歳)などがあり、いずれも長生きで、(兼良八十歳、実隆八十三歳)著述や書写に努めました。これらの古典は、それに親しんでいるうちに、自然に日本の国柄、その本質、その制度、その精神が分るものですから、戦国衰乱の世においても、これらの古典が喜ばれた以上、やがて日本国中興の日の到来するを期待してよいでしょう〉
頼山陽『日本外史』論賛①─足利氏
頼山陽は、『日本外史』「足利氏論賛」において、以下のように書いている。
〈外史氏曰く。源氏は王土を攘(ぬす)み、以て王臣を攘(ひ)く者なり。足利氏は王土を奪ひ、以て王臣を役する者なり。故に足利氏の罪を論ずれば源氏に浮(す)ぐ。而して源氏は再伝して亡び、足利氏は乃ちこれを十三世に延(ひ)くを得たる者は、蓋し源氏は宗族を剪除(せんじょ)して、孤立自ら斃る。而して足利氏は子弟・旧臣を封建し、以て相ひ維持するに足る。故に遽(にわか)に滅びざるのみ。然れども其の封建するや、本末軽重の勢を制するを知らず。ここを以て、纔(わずか)に能く一時を偽定すれども、而も反者蝟毛(いもう)の如くにして起る。その中葉以後に至つては、天下禽奔獣遁(きんぽんじゆうとん)し、而して復た制すべがらざるなり。……漫然割与し、動(やや)もすれば一姓をして三四州(赤松・細川・畠山氏らの類)に踞(きよ)するを得しむ。甚しきは、天下六分の一(斯波氏の場合)に居りて、これを能く制するなし。其の鎌倉に封ずるに至つては、室町と二君の如し。遂にその子孫、猜疑相ひ図る(室町の義教と鎌倉の持氏との争ひの類)を致す。而してこれを終ふるに、鎌倉は上杉氏の覆す所となり、室町は細川氏の弱むる所となる。皆所謂る尾大にして掉(ふる)はず、末大にして必ず折るゝ者なり。然れども其のこれをなすは、故あり。彼、其の王家中興の業を奪はんことを計る。故に濫賞侈封、務めてその欲を充て、復たその後を計らず、以て苟も天下を取れり。天下已に集(な)れり。而して裁抑すべからず。一たび問ふ所あれば、眦(まなじり)を裂いて起ちしは、怪しむに足る者なし。彼の欲を充てて、以て我の私を済(な)す。彼、我が私を知つて、その功を以て我に邀(もと)む。我れ何を以てこれを制せんや。蓋し足利氏は、土地・人民を以て天下の豪俊に餌(じ)し、而してこれを掣する能はず。その餌を并せてこれを失ふ。亦た哀むべし。……外史氏曰く、噫、是れ足利氏を助けて虐をなす者なり。夫れ天下、名あり、実あり。昔、我が王家、海内を統馭(とうぎよ)し、租に食(は)み税に衣(き)、而して爵秩(しやくちつ)を以て功労に酬ゆ。この時に当つて、名実の権、並に朝廷に在り。その後に及んで、その名を盗んで敗るゝ者あり。平将門是なり。その実を窃んで成る者あり。源頼朝是なり。その名実を并有せんと欲して、これを両失する者あり。則ち足利氏是なり。……義満に至つては、驕侈(きようし)跋扈、乗輿(天子)に僣擬し、信を外国に通じ、日本国王と称し、旧臣・門族を分ち、以て摂籙(せつろく)・清華に倣ふ。豈に名実を并有せんと欲するに非ずや。朝廷、その贈号を擬するに、太上天皇を以てす。無稽の甚しき、笑を千古に貽(のこ)すと雖も、而も義満の素心の蓄ふる所、亦た以て見るべし。其の早世して志を終へざる、我が邦の幸と謂はざるべけんや。……而して其の旧臣(三管領・四職・七頭を定め、朝廷における五摂家・七清華に倣ったこと)・門族を分つや、所謂る三管管領は皆大封に拠る者なり。既にこれに与ふるに、土地・人民の富を以てし、またこれに仮すに、官号の崇きを以てし、これに授くるに、権柄の要を以てす。是れ奚ぞ虎に伝(つ)くるに翼を以てするに異ならんや。応仁の乱、是れその由つて起る所なり。而して終に上将(足利氏)も亦た虚器を擁すること王室に同じきを致す。その極や、その位号を并せてこれを喪へり。豈に計の失へる者に非ずや。
細野要斎『感興漫筆』を読む①─崎門学派の息遣い
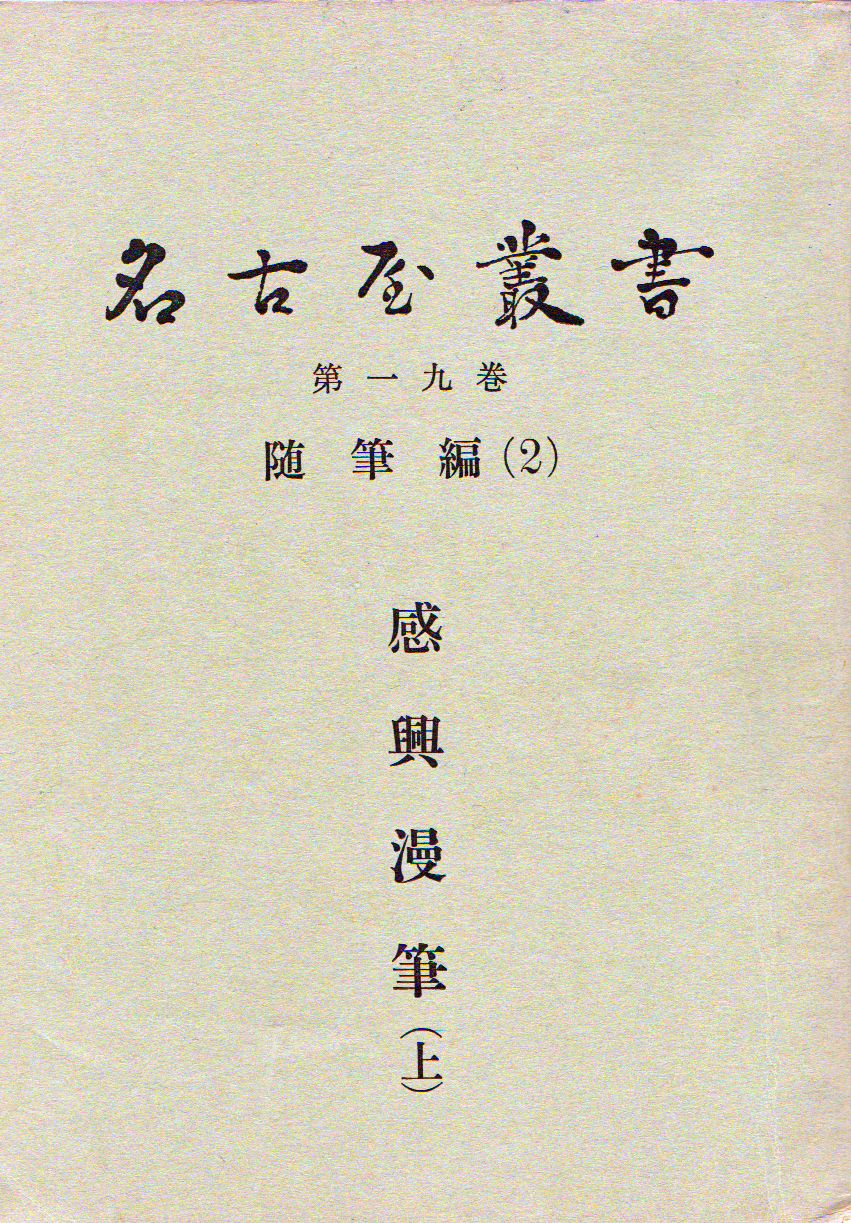 筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。
筆者は、尾張藩の尊皇思想は、崎門学派、君山学派(松平君山を中心とする学派)、本居国学派が微妙な連携を保ちながら強化されていったという仮説を持っている。このうち、幕末勤皇運動を牽引した崎門学派としては若井重斎や中村修らが知られているが、彼らの師こそ、「尾張崎門学の最後の明星」と呼ばれた細野要斎である。
要斎は、蟹養斎門下の中村直斎らから崎門学を、さらに中村習斎門下の深田香実から垂加神道を学んだ。要斎が遺した膨大な随筆『葎(むぐら)の滴』からは、尾張崎門学派の高い志と、日常の息遣いを感得することができる。
この貴重な記録『葎の滴』の中心部分を構成するのが、『感興漫筆』であり、その原本は伊勢神宮文庫に収蔵されている。『感興漫筆』は要斎二十六歳の天保七(一八三六)年から始まり、死去した明治十一(一八七八)年九月まで、四十二年に及ぶ記録だ。
例えば、弘化四(一八四五)年五月の記録には、要斎が深田香実から垂加神道の奥義を伝授された感動が記されている(『名古屋叢書』第十九巻、五十八、五十九頁)。
「香実先生、予が篤志に感じ、神道の奥義を悉く伝授し玉ふ時に、誓紙を出すべしとの玉ふ。その文体を問ふに、先生曰、爾が意に任せて書し来れと、仍つて書して先生に献す。文如左。
神文
一 今度神道之奥義、悉預御伝授、誠以、忝仕合奉存候。深重之恩義、弥以、終身相忘申間敷候事。
一 御伝授之大事、弥慎而怠間敷候事。
一 他人は勿論、親子兄如何様に懇望仕候共、非其人ば、猥に伝授等仕間敷候。修行成熟之人於有之は、申達之上、可請御指図之事。
右之条々、堅可相守候。若し於相背は、可蒙日本国中大小神祇之御罰候。仍而、神文如件。」


