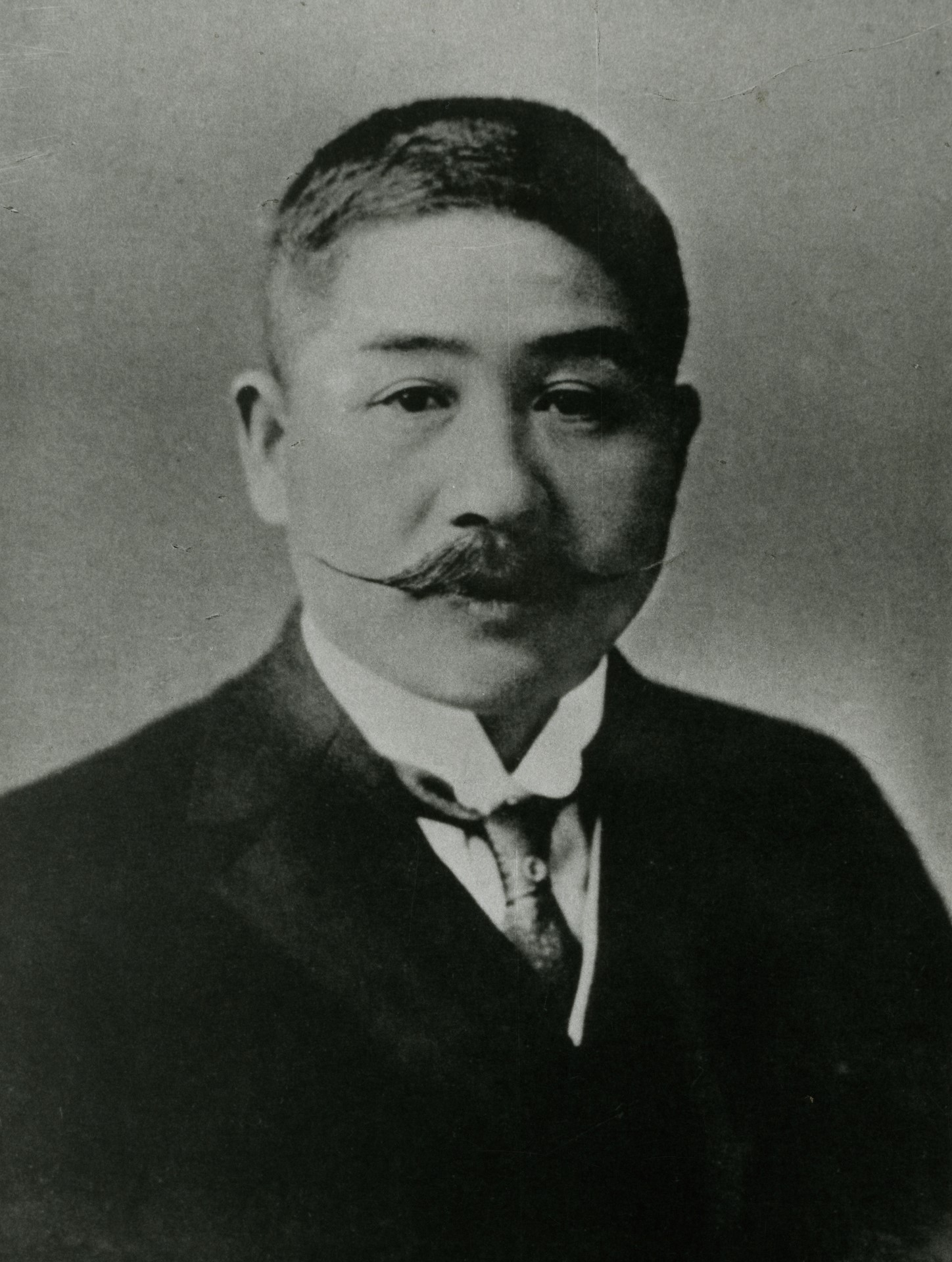『木村武雄の日中国交正常化─王道アジア主義者・石原莞爾の魂』のレビューを、はぐらめい氏が書いてくださいました。
〈木村武雄は私が住む地域選出の代議士だった。しかし、木村の思想的バックボーンへの関心は「金権的」イメージによってすっかり曇らされてしまっていた。木村武雄が私にとって身近であったはずの高校時代までは、ウォー・ギルト・インフォメーション・プログラム(WGIP)がしっかり浸透した教育環境だった。それゆえ、石原莞爾に連なる木村武雄像は闇の中でしかない。木村武雄vs 黒金泰美という、この地の保守を二分した激しい選挙のみが印象に残る。黒金泰美は1962年第二次池田内閣で官房長官を務めるが、1964年「黒い霧」として騒がれた吹原産業事件の中心人物として『金環食』(石川達三1966)という小説にまでなり、その後仲代達矢主演で映画化もされる。そうしたあおりで大成を期待されていたはずの黒金は政界から消えてゆく。梶山季之の『一匹狼の唄』(実業之日本社 1967)も黒金泰美は悪役だ。木村との暗闘がうかがえる。一方の木村は、1967年に第2次佐藤内閣の行政管理庁長官兼北海道開発庁長官、その後1972年第一次田中角栄内閣で建設大臣兼国家公安委員長を務めることになる。私の中での木村武雄の実像はそうした記憶の中で曇らされていた。坪内氏はその曇りを吹き飛ばして、本来の木村武雄像をくっきりと浮かび上がらせてくれている。
この書の「はじめに」はこう始まる。《令和4年9月29日、日中国交正常化50周年を迎えた。しかし今、対中強硬派の間では日中国交正常化の評判は決して良くない。国交正常化は、日本が政府開発援助などを通じて中国の経済発展を後押しし、中国を大国化させた元凶だと捉えられているからだ。/しかし、本書の主人公、木村武雄に光を当てるとき、日中国交正常化の評価は一変するかもしれない。木村は、石原莞爾の王道アジア主義体現の一歩として、日中国交正常化を位置づけていたのだ。/王道アジア主義とは、覇道の原理でアジアに迫る欧米の勢力を排除し、王道の原理に基づいたアジアを建設することにある。王道とは道徳、仁徳による統治であり、覇道とは武力、権力による統治だ。王道アジア主義の基本原則は、「互恵対等の国家間関係を結ぶ」、「アジア人同士戦わず」である。》(10p)戦後木村は石原の遺志を頑なに引き継ぐ。《木村は、「自分の後継には福田赳夫を」という佐藤(栄作)の意向に反して、田中派結成を主導、田中政権を見事に誕生させたのである。その過程で、木村と田中の間には、田中政権誕生の暁には日中国交正常化に動くという固い約束が交わされていたのである。》(11p)この書の意義はその経緯をつぶさに辿ったことにある。
なぜこれまでこのことが見えなかったのか。ひとつは木村武雄自身が「政界の影武者」に徹するという意志を持っていたことにあるが、そこにはアメリカの影がある。《田中政権の日中国交正常化はアメリカの警戒感を掻き立てた。しかもアメリカは、田中の背後で動く木村武雄に石原莞爾の影を見ていたのではないか。占領期の言論統制によって壊滅したかに見えた石原の王道アジア主義は、生き残っていたのである。》(11p)田中を葬る画策としてロッキード事件が起こされる。《キッシンジャーの謀略だったとの説もある。》(12p)木村は木村で交通事故が因となって、復帰を果たすものの命を縮めることになる。《親父の事故は田中総理の動きを止めるための謀略だったと言う人もいます》(木村莞爾談 195p)。
この書は、金にまみれ、行き着くところ殺し合いにも至る凄惨な政治の泥沼から、木村武雄という稀有な政治家をすくいあげた。あらためて、木村武雄に学ぶべきことは多いと思わされている。〉