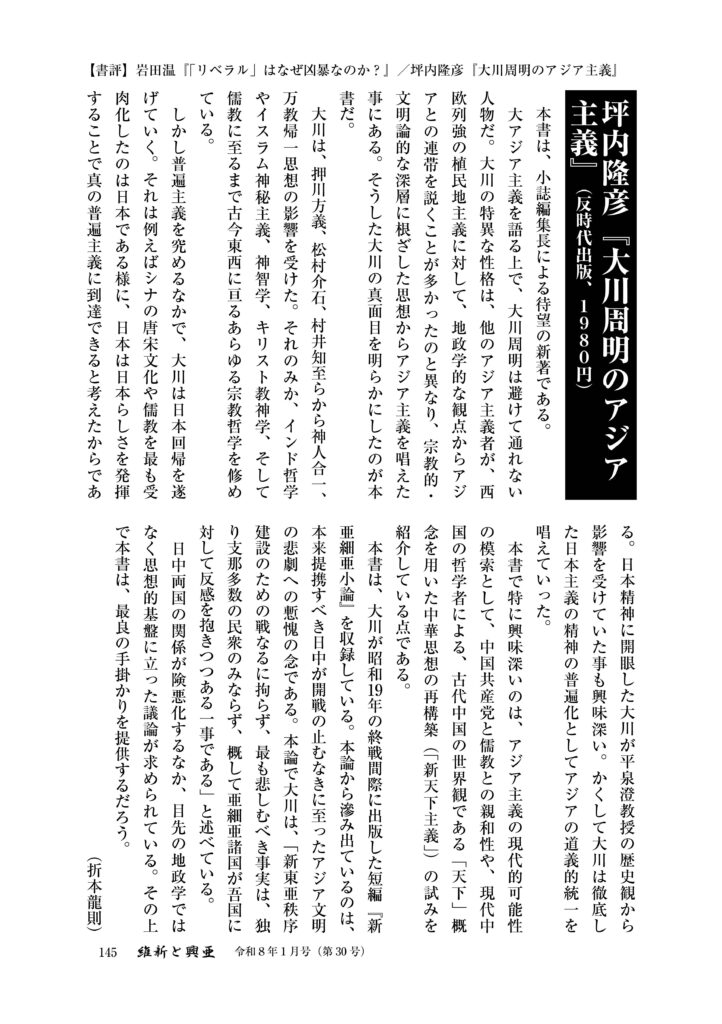本書は、小誌編集長による待望の新著である。
大アジア主義を語る上で、大川周明は避けて通れない人物だ。大川の特異な性格は、他のアジア主義者が、西欧列強の植民地主義に対して、地政学的な観点からアジアとの連帯を説くことが多かったのと異なり、宗教的・文明論的な深層に根ざした思想からアジア主義を唱えた事にある。そうした大川の真面目を明らかにしたのが本書だ。
大川は、押川方義、松村介石、村井知至らから神人合一、万教帰一思想の影響を受けた。それのみか、インド哲学やイスラム神秘主義、神智学、キリスト教神学、そして儒教に至るまで古今東西に亘るあらゆる宗教哲学を修めている。
しかし普遍主義を究めるなかで、大川は日本回帰を遂げていく。それは例えばシナの唐宋文化や儒教を最も受肉化したのは日本である様に、日本は日本らしさを発揮することで真の普遍主義に到達できると考えたからである。日本精神に開眼した大川が平泉澄教授の歴史観から影響を受けていた事も興味深い。かくして大川は徹底した日本主義の精神の普遍化としてアジアの道義的統一を唱えていった。
本書で特に興味深いのは、アジア主義の現代的可能性の模索として、中国共産党と儒教との親和性や、現代中国の哲学者による、古代中国の世界観である「天下」概念を用いた中華思想の再構築(「新天下主義」)の試みを紹介している点である。
本書は、大川が昭和19年の終戦間際に出版した短編『新亜細亜小論』を収録している。本論から滲み出ているのは、本来提携すべき日中が開戦の止むなきに至ったアジア文明の悲劇への慙愧の念である。本論で大川は、「新東亜秩序建設のための戦なるに拘らず、最も悲しむべき事実は、独り支那多数の民衆のみならず、概して亜細亜諸国が吾国に対して反感を抱きつつある一事である」と述べている。
日中両国の関係が険悪化するなか、目先の地政学ではなく思想的基盤に立った議論が求められている。その上で本書は、最良の手掛かりを提供するだろう。
(折本龍則)
「『大川周明のアジア主義』」カテゴリーアーカイブ
『大川周明のアジア主義』インタビュー(「宗教者・大川周明」『宗教問題』52号、令和七年 Winter)
『大川周明のアジア主義』レビュー(イトー「拓大生が今、知るべき『魂の熱源』」令和7年11月7日)
拓殖大学に通う私が、今あえて「大川周明」と「大アジア主義」について知りたいと思ったのは、ごく自然な興味からだった。大学の歴史に深く関わるこの人物が、かつて何を考え、何を訴えたのか。その答えを求めて手に取ったのが、本書『大川周明のアジア主義』である。
読み始めてすぐに、私は単なる歴史的知識の習得を超えた、生々しい「熱」に圧倒されることになった。大川周明と拓殖大学の結びつきは、私が想像していた以上に濃密で、情熱的なものだったのである。
本書(第4章)によれば、大川は第三代学長・後藤新平に招かれ拓大教授に就任するが、その講義の影響力は凄まじかった。後に拓大理事長を務めた狩野敏は、当時の大川の講義を「教室は水を打ったように、聴き入る学生の眼はかがやき」「或る時は切歯しつつ時の移るのを忘れていた」と回想している。
この熱狂や「復興亜細亜の諸問題」に感激した拓大卒業生らによって「魂の会」が創立される。「アジアはヨーロッパの奴隷の境遇を脱却しなければならない」「亜細亜復興の戦士は否応なく日本改造の戦士でなければならぬ」と説く大川の思想は、当時の学生たちの魂を根底から揺さぶったのだ。
だが、本書の白眉は、大川という強烈な「点」だけを描くにとどまらない点にある。
例えば、大川に共鳴し、在学中から彼が設立した猶存社に参加していた卒業生・薩摩雄次(第2章)の具体的な活動。
そして何より、拓殖大学(台湾協会学校)の第一期生であり、大川とは別に「アジアを道義的に統一する」という「大亜細亜主義・即日本主義・即神惟道」の思想(第4章)に至っていた田中逸平の存在。
本書を読み解くと、大川一人が熱源だったというより、彼の思想を受け止め、共鳴し、あるいは独自に同じ頂を目指す「熱き魂」が、拓殖大学という「場」に集っていた事実が浮かび上がってくる。
大川周明のアジア主義は、現代の視点からは多くの議論を呼ぶ複雑なものだ。しかし、本書が描き出すのは、イデオロギーの冷たい分析ではない。虐げられたアジアの姿に「切歯」し、その復興と日本の改造を本気で信じた、生身の人間たちの「情熱の記録」である。
今、私が通うこのキャンパスで、かつてこれほどまでに熱く、真剣にアジアと日本の未来を憂えた先輩たちがいた。
歴史上の人物として遠くに感じていた大川周明が、そして彼を慕った拓大の先人たちが、生身の人間として迫ってくる。拓殖大学の学生はもちろん、自らの信念に「魂」を燃やした人々の軌跡に触れたいと願う、すべての人に一読をおすすめしたい一冊だ。
『大川周明のアジア主義』レビュー(さちひこ「大川周明の宗教論とアジア論」令和7年10月26日))
本書の第一部「蘇る大川周明」において、著者は2章分を割いて大川の宗教論について解説している。彼の思想遍歴の中には、儒教から仏教、果てはイスラム教まで幅広いものがあるが、特に著者が重要だと指摘しているのは、大川が学生時代に「日本教会」というキリスト教の教会に入会していることである。日本教会の教義は「儒教的キリスト教」とも評されるそうだが、こうした宗教遍歴が彼のアジア主義の根底にあったと考えることは興味のあることである。
本書を読んで意外に思ったのは、大川周明が孫文をあまり評価していなかった、ということだ。アジア主義者の多くは孫文を支援していたというイメージがあるが、大川はむしろ、辛亥革命後の「五四新文化運動」に象徴されるような極端な旧文明の否定を見て、孫文のもとでは儒教道徳に基づいた政治は期待できない、と考えたのであろう。
第二部に収められた『新亜細亜小論』では、大川周明が1940年以降に書いた雑誌『新亜細亜』の巻頭言がまとめられている。特に印象的なのは、著者も第4章で引用している以下の文章である。
「日本民族は、拒むべくもなき事実として、自己の生命裡に支那およびインドの善きものを摂取して今日あるを得た。孔子の理想、釈尊の信仰を、その故国においてよりも一層見事に実現せるところに日本精神の偉大があり、それゆえにまた日本精神は取りも直さずアジア精神である。日本はこの精神を以てアジアにはたらかねばならぬ」(p113)
戦後80年を経て、安易な自民族中心主義が日本社会に表面化しつつある現在、あらためて大川周明の言葉に耳を傾けるべきだと、本書を読んでそう感じた。