 以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。
以下、『月刊日本』平成29年4月号に掲載した、山本直人先生の『敗戦復興の千年史』(展転社)の書評を紹介する。
戦後体制からの脱却を果たせないまま流れた72年間という歳月は、評者には長過ぎる時間に感じられてきた。その感覚をいくらか緩和してくれたのが、著者が平成27年9月に日本国体学会主催の講演会で行った講演だった。
この講演をきっかけに成ったのが本書だが、とりわけ評者が強い印象を受けたのが、講演で紹介された昭和天皇のご発言である。敗戦直後、米内光政海軍大将が昭和天皇に拝謁し、「敗戦の結果、日本の復興というものは、恐らく五十年はかかりましょう。何とも申し訳ないことでありますが、何卒、御諒承をお願い致します」と申し上げた際のお言葉である。この時、昭和天皇は米内に対して、「五十年で日本再建ということは私は困難であると思う。恐らく三百年はかかるであろう」と仰せられたのである(本書201頁)。
著者は、〈白村江から三百年といへば、元号でいふと応和年間にあたる。応和年間といへば村上天皇の御治世。すなはち、後年朝廷にとつての理想政治とされた「延喜天暦の治」のただ中にある〉と指摘し、白村江敗戦後の国家再建におよそ300年を要したことに注目する。
わが国の歴史において、本来の姿である天皇親政の時代が一貫して続いてきたわけではない。鎌倉幕府以来、明治維新に至るまで、700年に及ぶ幕府政治の時代が続いたことを考えるにつけ、歴史を長いスパンでとらえる視点が必要だと痛感する。
本書は、白村江敗戦後の天智天皇と、大東亜戦争敗戦後の昭和天皇とを重ね合わせ、その戦後復興の意味を問いかける。
昭和天皇は、昭和21年8月14日に、首相、閣僚たちを召されたお茶会で「終戦記念日にあたって、私はかつて(大正九年の春)大宰府を訪れたときに聞かされた、あの有名な白村江戦の故事を思い出した。あのときは百済の再興を援助するべく、日本軍が出勤したが、唐と新羅との連合軍に完敗してしまった。そのあとで、当時の天智天皇がおとりになった国内整備の経綸を、文化国家建設の方策として偲びたい」とお話しされた(本書10頁)。
著者は白村江の戦いと大東亜戦争を対照し、それぞれの戦争に至る過程と敗戦後の歩みを比較する。飛鳥から白鳳期にかけての古代史と、明治から昭和までの近現代史を対照した年表(17頁)を見ると、文明開化(外来思想の受容)の発展とその衰退過程において、多くの符合があることに驚かされる。例えば、欽明13(552)年の仏教伝来と嘉永6(1853)年の黒船来航は、ともに「新文明との衝突」と位置づけている。戦後復興の共通点については、次のように述べる。
「白村江敗戦以来、大津宮で天智天皇が積極的に国内改革を進められたのと同様に、昭和天皇は日本が嘗てない世界規模の大戦の負け戦に直面し、しかも米軍による占領下といつた史上例のない事態にあつて、どうにかこの危機を乗り越えるべく、戦後改革を進めてこられた」(12頁)
白村江敗戦からの国家再建においては、律令制度の導入など「唐化」が進んだ。この「唐化」から脱却し、「延喜天暦の治」をもたらしたものは、天皇親政というわが国本来の姿への希求だったと評者は考えている。まず、醍醐天皇の父・宇多天皇(在位:887~897)が摂関政治を排除し、天皇親政に復すという明確な意志を示された。宇多天皇は、894年に遣唐使を廃止し、さらに『日本三代実録』など国史編纂に着手した。同時に、漢詩全盛時代においてもなお、国民には日本語護持の理想が維持され、やがて醍醐天皇時代の『古今和歌集』に結実した。
著者は、〈三百年の復興の道のりは、まだまだ緒に就いたばかりである。今から三十年後の「戦後百年」までに、新たなる「千年紀」への一歩が踏み出せるや否や。それは「今、ここ」を生きる、現在の我々自身の手に委ねられてゐる〉と結んでいる。
大東亜戦争敗北からの国家再建においても「米化」が進行した。それは非常時の手段であったが、いまやそれが目的化してしまっているようにも見える。
長い年月がかかろうとも、「米化」から脱却して、わが国本来の姿を取り戻すには、日本人がその理想を見失わず、日本語護持、国史護持を貫けるかどうかにかかっているのではなかろうか。



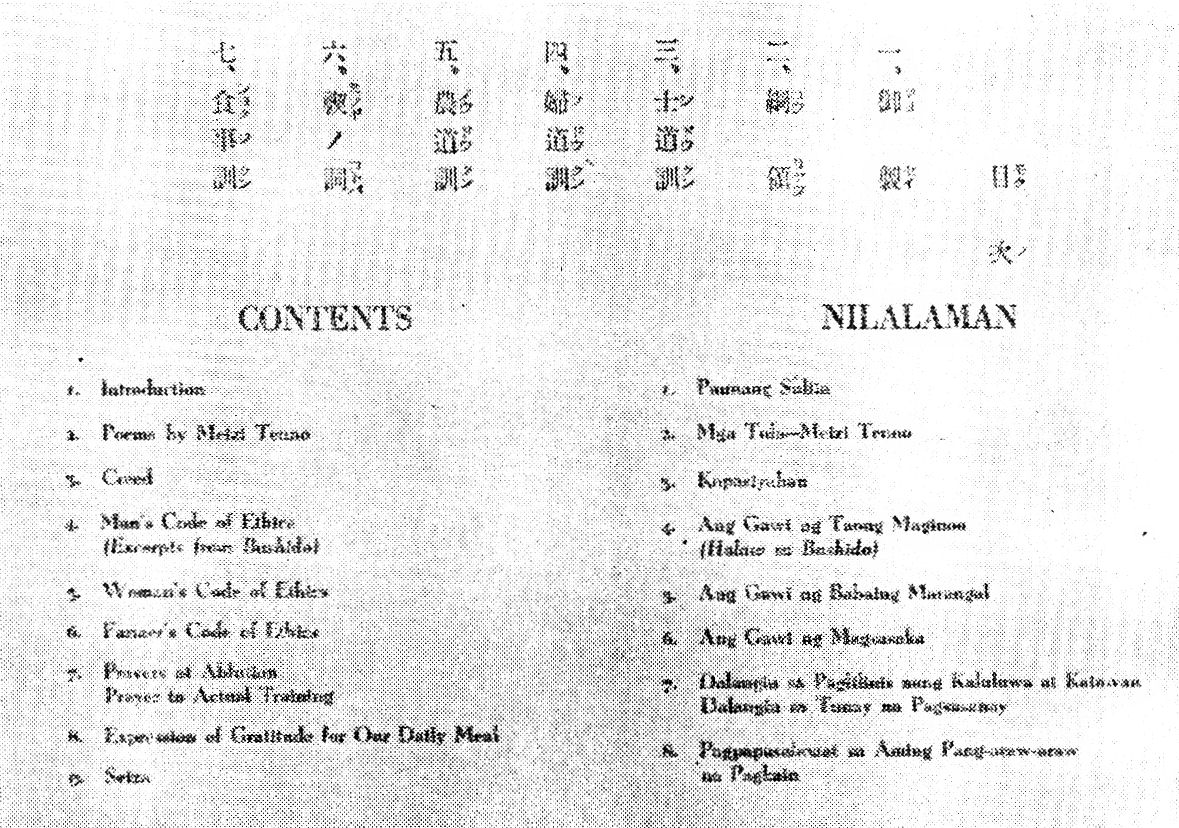
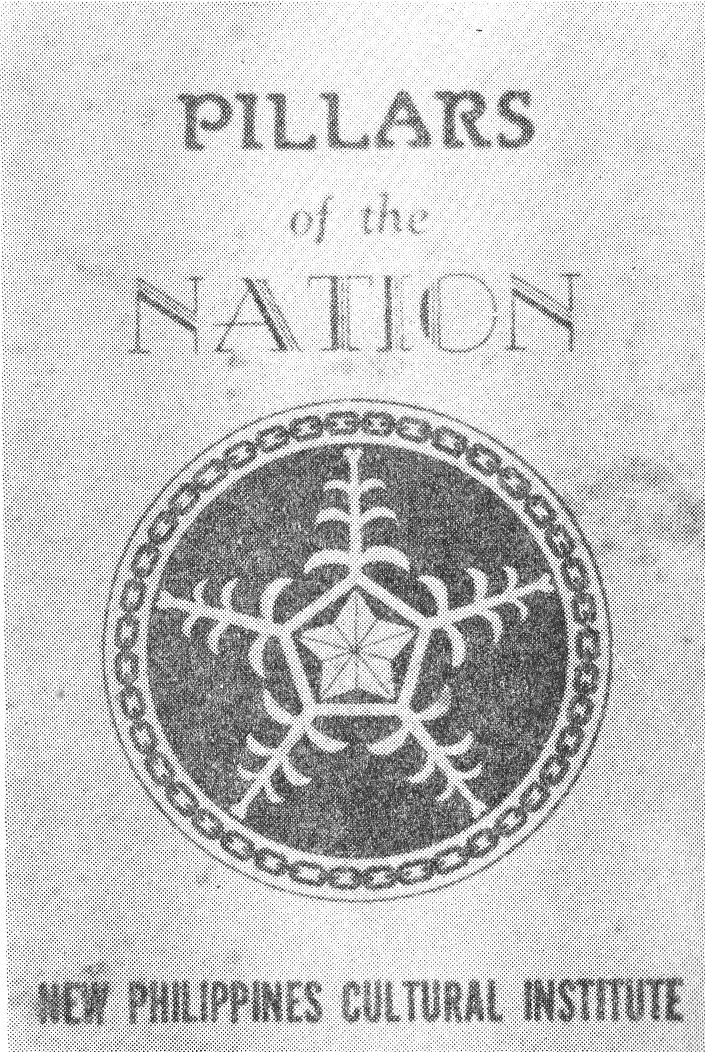

 昭和26(1951)年12月24日、フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士が来日したことをきっかけに、108人の日本人兵士の命を救う奇跡の曲「あゝモンテンルパの夜は更けて」は誕生した。
昭和26(1951)年12月24日、フィリピンの大亜細亜主義者ピオ・デュラン博士が来日したことをきっかけに、108人の日本人兵士の命を救う奇跡の曲「あゝモンテンルパの夜は更けて」は誕生した。