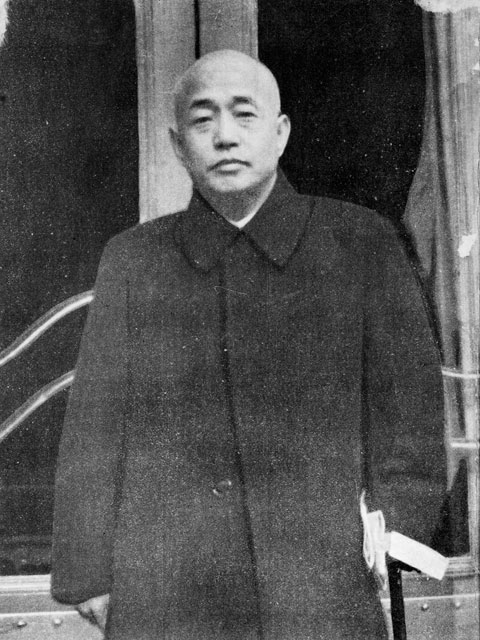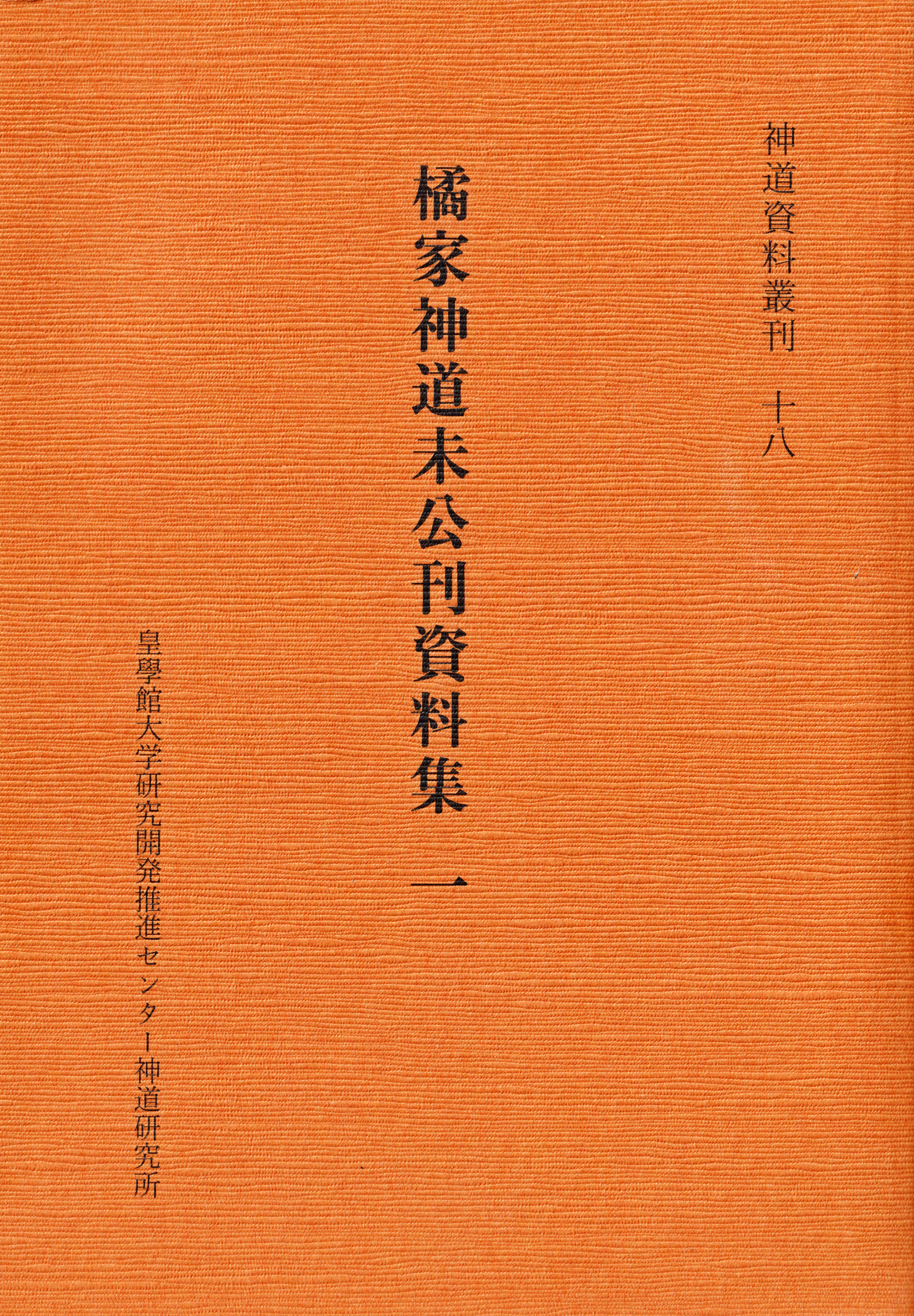はじめに
第一章 政治家・木村武雄の誕生
「俺は馬賊になる」
党人政治家・安達謙蔵との出会い
そんぴん(損貧)
「十一教授追放事件」
「混濁の世に社会正義を貫き徹す」
「自分が農民の先頭に立って戦う!」
突然逃げ出した石原莞爾
王道アジア主義への道
アジア統合と「国体と融合した仏教思想」
「満蒙占領論」から「満蒙独立論」への転換
橘樸の王道論
詠士を「覇道あることを許さぬ真人」と称えた笠木良明
稀有の大文章「自治指導部布告第一号」
石原莞爾と笠木良明の不幸なすれ違い
協和会に混在した王道アジア主義と覇道アジア主義
大亜細亜建設協会と大亜細亜協会
第二章 石原莞爾と東亜連盟
特使として派遣された宮崎滔天の長男龍介
石射猪太郎の和平工作
「日本は日清戦争以前にまで逆行するぞ」
「国民政府を対手とせず」
近衛三原則と東亜連盟
中山優の警告
「この日本軍が皇軍と僭称することを天はゆるすであろうか」
「支那難民救恤運動」の開始を訴えた葦津耕次郎
中野正剛と東亜連盟
東亜連盟協会を旗揚げ
石原─板垣─辻ラインが進めた「アジア大学構想」
辻政信が起草した「派遣軍将兵に告ぐ」
「日本主義」に潜む西洋覇道主義
日中の危機回避に動いた繆斌と権藤成卿
「西洋の覇道の番犬となるのか、東洋の王道の干城となるか」
汪兆銘は孫文の対日批判を切り落としたのか
東亜連盟に対する弾圧の開始
覇道アジア主義に飲み込まれる王道アジア主義
東条に歯向かい続けた木村武雄
上海の「木村公館」─王道アジア主義の牙城
木村の一声で集まった六十万トンのコメ
周恩来と東亜連盟

第三章 王道アジア主義の源流
八紘一宇(八紘為宇)に侵略的な意味はない
「派遣軍将兵に告ぐ」に示された八紘一宇
木村武雄の八紘一宇論
王道アジア主義の源流・西郷南洲
南洲は征韓論など唱えていない
「支那のことは宮島(誠一郎)に聞け」と仰せられた明治天皇
曽根俊虎と興亜会
宮崎滔天と孫文
王道アジア主義者を輩出した宮島詠士の善隣書院
人種差別撤廃を唱えた宮島詠士
中野正剛の名刺をもみくちゃに捩りつぶした詠士
南洲の東洋経綸と道義外交を引き継いだ荒尾精
「漢口楽善堂」に集結した興亜の志士
南部次郎と日華提携の真義
「将来の中国のためにこそ中国を撃つ」
皇国の天職と「百年の長計」
松井石根大将処刑の逆説
清国変法自強派と東亜会の連携
「明治維新に学べ」─康有為に影響を唄えた黄遵憲『日本国志』
日清両国の君主の握手
「乙未同志会」から同文会へ
東亜同文書院の精神
書院の建学精神を体現した石射猪太郎
第四章 執念の日中国交正常化
アジアの団結に対する強い危機感
「ペリーを呼んでこい」
辻政信の潜伏に手を貸した東亜連盟の同志たち
公職追放によって阻まれた木村武雄の動き
石原莞爾最後の言葉
総選挙で躍進した東亜連盟系候補
「秘密独善の外交一掃」を掲げる
日本民主党に加わらなかった木村武雄
鳩山一郎政権と反米ナショナリズム
廖承志・高碕(LT)貿易の端緒
三木武吉による「木村打倒」によって落選
日中接近を阻んだアメリカ
木村武雄と陳毅外交部長との会談
スハルト政権との太いパイプ
スハルトへの直談判で実現した第三十六師団(雪部隊)の遺骨収集
自民党内の親台派と親中派
佐藤栄作は親台派だったのか
「毛沢東と会う」と言った佐藤栄作
ニクソン・ショック後の自民党の変化
石原莞爾との誓い─御成山公園に聳え立つ「石原莞爾分骨記念碑」
幻の「佐藤栄作・王国権会談」
「佐藤内閣をここまで追い込んだ責任は岸・賀屋グループにある」
「田中さんの人柄に惚れてしまった」
ポスト佐藤は官僚ではなく党人派に
佐藤の逆鱗に触れた木村武雄
日中国交正常化を推進した外務官僚・橋本恕
外務官僚などに任せず、自ら中国の胸の中に飛び込む
田中派旗揚げの瞬間
北京の決断と木村武雄
国家公安委員会委員長として右翼を抑える
「今、日本の東亜連盟の同志はどうしていますか」
第五章 田中角栄失脚の真相─王道アジア主義を取り戻せ
「ジャップたちが上前をはねやがった」
高をくくっていたアメリカ
キッシンジャーの「秘密兵器」
親台派の強烈な反発を招いた日中国交正常化
怒号が飛び交った総理帰国当日の両院議員総会
日中航空協定交渉に反発した青嵐会
木村武雄と中川一郎の「激突対談」
田中退陣と「三木おろし」
木村武雄の交通事故には謀略説も
日中平和友好条約締結に情熱を燃やした木村武雄
渡辺三郎衆議院議員の追悼演説
日中蜜月の時代から日中対立の時代へ
アメリカを恐れる日本の指導者たち─田中角栄失脚のトラウマ
肇国の理想を失った国家は「生ける屍」だ
今も生きている黄禍論
大東亜共栄圏と「一帯一路」構想─王道アジア主義を取り戻せ
おわりに
── ようやく、日中国交正常化を実現するための環境が生まれてきた。石原莞爾先生の悲願をいまこそ私が成就させなければならない。
木村武雄はそう決意したに違いない。昭和四十六(一九七一)年八月十五日、木村は石原莞爾に誓いを立てるべく、米沢の御成山公園に「石原莞爾分骨記念碑」を建立した。昭和二十四(一九四九)年八月十五日に石原が亡くなると、木村は石原の遺骨を分骨し、米沢に持ち帰って埋葬していたのである。
令和四年八月、この分骨記念碑を訪れるため、木村武雄の次男莞爾氏、三男征四郎氏、孫の忠三氏の案内で、大アジア研究会代表の小野耕資氏とともに車を走らせた。中腹の御成山公園からは米沢盆地を見渡せる。そこからさらに八百メートルほど山道に沿って登ると、重厚な記念碑が姿を現した。高さは五メートルほどもある。木村はこの記念碑を石原の故郷鶴岡に向けて建てたという。木村が撰した碑文には、彼の思いが凝縮されている。
〈石原莞爾先生は明治二十六年一月十八日、山形県鶴岡市日和町で生誕されて、昭和二十四年八月十五日山形県飽海郡遊佐町に逝去された。在世六十年七ヵ月である。
先生の歴史は昭和六年九月十八日の満州事変と満州建国に要約し得るが、その中に包蔵された先生の思想はこの歴史よりも遥かに雄大で、岡倉天心のアジアは一なりの思想、孫文の大アジア主義と軌を一にする東亜連盟から世界最終戦争論にまで発展する。その総てが世界絶対平和を追求する石原先生の革命思想の発露である。

岡倉天心が明治二十六年七月、中国に渡って欧州列強の半植民地政策による貧困と苦痛をつぶさに観察して足を印度に延ばし、詩聖タゴールと交ってヨーロッパの繁栄はアジアの恥辱なりと喝破してアジア復興をアジアの団結に求めて印度を追放されたのも、孫文が日本に亡命してアジア主義を提唱して中国の独立を日本の援助に托したのも、石原先生が満州を建国して東亜連盟に踏み出したのも、その真情は総じてアジアの解放にある。
先生はアジアを直視して、アジアの独立と繁栄が、隣国を敵視反目する中国と日本の調整に始まるとした。そして先の両国の中間にあたる満州に日華民族の協和する王道楽土を建国し、これを橋梁として多年抗争する両国を東亜連盟で結んで欧米勢力と対決して人類歴史の前史を最終戦争の勝利で締めくくり、かくて世界絶対平和の後史をアジア人の道徳を中心として建設せんとした。だが、その構想は爾後の戦争で歪曲蹂躙され敗戦と共に埋没したが、先生の思想と行動は昭和前史の□□と共に永く後世を照鑑する事と確信する。世に石原先生ほどアジア人を愛した人は少ない。
そしてその解放と繁栄と世界絶対平和を、マルクスの唯物史観を超えた先生の戦争史観に□□を托されたが、史観の予言した如く、今や人類の前史は早晩終りを告げんとし、人類が世界絶対平和の後史に突入する日も間近かである。
先生の遺骨を分骨して郷里米沢に持参して二十二年になる。昭和四十六年八月十五日埋葬した記念としてこの碑を建立する〉(□は判読不明)
ここにある「敵視反目する中国と日本の調整に始まる」という言葉こそが、日中国交正常化を目指す木村武雄を支え続けたのである。
幻の「佐藤栄作・王国権会談」

この記念碑を建立した直後、木村武雄は佐藤栄作を動かそうとした。そのために、まず王国権と佐藤栄作の会談をセットしようとしたのである。王は、戦前に日本に留学した経験を持つ外交官であり、昭和四十五(一九七〇)年に中国人民対外友好協会副会長、中日友好協会副会長に就任していた。
昭和四十六(一九七一)年八月二十一日、日中国交正常化を見ることなく、松村謙三が死去した。その葬儀に参列した王国権は、政府関係者、各界の有力者とも次々と会談し、「王国権旋風」を巻き起こした。
松村の葬儀は八月二十六日、東京築地の本願寺で執り行われた。王は最前列に着席していた。しばらくすると佐藤総理が会場に現れ、わざわざ王の前に来て、握手を求めながら、「遠路はるばるお越しいただき、非常に感謝しております」と言ってから、着席した。
葬儀が終わると、佐藤総理は再び王のところに来て、「周恩来総理によろしくお伝えください」と言った。王は「ありがとうございます」とだけ答えた。
実は、王が日本を訪れる前、木村は香港に飛び、あるお寺のお堂で王と密かに面会していたのである。王が来日する際、佐藤総理と会談させようと根回しをしていたのだ。そして、木村は官房長官の竹下登に、王を羽田で出迎えて、佐藤総理との会談をセットするように指示していた。そして、木村は、王・佐藤会談の結果を聞くため、香港で王の帰りを待っていた。戻った王に、木村が「佐藤総理と会談はできましたか」と問うと、「できなかった」との答えだった。
この時の木村の失望と怒りは想像を絶するものだった。日本に帰国した木村は、そのまま官邸に乗り込み、竹下のいる官房長官室に怒鳴り込んだ。そして、テーブルにおいてあったコップの水を竹下にぶっかけて、「おまえは政治がわからん?野郎だ」と怒鳴りつけた。その場にいた木村莞爾氏は「あれほど激高した親父は見たことがなかった」と振り返る。それほど木村は、佐藤栄作・王国権会談に賭けていたのだろう。
「佐藤内閣をここまで追い込んだ責任は岸・賀屋グループにある」
やがて佐藤への木村の期待は失望へと変わっていった。その引き金の一つとなったのが、国連の中国代表権問題をめぐる佐藤の姿勢だった。
昭和二十四(一九四九)年十月の中華人民共和国政府成立以来、台湾政府は中国本土に対する実効的支配を失った。それ以来、国連での代表資格をめぐって、北京政府と台湾政府が争ってきた。
ところが、昭和三十五(一九六〇)年になると、台湾支持に賛成の国は、反対国と棄権国の合計を下回るようになった。さらに、中国は昭和四十五(一九七〇)年以降、カナダ、イタリアなどと次々に国交を樹立した。こうして、昭和四十五年十一月の国連総会では、「中国の加盟、台湾の追放」を骨子とするアルバニア決議案が初めて過半数の支持を得たのである。
これに対して、日本とアメリカは「逆重要事項指定案」で対抗しようとした。台湾追放の部分を総会の三分の二多数を要する事項に指定するという案だ。木村は、佐藤に「日本は逆重要事項指定の提案国にだけは絶対になってはいけない」と言い続けていた。
ところが、昭和四十六年の国連総会で、日本はアメリカとともに「逆重要事項指定案」の提案国になったのである。こうした佐藤政権の姿勢に、北京政府も不満を抱いていた。周恩来首相は、九月に自民党若手議員とともに訪中した川崎秀二に対して、「国交正常化交渉は、次期政権とのみを行う」と述べた。
木村は、『週刊文春』のインタビューで、次のように不満をぶちまけた。その矛先は外務省に、さらには岸信介や賀屋興宣にも及んだ。
「総理は何も逆重要を自分で考え出したわけではないのです。総理の知らない間に、外務省の役人どもが逆重要という手をアミ出してアメリカに持っていった。アメリカがこれに飛びついたのはなぜだと思います? 今後の競争相手は日本だと彼らが考えているからですよ。そのためには、中国が日本と親しくなってほしくないわけですね。……佐藤内閣をここまで追い込んだ責任は岸・賀屋グループにあると思います。総理はいつもわたしの一つの中国論に耳を傾けて聞き入ってくれる。ところが岸さんのグループに会うと、とたんにグルリと意見が変わってしまうんだ」(「総理〝ご意見番〟木村武雄の転身」『週刊文春』昭和四十六年十月二十五日号)
結局、日本が提案国となった「逆重要事項指定案」は、昭和四十六年十月二十五日、賛成五十五、反対五十九、棄権十五で否決されたのである。そして、「中国の加盟・台湾の追放」を骨子とするアルバニア案が賛成七十六、反対三十五、棄権十七で可決された。この結果、台湾は国連脱退を表明し、中国の加盟が正式に決まった。
(『木村武雄の日中国交正常化─王道アジア主義者・石原莞爾の魂』)
日中の国交を正常化させた木村武雄は、昭和五十八(一九八三)年四月頃から持病となっていた糖尿病が悪化し、自宅で伏せることが多くなった。十月二十七日に様態が悪化し、米沢市立病院に入院した。その後、十一月四日に退院し、自宅療養を続けていたが、二十六日風邪による急性肺炎を併発して危篤状態に陥り、午後零時四十分、歳子夫人ら親族に見守られながら、八十一年の生涯を閉じた。
胡耀邦総書記が日本を訪問し、中曽根康弘首相と「平和友好、平等互恵、長期安定、相互信頼」の日中関係四原則を確認の上、「日中友好二十一世紀委員会」の設立を決定したのは、その三日前のことである。木村の最後の願いが叶ったように見える。
木村の死去を受けて、自民党山形県連会長(当時)の近藤鉄雄は、「木村先生は自民党の主流にありながらも、常に野党的な反骨、批判精神を持ち続け、時流の中に決して埋没することのない政治家だった」と語った。
十二月十一日に米沢市の市立体育館で行われた告別式では、天皇、皇后両陛下、中曽根総理、インドネシアのスハルト大統領から贈られた生花などが飾られ、故人ゆかりの約三千五百人が出席した。中曽根総理から寄せられた「国家のためかけがえのない偉大な政治家を失い、哀悼にたえない」との弔辞が代読された。
昭和五十九(一九八四)年二月九日の衆議院本会議で追悼演説に立ったのは、木村の同郷で社会党衆議院議員の渡辺三郎だった。以下、全文を掲げる。

「今ここに政界の大先達である木村武雄先生の政治活動を顧みますると、先生は、戦前、戦中、戦後の帝国主義から民主主義へと大きく変貌した政治状況の中にあって、外に対しては終始一貫民族協和を主張されました。日中友好に果たされた役割も大きく、また、インドネシア政府から贈られた最高功績章などはその端的な一例と言えましょう。
また、先生は、生まれ故郷米沢の風土と伝統によってはぐくまれた反骨精神、いわゆる米沢かたぎの人でもありました。
先生は、権力に迎合することなく、名利を捨てて、大胆かつ独特の悲憤慷慨口調で俗説に対する鋭い批判を行われたのでありますが、特に、官僚機構に頼り切った政治では、真に国家百年の大計を樹立することは不可能であるとの信念を強く持っておられました。そのため、政党政治研究会を設立して行政に先駆けする政治を唱えられ、政党政治の確立に並み並みならぬ情熱を傾注されたのであります。
先生は、その政治活動を通じて鋭い感覚と闘志あふれる行動で一貫されましたが、その反面、情に厚く、先生が小学生のとき、同じその小学校の教師をしておりました私の母が年老いてからは、健康を気遣われてしばしば激励のため我が家をお訪ねくださいました。私が社会党から県会議員になり、また、先生と同じ選挙区から本院の末席を汚すことになって、時に先生との間に激しく論戦する立場になってからも、その先生の御厚情はいささかも変わることがありませんでした。
歯にきぬ着せぬ言動と政界の指南番を自認し、進んで政界の影武者となり、保守政界の舞台回しに砕身された先生を、同僚、後輩諸君は元帥と愛称し、そのお人柄に親しく接してまいりましたが、国家、国民の繁栄、郷土の振興のためその一身を燃やし尽くして、先生はついに生涯の幕を閉じて逝かれました。
亡くなられた十一月二十六日は、折から、解散を直後に控えて政局は緊張し、また、地元米沢では保革一騎打ちとなった激烈な市長選挙の投票前日でもありました。昭和政治史の一断面をみずからの歩みをもって体現し、半世紀に及ぶ激動の時期をただ政治一筋に生き抜かれた先生をお送りするにあるいはふさわしい日であったのかもしれません。この日、豪雪の地米沢はこの冬初めての大雪となり、ちまたは白一色に包まれていきました。
先生の御令息莞爾君は、先生を追悼して次のように歌われております。
いつも、勇気と茫然とした姿勢をもてといった。
いつも、民衆のはかり知れない力を信じるといった。
いつも、この土地と日本民族のことを考えろといった。
いつも、あいまいな妥協は決してするなといった。
いつかお前は俺とけんかをしながら俺を越えてゆけといった。
と。この言葉の中に私は先生の真骨頂を見るのであります。(拍手)まことに感無量なるものがございます。
長年にわたって残された先生の御偉業は、憲政史上不減の光芒を放ち続けることを信じて疑いません。その御逝去は、本院にとっても国家にとっても多大の不幸と申さなければなりません。
ここに謹んで木村先生の御功績をたたえ、その人となりをしのび、心から安らかな御冥福をお祈りして、追悼の言葉といたします」
令和四年九月二十九日、日中国交正常化五十周年を迎えた。しかし今、対中強硬派の間では日中国交正常化の評判は決して良くない。国交正常化は、日本が政府開発援助などを通じて中国の経済発展を後押しし、中国を大国化させた元凶だと捉えられているからだ。
しかし、本書の主人公、木村武雄に光を当てるとき、日中国交正常化の評価は一変するかもしれない。木村は、石原莞爾の王道アジア主義体現の一歩として、日中国交正常化を位置づけていたのだ。
王道アジア主義の目的は、覇道の原理でアジアに迫る欧米の勢力を排除し、王道の原理に基づいたアジアを建設することにある。王道とは道徳、仁徳による統治であり、覇道とは武力、権力による統治だ。王道アジア主義の基本原則は、「互恵対等の国家間関係を結ぶ」、「アジア人同士戦わず」である。
戦前、木村は石原の思想に共鳴して支那事変拡大に反対、昭和十四(一九三九)年に東亜連盟協会を自ら旗揚げし、東条英機の覇道アジア主義に抗った。木村は戦後も石原の魂を守り続け、日中国交正常化に執念を燃やす。まず木村は佐藤栄作総理を動かそうとした。しかし、「笛吹けど踊らず」、佐藤は動かなかった。しかし、それでも木村は決して諦めなかった。そこで目をつけたのが、党人派の田中角栄であった。木村は、「自分の後継には福田赳夫を」という佐藤の意向に反して、田中派結成を主導、田中政権を見事に誕生させたのである。その過程で、木村と田中の間には、田中政権誕生の暁には日中国交正常化に動くという固い約束が交わされていたのである。
正常化に邁進した木村武雄の原動力は、王道アジア主義だった。それは、石原の理想の体現であり、西郷南洲を源流とする思想の継承でもある。王道アジア主義は、南洲を源流とし、宮島誠一郎、宮島大八、南部次郎、荒尾精、根津一、頭山満、葦津耕次郎といった人物に継承されていた。

では、なぜこれまで「日中国交正常化における木村武雄の役割」に光が当てられなかったのか。一つの理由は、木村自身が「政界の影武者として生きる」と決めていたことにある。しかし、さらに大きな理由は、彼がアメリカにとって不都合な人物と認定されたからだろう。田中政権の日中国交正常化はアメリカの警戒感を掻き立てた。しかもアメリカは、田中の背後で動く木村武雄に石原莞爾の影を見ていたのではないか。占領期の言論統制によって壊滅したかに見えた石原の王道アジア主義は、生き残っていたのである。本書では、これまで黙殺されてきた「木村武雄の日中国交正常化」の封印を解き、王道アジア主義の真髄を明らかにしていきたい。
■アメリカを恐れる日本の指導者たち─田中角栄失脚のトラウマ
木村武雄が亡くなってから七年後の平成二(一九九〇)年十二月、マレーシアのマハティール首相は東アジア経済グループ(EAEG、その後東アジア経済協議体=EAEC)を提唱した。日本、中国、韓国とASEAN(東南アジア諸国連合)からなるグループを形成し、真に対等、相互尊重、相互利益の原則による共同体を東アジアに作ろうという構想だ。
しかし、アメリカはこのマハティール構想に過剰に反応した。ブッシュ(父)政権のベーカー国務長官は、「どんな形であれ、太平洋に線を引くことは、絶対に認められない。EAEC構想は太平洋を二分し、日米両国を分断するものだ」とEAEGを批判した。
日本はアメリカの強烈な圧力によって、EAECに背を向けてしまったのである。平成三(一九九一)年十一月に開かれた渡辺美智雄外相主催のベーカー国務長官歓迎夕食会で、「アメリカが入らない組織には、日本も入らない」と事実上のEAEC不参加の密約を交わさせられたとも報じられている(『毎日新聞』平成三年十一月二十九日付朝刊)。
日中国交正常化がアメリカの逆鱗に触れて以来、日本の指導者たちは、主体的な外交を展開してアメリカを怒らせることを異常に恐れるようになった。田中角栄失脚のトラウマは今なお克服されていないのではないか。
ただ、多くの政治家、官僚、言論人がアメリカを恐れ、アメリカに阿り、EAEG参加に消極的姿勢を示す中で、堂々とEAEG参加支持を表明した人物もいる。福田政権時代に外務省アジア局長を務めた中江要介、外務官僚の古川栄一、元朝日新聞記者の林理介らである。中江は次のように述べていた。
「マハティール首相構想の場合にもまた、日本は先に米国の顔色を窺っているのである。米国がノーといえば、一緒になって何かとあら探しをする。米国がアジアの経済圏構想に反対するのは、米国の覇権主義が邪魔されるからであろう。そのしり馬に乗って構想をつぶすのに加担したとすると、それは日本の政治的役割を放棄したことになる。アジアと反対の方向に向いている日本には、アジアでの政治的役割はない」(中江要介『中国の行方』)
■肇国の理想を失った国家は「生ける屍」だ

ただ、日本人がマハティール構想に背を向けたのは、アメリカの圧力だけが理由だとは言い切れない。日本人に王道アジア主義の理想を取り戻す気持ちがあるならば、王道アジア主義に通ずるEAEG構想がマハティール首相から提案されたことを歓迎し、支持したはずである。
むしろ、多くの日本人は、かつて日本人が王道アジア主義を唱えて国際秩序の変革を目指した歴史さえ忘れてしまっているのではないか。だから、マハティール構想にまともに反応できなかったのかもしれない。
大東亜戦争における敗北、占領を経て、日本人は主体的に国際秩序を構築することを放棄してしまったのである。いまや「日本外交は大陸に深入りすれば失敗する」という考え方が、あたかも正しい「理論」のように語られているのが現状だ。
こうした現状を、アジアの解放、アジアにおける道義的秩序の確立のために命を捧げた先人たちは、どう思うだろうか。
いま筆者は、改めて西郷南洲、宮島誠一郎、宮島大八、南部次郎、荒尾精、根津一、頭山満、葦津耕次郎、権藤成卿、笠木良明、石射猪太郎、中山優といった王道アジア主義者たちの固い信念を噛みしめている。そして、アジアに志を抱き、苦難の人生を歩んだ無数の日本人の思いを想像している。こうした先人たちを、リアリズムの分からない愚か者として切り捨てられるのか。
いまこそ、日本人は王道アジア主義の理想を取り戻し、先人たちの魂を継ぐ時なのではないか。王道アジア主義の立脚点は肇国の理想、八紘一宇(八紘為宇)である。肇国の理想を失った国家は、もはや「生ける屍」である。
狭い意味での国家安全保障、物理的な国家の生存を最優先で考えれば、外交政策は与えられた条件、自国を取り巻く国際環境の中で、リアリズムに徹して構築されるべきだという結論が導き出される。冷戦終結後もなお日本人が日米同盟以外の選択肢を提示し得ないのは、自らの防衛を自らの手に取り戻すという気概を失ったからだけではなくて、このリアリズムが外交当局や知識人に定着しているからである。いわば、「物理的生存至上主義」である。
しかし、人間と同様、国家もまた、物理的に存続すればそれで十分というわけにはいかないのではないか。人間に魂があり、誕生の意味、生きる意味があるのと同じように、国家にも魂があり、肇国の意味がある、と筆者は信ずる。どのような形で生存し、どのような役割を担って生存するか。それこそが重要なのではないか。だから筆者は、外交政策も肇国の理想の体現であるべきだと信じている。
■今も生きている黄禍論
実は、ベーカー国務長官は先に挙げた歓迎夕食会で、EAEGを徹底的に批判しながら、マハティール首相の民族服までヤリ玉にあげていた。その場にいた中曽根、竹下、宇野の各元首相ら日本側出席者は、批判の過激さに息をのんだという(『毎日新聞』平成三年十一月二十九日付朝刊)。
ここで即座に想起されるのが、田中角栄を口汚く罵ったキッシンジャーの「裏切り者の連中の中で、ジャップたちが上前をはねやがった」という言葉だ。アメリカ在住の政治アナリスト伊藤貫氏は、「キッシンジャーは、日本人に対して鋭い敵意と嫌悪感を抱いている」と書いている(『中国の「核」が世界を制す』)。
欧米の指導者の中には、「アジア人が国際秩序を構想するなど生意気だ」というメンタリティが残っているのではないか。
遡れば明治二十八(一八九五)年四月二十三日、フランス、ドイツ、ロシアの三国は、日清戦争の日本の勝利とそれに伴う下関条約によって日本に割譲された遼東半島を清国に返還しろと要求してきた。実は、この三国干渉も黄禍論と連動していたのである。三国干渉の三日後、ドイツ皇帝ヴィルヘルム二世はロシア皇帝二コライ二世に宛てた手紙で、「アジア大陸を開拓し、巨大な黄色人種の攻撃からヨーロッパを守ることが、ロシアの将来の偉大な任務であることは明らかである」と述べている。同年秋、ヴィルヘルム二世は、自らが原画を描き、宮廷画家ヘルマン・クナックフースが仕上げた寓意画「ヨーロッパの諸国民よ、汝らの最も神聖な宝を守れ!」をロシア帝国の皇帝ニコライ二世に贈呈している。
この寓意画は、ヴィルヘルム二世自身による解釈では、絵の左上の十字架の下で、鎧で身を覆っている女性たちは一人一人が当時のヨーロッパ諸国を象徴している。その先頭で手に剣を携えているのは、大天使ミカエルで、その左手が指している対岸が東洋である。そこでは、火炎が起こっていて、炎の上には龍が、その背中に仏陀を背負って、西洋の都市にせまっている(飯倉章「世紀の終り『黄禍』の誕生」『国際文化研究所紀要』平成九年七月)。
翻って現在の米中対立の背景にも、黄禍論が横たわっているように見える。「西洋文明に対する新たな挑戦者として中国が現れた」と欧米の指導者たちは認識しているのではあるまいか。実際、令和元(二〇一九)年四月、米国務省政策立案局局長のキロン・スキナー女史は、安全保障関連のフォーラムで以下のように語ったのだ。
「東西冷戦は西洋諸国(Western Family)の間での戦いだったが、中国は西側の思想、歴史から産まれたものではない。米国は白人以外と初めての大きな対立を経験しようとしている」
欧米の指導者たちが最も恐れているのは、日本と中国が手を握り、アジアが団結することである。それを避けるために、欧米の指導者たちは、日本と中国を戦わせて互いに消耗させ、漁夫の利を得ようとしているのかもしれない。(坪内隆彦『木村武雄の日中国交正常化─王道アジア主義者・石原莞爾の魂』より)
令和4年10月7日に開催された『維新と興亜』塾「橘孝三郎を読み解く」(講師:小野耕資)に参加させていただいた。
小野氏からの講義の後、東条政権下の橘孝三郎の動向にかかわる質問があった。近衛新体制下、東条政権下における維新派の動向は極めて重要なテーマである。
小菅刑務所で服役していた橘が仮釈放となって出所するのは、昭和15年10月17日のことである。血盟団事件の井上日召も同じ日に出所している。
三上卓は、これより先昭和13年7月に仮釈放となっている。橘が仮釈放となる少し前の昭和15年2月前後、三上は大岸頼好らとともに、何度も近衛文麿と面会、やがて近衛新体制運動が動き出す中で、同年7月初旬、七生社の穂積五一らと日本主義陣営の横断的組織の結成に動き、同年8月16日 学士会館で「翼賛体制建設青年連盟」(後に皇道翼賛青年連盟と決定)を結成することを決めた。一方、井上日召は、三上や四元義隆の協力を得て、昭和16年7月に「ひもろぎ塾」を設立した。
東条政権が発足するのは、その3カ月後の昭和16年10月18日である。東条は昭和17年1月18日、戦時刑事特別法案を国会に提出した。国家総動員法、言論出版集会結社等臨時取締法につらなる戦時体制強化を目指した法案だった。一部議員の反対を押し切って成立した同法は同年3月に施行された。東条は、さらに同年末に召集された第81議会で、「国政を変乱」する目的の刑法犯や、治安・秩序を乱す宣伝活動なども処罰対象とする同法改正案を提出した。帝京大学教授の小山俊樹氏は次のように述べている。
〈戦刑法の改正過程は、強権化した東条英機政権への反発者を炙り出すものとなった。
一九四三年二月、第八一議会では衆院議員の清瀬一郎(元五・一五事件弁護人)が、「言論の自由」を求め、統制強化をすすめる東条政権を正面から批判した。さらに鳩山一郎(元政友会)ら旧既成政党の非主流派(自由主義派)と、中野正剛(元東方会・東方同志会会長)ら国家主義派、笹川良一・赤尾敏ら民間右派、水谷長三郎(元社会大衆党)ら旧無産政党系など、左右の立場を問わない衆院議員が結集して戦刑法の改正に反対した。皇道翼賛青年連盟も、東方同志会など一四団体と連名で反対を表明した。だが東条内閣は強行採決で改正案を成立させ、反対者への弾圧を強化した。
東条政権の高まる威圧を前に、三上ら維新勢力は軍部との対立を深める。毛呂(清輝)は回想する。
「東条の憲兵政治は常に私らの動きに眼を光らせていた。〔中略〕当時は支配者は官僚化した軍部であり、その治下での国内革新の運動は技術的にも非常に困難だった」。東方同志会の幹部も、三上とはこの頃に「相提携してともども東条内閣と戦った」と回顧する。
ただし毛呂によると、三上は皇道翼賛青年連盟の一部が「非常手段による東条内閣打倒を計画したとき」に反対し、委員長を辞して脱退したという(「日本クーデターの真相」)。三上の動向は判然としないか、青年たちを危険にさらすテロは本意ではなかったのであろう。
このとき政権批判の急先鋒は、東条首相をこきおろす「戦時宰相論」を『朝日新聞』に寄稿した(即日発禁)中野正剛であった。中野は密かに、天野辰夫(神兵隊事件首謀者)と結んで宇垣一成(元陸相・元外相)擁立工作を進めていた。片岡駿(勤皇まことむすび=五・一五事件元受刑者の本間憲一郎らを中心に一九三九年結成)の協力によって、東条に予備役へ編入された石原莞爾(陸軍予備役中将)とも密かに連絡した。
一九四三年一〇月二一日の全国一斉検挙は、これらの反東条の動向を圧殺しようとするものであった。東方同志会・勤王まことむすび・大日本勤王同志会などの民間右派から、百数十名を超える大量の検挙者が出た(皇道翼賛青年連盟の構成員もこの数に含まれる)。〉
やがて三上は東条暗殺計画に参画する。昭和19年6月22日、三上は東条政権打倒に動いていた高木惣吉海軍少将に近い神重徳大佐と密会、暗殺計画を作成していった。高木の残した記録によると、「決行人員は七人。場所は海軍省手前の四つ角。自動車三台に分乗し、海軍省内、大審院の濠沿い、内務省側にそれぞれ待機。(東条の)オープンカーが警視庁前に見えたら合図させ、前と両方の三方から挟み撃ちにして衝突させ、射殺する」という計画だった。
ところが、7月13日付で神大佐に、連合艦隊司令部参謀への転出内示が出される。そのため、計画の実行は一週間延期された。その間、7月18日にサイパン失陥の責任をとる形で、東条内閣は総辞職。暗殺計画は実行されなかった。
一方、永松浅造は『生きている右翼』で次のように書いている。
「皇道翼賛青年連盟の毛呂清輝、小島玄之もまた軍部の擅横に対して蹶起した。
その理由は、東条内閣と大政翼賛会と、陸軍大将阿部信行を総裁とする翼賛政治会とは、三位一体となって国政を壟断し、議会の真の機能を停止状態に麻痺させている。これは明かに欽定憲法を無視し、蹂躍した軍部中心の幕府的存在で、その亡状、天人倶に許しがたい。速かにその非を改めると同時に辞職せよと、猛然、非難攻撃をした」
ちょうど五十年前の昭和四十七年、田中角栄は日中国交回復に動いた。それを支えたのが元帥と呼ばれた男・木村武雄である。日中国交回復を使命と定めた木村の原点には、師・石原莞爾の民族協和主義があった。
昭和十六年三月、石原は京都の十六師団長を最後に、現役の軍職から退いた。当時、「石原退職の原因は、木村が石原将軍擁立の政治運動をやったことだ」という噂も流れていた。そこで木村は、謝罪もかねて石原を京都の師団長官舎に訪れたのだ。その時、石原は木村に次のように語ったという。
「今までの日本人は、民族独善主義の道を歩いて来た。そしてその結果、日清戦争・日露戦争にも勝ち、更に第一次大戦でも勝利して、日本は世界の三大列強の一つになる事が出来た。然し日本が満州問題に発言して以来、日本の民族独善主義は完全に民族協和主義に変ってしまったのだ。それで民族協和主義に徹しなければ、これからの日本は成り立たない。これからの日本は役に立たなくなるんだ」
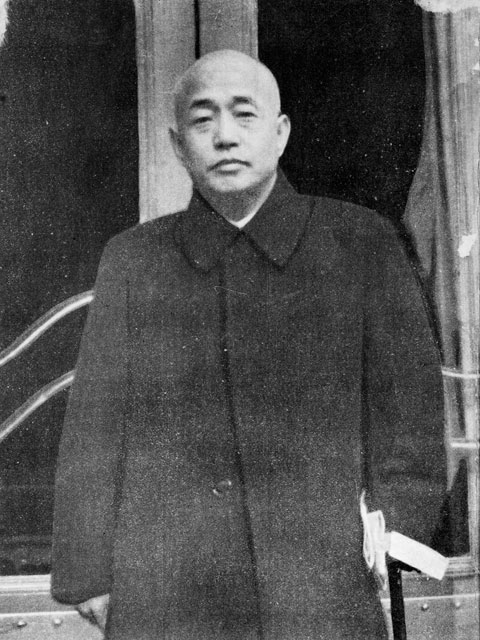

では、なぜ民族協和主義に変わったのか。石原は次のように語った。
「日本人は、日本と云う島国に住んでおる時代は民族独善主義でも良かったけれども、日本が大陸に発言して満州に新しい国造りをやってからは、完全に民族協和主義になってしまった。そうならざるを得なくなったのだ。それ以前には、朝鮮半島に新しい日本国を建設して、朝鮮民族と日本民族で手を携えて朝鮮内外の場所で、お互いが仲良くなるよう努力したが、その時にはまだ民族協和主義に日本は徹していなかったのだ。
その証拠には、日本が朝鮮半島で教育を指導するようになったが、その教育を通して、朝鮮民族の使用しておった朝鮮語は使わせないようにした。朝鮮語を教えないようにして日本語だけで朝鮮民族の教育をやった。これをみても、その時代の日本は、やはり日本民族の独善主義がそのままその時代まで横行しておったと思う。ところが、日本が一度満州に足場を造って、そこで満州問題について日本が発言するようになってからは、民族独善主義では通らなくなった。それで民族協和主義に変ったのだ。なぜかと申せば、満州には在来の先住民族として蒙古人が住んでおる。そこに満州民族がどっとおしかけてきて、満州民族も住むようになった。更に漢民族も多数住みつくようになった。それに西の方からはロシア人がやって来て住むようになり、東の方からは朝鮮民族がやって来て住むようになり、そこにまたまた日本人が、日清日露戦争以来、特に日華事変以来やって来て住みつくようになってからは、六族が満州に住むようになった。そこで六族が相共に協和しなければ満州国と云うものを育成、強化する訳にはゆかなくなったのだ。それ以来、日本人は民族独善主義をかなぐり捨てて、民族協和主義を掲げざるを得なくなったのだ」
この話を聞いて、木村は民族協和主義が日本にとっては必要欠くべからざるものである事を確信した。
この度、皇學館大學教授の松本丘先生が編まれた『橘家神道未公開資料集 一』(神道資料叢刊 十八、令和四年三月)を贈呈していただいた。誠に有難うございます。
筆者は崎門学研究会代表の折本龍則氏、同副代表の小野耕資氏とともに崎門学、垂加神道の勉強を続けてきたが、『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』執筆過程で、尾張藩の垂加神道派にも強い関心を持つようになった。
尾張藩初代藩主・徳川義直の遺訓「王命に依って催さるる事」は、第4代藩主・吉通の時代に復興し、明和元(1764)年、吉通に仕えた近松茂矩が『円覚院様御伝十五ヶ条』として明文化した。
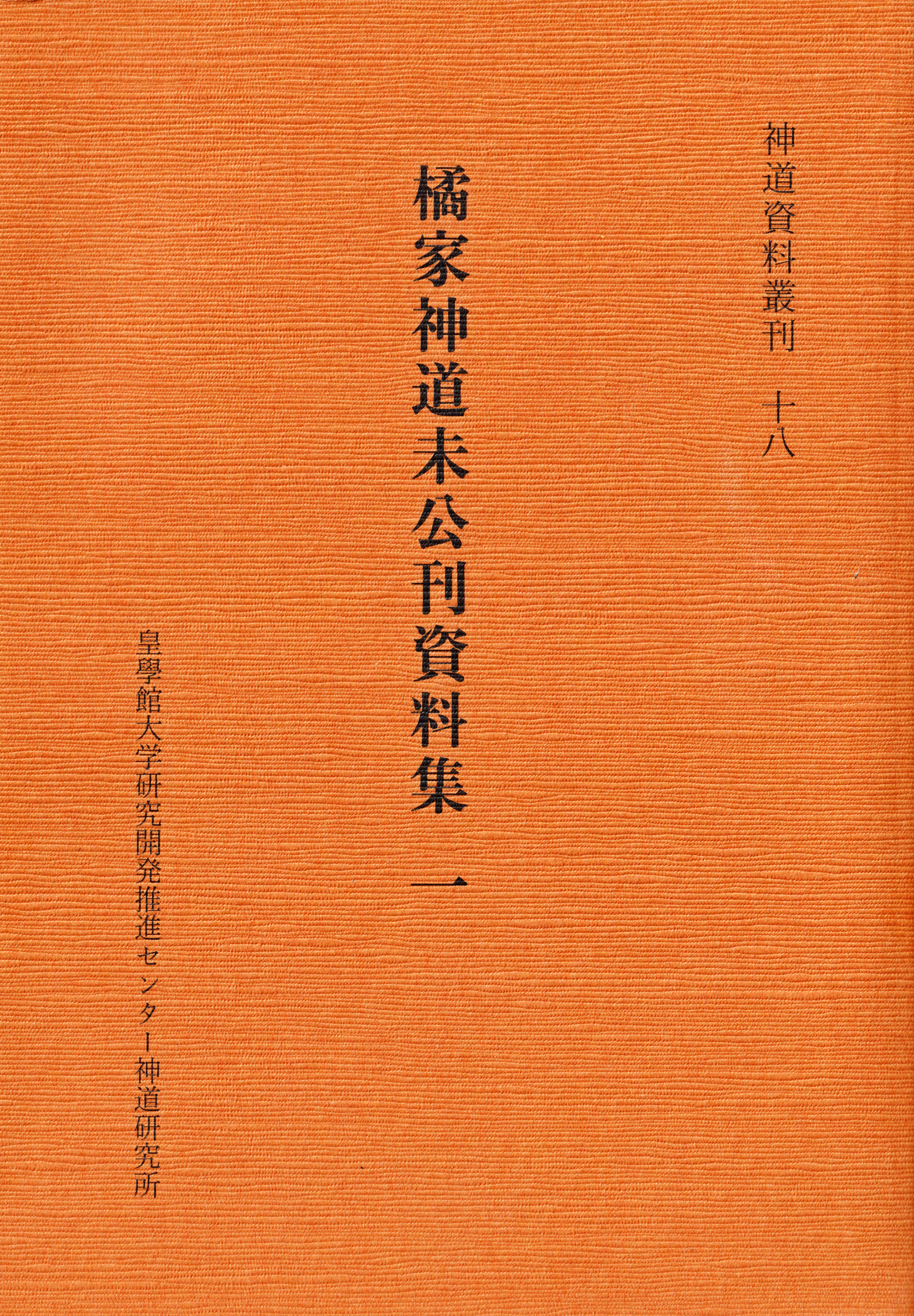
近松茂矩は、長沼流を皆伝した後、橘家神道に継承された秘伝を取り入れて、独自の流派「一全流」を創始していた。
今回、松本先生が編まれた『橘家神道未公開資料集 一』には、名古屋市蓬左文庫所蔵の『橘家神道口傳抄』が収められている。松本先生の解題にある通り、同書は玉木葦斎の講述、吉見幸和筆記に係る。安永四年に吉見が上京した際に、葦斎から伝授された橘家神道秘伝である。さらに、松本先生は次のように指摘されている。
〈本文と同筆の書入に「茂矩」の名が見えてをり、幸和門人で兵学者としても知られた近松茂矩の筆写に係るものと考へられる。尾張徳川家家令であつた鈴木信吉氏の旧蔵書である」(解題五頁)
茂矩が橘家神道の秘伝を伝授されていたことが窺われる。
拳骨拓史氏が『兵学思想入門』で引いているように、近松は『神国武道弁』で「所謂神道は武道の根なり。武道の本は神道なり。道に二つなし」と述べていた。そんな近松が、橘家神道の秘伝を伝えられていた敬公の『軍書合鑑』の真価を見抜いたのは決して偶然ではない。近松は『昔咄』において次のように書いていたのである。
「軍書合鑑は、寛永年間の御撰述の由、是又本朝にて、軍術正伝の書の最第一と称せん、故いかなれば、凡そ神代相承の軍術は、神武天皇より代々の天皇、天津日嗣の時に、三種の神器と同じく、御相伝ありし、但し敏達天皇慮有りて、其神伝軍術をば、難波親王へ御伝受あづけられて、親王の御子孫代々伝へて、守り奉るべき勅令にて、橘家代々受けあづかり奉りて、三十四代相承し、唯授一人として、他へみだりに、伝ふる事なし」
さらに近松は、「付会をなして、何流と称する軍師」たちを批判した上で、「天下の兵法を立てた」として長沼澹斎を称え、さらに次のように述べている。
「源敬(敬公)様此御選ありて、終に依王命被催に、筆を停め給ふ、これよく本朝神武の道を得させられし事、言はずして明白なり、故に予恐れながら、本朝正兵伝書編述の根元なりと、称し奉りぬ」
このように近松は、敬公が本朝神武の道を極めていたことを示すものとして「王命に依って催さるる事」をとらえ、尾張尊皇思想を力強く継承せんとしたのだった。
『維新と興亜』編集長・坪内隆彦の「維新と興亜」実践へのノート