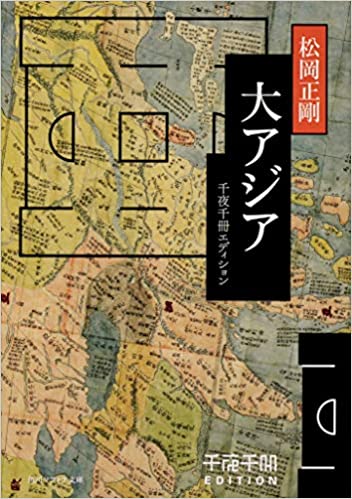令和2年7月、松岡正剛氏の『千夜千冊エディション 大アジア』(角川ソフィア文庫)が刊行された。「大アジア」というタイトルに驚き、筆者の問題意識と重なる多くの書物が手際よく紹介されていることもあり、熟読した。
さて、同書において、12年も前に書いた拙著『アジアの英雄たち』(展転社)を圧倒的ページ数(287~353頁)で取り上げていただいたことに、心より感謝申し上げる。
〈著者は日本経済新聞出身のジャーナリスト兼ライターの坪内隆彦で、「月刊日本」連載の『アジアの英雄たち』をもとに充実させた。タイトルに『アジア英雄伝』とあるように、あからさまな大アジア主義称揚の視点で綴られている。冒頭に頭山興助の「推薦の辞」が飾られているのだが、この人は頭山満のお孫さんだし、あとがきには田中正明の『アジア独立への道』(展転社)からの影響を記している。田中は松井石根の私設秘書から近現代アジア史の著述に向かい、『パール博士の日本無罪論』(小学館文庫)、『東京裁判とは何か』(日本工業新聞社)などを書いた。
そういう一冊ではあるのだが、当時の大アジア主義にかかわった人物を点検するには浩瀚かつ便利な一冊になっている〉
松岡氏が「そういう一冊ではあるのだが」と、わざわざ前置きされたことについては、いろいろ考えるところがあるが、筆者が「大アジア主義称揚の視点」で綴っていたことを否定するつもりはない。
ただ、大アジア主義といっても、在野のアジア主義と政府のアジア主義には違いがある。筆者は一貫してアジアの亡命志士たちが日本政府の政策に失望した事実を強調してきた。拙著の中でも次のように書いている。
〈アジアの志士たちにとって悲劇だったのは、日本政府の目標が、興亜陣営の崇高な目標と必ずしも一致していなかったことである。
神武創業への復帰を目指した明治維新の精神は、国家独立とそのための近代化という国家経営の論理が優先する中で、次第に形骸化していったように見える。
だからこそ、西欧列強との協調を重視した日本政府は、列強に阿り、アジアの志士たちを冷たく扱っていた。例えば、日仏協商を結んだ日本政府は、フランスの意向に沿ってクォン・デらベトナムの志士を国外追放した。このとき、クゥン・デらの失望はどれほど大きかったろうか。チャン・ドンフー(陳東風)は日本政府の姿勢に抗議して自決している。
(中略)
やがて、国際連盟脱退後、日本政府は列強に対する外交姿勢を改め、興亜外交に舵を切ったが、そこでも国家経営の論理が優先されていた。対米開戦後には、言葉の上では「アジア解放」というスローガンが前面に出てきたが、そこでもやはり、占領地域の統治、資源の確保など戦争遂行の論理が最優先されていた。
興亜論者の理想を信じていたアジアの志士たちは、それに戸惑いを隠すことができなかった。興亜論者と交流を続けたプラタップは、参謀本部から邪魔者扱いされ、東京から離れて小平への隠遁を強いられている。クルバンガリーもまた、最終的には日本政府・軍と微妙な関係に陥った。
ラモスも同様である。参謀副長の西村敏雄少将や松延幹夫参謀少佐、犬塚惟重海軍大佐など、軍の一部は、ラモスとそれに連なる旧ガナップ党員の役割に期待したが、エリート層登用路線を主張する村田省蔵大使や軍政監部の総務部長兼参謀の宇都宮直賢大佐は、ラモスを敬遠した。
(中略)
興亜の理想を維持した日本人の存在とあわせて、アジアの志士たちの苦悩をも直視することが、本当の興亜の理想を理解することになるのではなかろうか〉
いずれにせよ、松岡氏の『千夜千冊エディション 大アジア』は、日本人が「大アジア」という言葉の意味を改めて考える機会を提供してくれた。同書の末尾には〈いま「大アジア」を問うことは時代錯誤だろうか。そうでははあるまい〉とある。改めて「大アジア」を問うてみたい。