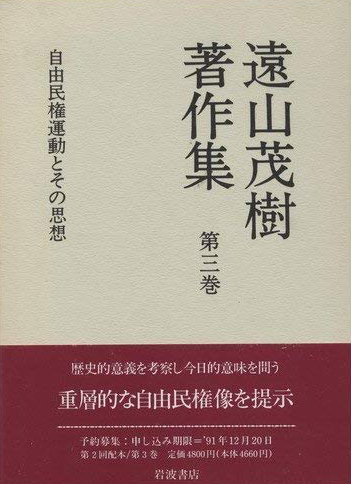 遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
遠山茂樹は、杉田定一について次のように書いている。
〈立志社周辺の自由民権の壮士達、例えば杉田定一の場合を考えてみよう。彼は本来の武士出身ではない。杉田家は越前随一の大地主で、藩の用達を務めた豪農・豪商である。しかし彼をして自由の闘いに身を挺せしめた意識は、庶民としてのそれではなく、あくまでも志士の気概であった。「国事の為に死生を度外に置き、天下を取るか、首を取らるるかは当年の理想なりしなり……獄中閑日月の間、書を読みて或は英雄豪傑の偉業を追慕し、或は志士仁人の艱苦を回想し」と述懐している。彼は自己の思想の系譜を次の如く説明している。「道雅上人からは尊王攘夷の思想を学び、東篁先生からは忠君愛国の大義を学んだ。この二者の教訓は自分の一生を支配するものとなって、後年板垣伯と共に、大いに民権の拡張を謀ったのも、皇権と共に民権を重んずる明治大帝の五事の御誓文に基づいて、自由民権論を高唱したのであった」と。すなわち尊王攘夷の帰結として、「内においては藩閥政治に反対し、外においては東洋の自由を主張した」闘いの実践がうち出されたのである。だからこそ西南の役勃発に際会し、「第二の維新を東北より起さん」とし、まず水戸に足を運んだ。何故水戸を第一に選んだか、明治維新の思想的根源である水戸学の発祥地であるからと、彼は説明している。もとより水戸では志をえず、転じて庄内に入った。蓋し庄内は幕末徳川氏に殉じて最後まで「義戦」した「純忠至誠の心」「尊王愛国の精神」を有した地、よって「東北諸藩を聯合し」薩長藩閥政府を打破せんというのが、彼の計画であったという。しかし庄内でも失意、三転土佐に赴き挙兵を勧説しようとし、そこで板垣に会い言論の闘いに翻意する。当時の自由民権論者の思想的遍歴を象徴するかのような行動であった。
杉田が民権派の壮士となる機縁をなしたものは、彼が『評論新聞』の記者となったことであるが、その『評論新聞』、さらに彼が編輯長となった『草莽事情』、これらと同系統の『采風新聞』『草莽雑誌』『莽草雑誌』『湖海新報』等──これらの新聞雑誌こそ、過激派民権壮士の拠点であり、それに掲載された論説は、士族的精神に支えられている最も封建的な、と同時にその故に最も戦闘的な自由民権思想の典型であった。
(中略)
…総じて自由民権派の議論には……依然として封建的な考え方──政治とは、あくまで私事を犠牲にしての、またそれを要求する資格ある国事に拘ることだと理解する──が支配的であった。この傾向は、後の改進党に連る穏健民権派よりも、自由党系の過激派に強かった。「一身の幸福は之を一国の幸福に比すれば、海洋の涓滴、山岳の土壌たるに過ぎず……身の禍福を顧ず一国の幸福を重んじ、死を以て国恩に報答するは国民の義務なり、嗚呼志士仁人は身を殺して仁を成す……死も亦愉快ならずや」(『草莽雑誌』)、「今の鎮西は古の関東の如く、士人の気象自ら勇往英邁にして私利私欲の為めに齷齪として俗事に奴隷たるの風に乏しき者の如し」(『草莽事情』)──自由民権の闘士は、「天下の安危を以て任ずる」国士であり、愛国者であった。彼らの理想とする愛国者の姿は「愛国の情は精魂に銘じ、正義を取り真理を踏み、上は皇上を奉戴し、下は良民を窮迫に救ひ、以て国権の失墜を恢復し、皇国をして万国に冠絶たらしめんと欲す」(同上)というにあった。だからそこで強調される自由とは、いうまでもなく第一には国家の対外的自主独立であり、国家の富強のための個人の自主自由・独立不羈であり、かかる報国の念を暢達すべき参政の自由であった。
(中略)
過激民権派のきわだった特色は、武力礼讃である。「我れ天性腕力を好む」(『草莽雑誌』)──あまりにも率直な表白。「真正の自由は鮮血死屍の萌芽にして坐上議論の萌芽にあらざるなり」(『評論新聞』)──アメリカ独立革命を見よと叫ぶ。廃刀令をもって民間から武器一切をとりあげ、軍隊警察をもって専制支配の暴力とした絶対主義政府の弾圧に対抗し、人民の独立を保つに頼みとしたものは、やはり武力であり、武器であった。
この武力主義は第一には戦争支持となり、征韓論に結合する。清国における一揆徒党鋒起の報を評して曰く、「壮図一世を蓋ひ、功名千古に垂るるは、豈男児平生の志にあらずや。我蜻蜒の洲は弾丸一孤島のみ。未だ以て英雄の奇才を試みるに足らず。今の亜細亜州中に在て蓋世の偉業を成さんと欲せば、支那を捨てて何ぞ。……吾人筆を投じ戎軒を事とするの機会は此時にあり」(『評論新聞』)。戦争は外に国家の発展を導くと共に、内に飛躍的進歩をもたらすと考える。「戦争は国家に大益あるの説」と題し、「戦争は実に国家の元気を盛んにし人智の開発を助け、一蹴して開明を握取すべきものなり」(『評論新聞』)と説く。但しこの「戦争」の中に対外戦争と並んで武力革命が包含されていたことは、フランス大革命の例証を引用していることからも明かである。戦争と革命とを同一視する、ここに問題があるが、革命忌むべからずとして政府権力と堂々と争わんとした気力の底には、必ずやかかる古き戦争利益論、腕力肯定主義が支えとなっていたと見るべきであろう。
武力主義の第二の結果は、当時続発した士族暴動の同情支持となり、その反面開化論者への反感となったことである。山口の乱における前原一誠を讃嘆して「前原氏亦俗吏を見る事土芥の如し、……威武の凛々たる目前に見るが如し」(『評論新聞』)という。その真意は、政府に反抗する前原への傾倒であり、それに反し開化論者がとかく政府の上からの啓蒙政策に結合する傾向あるに反撥するか、ないし革命的実践への怯堕にたいする不満を懐いたからであった。「生開化者流争て洋風を摸擬し……動もすればミルを説き、バックルを談じ、所論は極めて高上なれども、その心術を問へば、卑屈悒怯、政府を畏れ官吏に屈し、圧制政府の羈絆を甘受し、天与の自由を剥奪せられて、恬然自ら顧みざるなり」(『莽草雑誌』)。その極は奸臣を斬るは国家治安の本、開化先生福沢諭吉・加藤弘之の著書『学問のすすめ』『国体新論』が天皇陛下の奴隷というは、わが国体を紊乱し、決して治安の期なかるべしとまでいう(『評論新聞』)。
(中略)
「文明の世に蛮夷の気象を失ふべがらざる論」(『莽草雑誌』)は、その意味で注目すべき論旨を展開している。──往昔ゲルマンの蛮夷は、森々たる深林に住するや、自由の空気充塞し、独立の気象に薫陶す。しかれども人智漸く開け、人文漸く進み、ために天性固有の元気を放出し、独立不羈の志操は萎靡するに至る。わが国においても然り、封建の時、各藩の壮士はその蛮風固陋憫笑するに堪えたりと雖も、かの堂々たる大和魂の如きは、実に嘆美すべしと。かく論じ来って、江湖の諸士よ、自由独立の気風を振起するためには「従来の大和魂を失ふ勿れ」と叫ぶのである。
(中略)
疑いもなく彼ら草莽の志士の民権論の根柢には、維新以来の士族的倫理、士族的政治意識が牢固として存続していた。かかる民権論の本質は、絶対主義を一応下から、すなわち人民的立場から裏付けようとした点にあったのである。従って大久保・木戸・伊藤から江藤・板垣を分たしめたもの、さらに江藤・板垣から杉田・関等壮士を分たしめたものは、この下からの立場の徹底如何にあったといえよう。しかもこの「下から」の尺度が、それぞれの人の思想の内面的理解から必然的なものとして捉えることができずに、むしろ彼がその時々置かれた政治的社会的地位といった外的偶然的条件によって決定される傾きが強かった。だからといって、それぞれの大がその時その時に演じた進歩的ないし反動的役割のけじめは、いささかも曖昧ではない。絶対主義の下からの裏付けという場合でも、それが人民的立場に立つ限り、ある限界内ではあっても、上の強制にたいする下の自主の対抗であるし、対抗である限り、対抗の白熱的過程の中で、絶対主義の裏付けがその否定に転化するか、少くとも革命的思想の母胎となることはできるのである。
江藤・板垣は岩倉・大久保政権の反対派であっても、時来らば台閣に列しうる。そこにその民権論の裏はらの封建意識が、そうした政権への割り込みの橋渡しとして、民権主義を抑制し、ないし裏切る作用を専ら演じる。これに比して杉田・関的草莽志士は、個々人の運命は別として、全体的には藩閥政権参加の機会は年々失われ、すでに望み薄きものとなっている。己が首領板垣にたいしてさえ、その入閣には、我等を見捨てるのかと痛烈な皮肉を投げつけるまでに激している。野人として、いわば人民として絶対主義政府に対する時、その民権論の核心に横たわる士族精神は、一面では依然民権主義の内容上の革命性を制約する働きをなすと共に、他面では在野性の主体的精神となることによって、その民権主義の実践上の革命性を支持促進したのである。古き士族精神をもって、ともかくも一の新しき革命的エネルギーに転化せしめえたところに、「下流の民権説」ないしその分派のみが持つ栄誉ある特質が存したのであった。〉(『遠山茂樹著作集 第3巻 自由民権運動とその思想』岩波書店、1991年、46~52頁)
