国学派ネットワークの情報拠点・中津川
 明治維新に至る尊皇攘夷運動における国学の影響を考える上で、島崎藤村晩年の大作『夜明け前』は重要な資料となる。二部からなる同書は、ペリー来航の嘉永六(一八五三)年前後から明治十九(一八八六)年に至る激動の時代を、中山道の宿場町であった信州木曾谷の馬籠宿(現在の岐阜県中津川市馬篭)を舞台に、主人公青山半蔵の生涯を描いた作品である。半蔵のモデルとなったのが、藤村の父正樹だ。
明治維新に至る尊皇攘夷運動における国学の影響を考える上で、島崎藤村晩年の大作『夜明け前』は重要な資料となる。二部からなる同書は、ペリー来航の嘉永六(一八五三)年前後から明治十九(一八八六)年に至る激動の時代を、中山道の宿場町であった信州木曾谷の馬籠宿(現在の岐阜県中津川市馬篭)を舞台に、主人公青山半蔵の生涯を描いた作品である。半蔵のモデルとなったのが、藤村の父正樹だ。
馬籠で本陣・問屋・庄屋を代々の家業としてきた家に生まれ、その家業を継いだ半蔵は、平田派の国学に傾倒して王政復古を願った。しかし、明治維新は彼が描いたものとは別のものとなっていく。絶望した半蔵はついに狂い、座敷牢に生涯を終えた。
交通の要衝として物流・情報の拠点だった中津川は、平田国学においても重要な拠点となった。国立歴史民俗博物館館長の宮地正人氏は、次のように指摘している。
「東濃の一宿場町の平田派国学者グループが、全国的な政治情報を正確に把握する情報ネットワークを作りあげることができたのは、京都における平田門人の宿泊場所として、センター的役割を果たしていた生糸問屋の池村久兵衛と中津川国学者が、彼らの平田派入門以前から商売上深い関係にあったことが大きい。池村に集まる情報が全て中津川に届けられ、江戸の平田家にその情報が伝わっている」
そして、対外的な危機に促され、安政六(一八五九)年以降、中津川における平田派門人は急速に増加していった。
藤村の父正樹が平田篤胤没後の門人となったのは、文久三(一八六三)年、三十三歳の時だが、半蔵は安政三(一八五六)年、十九歳の時に入門したことになっている。
これについて、細川正義氏は「事実に立脚することの多い作品の展開において、この七年間の変更は注目される。そこには藤村の意図、即ち半蔵の思想と認識において平田国学の影響をより強いものとして設定していることが窺える」と書いている。
半蔵の篤胤への傾倒は次のように描かれる。
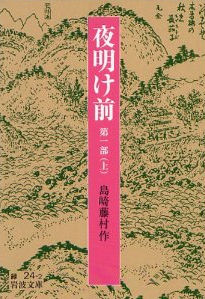 〈いつでも半蔵が心のさみしい折には、日頃慕っている平田篤胤の著書を取り出して見るのを癖のようにしていた。『霊の真柱』、『玉だすき』、それから講本の『古道大意』なぞは読んでも読んでも飽きるということを知らなかった〉(『夜明け前』岩波文庫、第一部第二章、八十九頁)
〈いつでも半蔵が心のさみしい折には、日頃慕っている平田篤胤の著書を取り出して見るのを癖のようにしていた。『霊の真柱』、『玉だすき』、それから講本の『古道大意』なぞは読んでも読んでも飽きるということを知らなかった〉(『夜明け前』岩波文庫、第一部第二章、八十九頁)
半蔵が篤胤没後の門人になろうと決意し、親しい学友の蜂谷香蔵宛に書いた手紙には次のように書かれていた。
〈君に悦んでもらいたいことがある。自分はこの旅で、かねての平田入門の志を果そうとしている。最近に自分は佐藤信淵の著書を手に入れて、あのすぐれた農学者が平田大人と同郷の人であることを知り、また、いかに大人の深い感化を受けた人であるかをも知った。本居、平田諸大人の国学ほど世に誤解されているものはない。古代の人に見るようなあの直ぐな心は、もう一度この世に求められないものか。どうかして自分らはあの出発点に帰りたい。そこからもう一度この世を見直したい〉(第一部第三章、百三十一、百三十二頁)
半蔵が「古代の人の直ぐな心」への回帰に重要な意義を見出していたことは、次の一節にも明確に示されている。半蔵に国学の手ほどきをした宮川寛斎について、次のように描かれている。
〈寛斎はまた平田派の国学者である。この彼が日頃先輩から教えらるることは、暗い中世の否定であった。中世以来学問道徳の権威としてこの国に臨んで来た漢学び風の因習からも、仏の道で教えるような物の見方からも離れよということであった。それらのものの深い影響を受けない古代の人の心に立ち帰って、もう一度心寛かにこの世を見直せということであった〉(第一部第二章、七十九頁)
中世の否定というテーマは、実際に父正樹が抱いていたものである。藤村は、昭和十六年に書いた『回顧』の中で、次のように書いているのである。
〈父等には中世の否定といふことがあつた。もとより中世期に於ける武家幕府の開設に伴ひ王権の陵夷は争ふべからざる事実であつて、尊王の念に厚い平田派の学者達が北条・足利二氏の専横を許しがたいものとしたのは当然のことであつた。日本民族の純粋な時代を儒仏の教の未だ渡来しない以前に置いた父等が、ひどく降つた世の姿として中世を考へるやうになつて行つたのも、これまた自然の帰結であつたらう」(細川正義「島崎藤村『夜明け前』論(上)」)
そして、半蔵が見つめていたものは、「新しき古」であった。
〈国学者としての大きな諸先輩が創造の偉業は、古ながらの古に帰れと教えたところにあるのではなくて、新しき古を発見したところにある。
そこまで辿って行って見ると、半蔵は新しき古を人智のますます進み行く「近つ代」に結びつけて考えることも出来た。この新しき古は、中世のような権力万能の殼を脱ぎ捨てることによってのみ得らるる。この世に王と民としかなかったような上つ代に帰って行って、もう一度あの出発点から出直すことによってのみ得らるる。この彼が辿り着いた解釈の仕方によれば、古代に帰ることは即ち自然に帰ることであり、自然に帰ることは即ち新しき古を発見することである。中世は捨てねばならぬ。近つ代は迎えねばならぬ。どうかして現代の生活を根から覆して、全く新規なものを始めたい〉(第二部第十一章、二百二十二頁)
青山半蔵が見た篤胤の「実行」と「必死」
「日本古来の精神への回帰」という国学派の主張が、尊皇攘夷に大きなエネルギーを与えたわけだが、志士たちを行動に駆り立てる上で、篤胤の生きざまこそが強い影響を与えていた。
そこで、浮かびあがるのが、篤胤の「実行」と「必死」である。国学に傾倒していく半蔵は、宣長と篤胤の思想を一体のものとして描いているが、次の一節に篤胤の「実行」と「必死」を明確に描き出している。
〈あの本居宣長の遺した教を祖述するばかりでなく、それを極端にまで持って行って、実行への道をあけたところに、日頃半蔵らが畏敬する平田篤胤の不屈な気魄がある。半蔵らに言わせると、鈴の屋の翁には何と言っても天明寛政年代の人の寛濶さかある。そこへ行くと、気吹の舎大人は狭い人かも知れないが、しかしその迫りに迫って行った追求心が彼らの時代の人の心に近い。そこが平田派の学問の世に誤解され易いところで、篤胤大人の上に及んだ幕府の迫害もはなはだしかった。…同時代を見渡したところ、平田篤胤に比ぶべきほどの必死な学者は半蔵らの眼に映って来なかった〉(第一部第五章、二百四十九頁)
そして、実際に平田派の思想が尊皇攘夷運動への参画を促していくことは、例えば尊皇攘夷の気運が盛り上がった文久三(一八六三)年当時の次のような描写に示されている。
〈平田篤胤歿後の門人は諸国を通じて千人近くに達するほどの勢いで、その中には古学の研究と宣伝のみに満足せず、自ら進んで討幕運動の渦中に身を投ずるものも少くなかった〉(第二部第八章、六十六、六十七頁)
いかにして、平田派の志士が討幕運動に身を投じたかを考える上で、不可欠なのが『霊能真柱』に示された篤胤の思想である。そこで展開された死後霊魂の行方と安心論こそ、志士の行動に意味づけを与えるものだったと考えられるからである。
