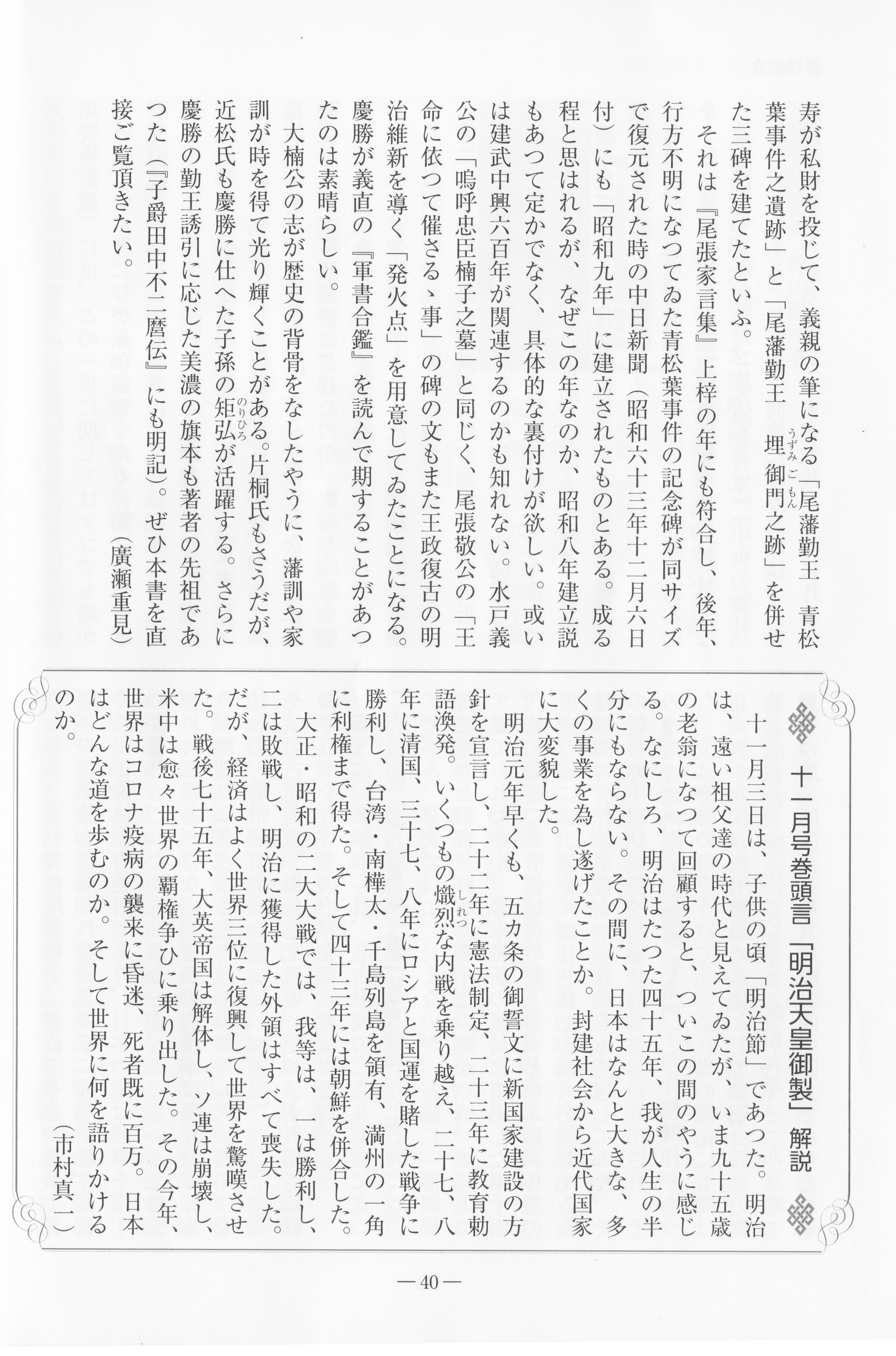今まであまり描かれなかった渋沢栄一の側面
今年の大河ドラマ「青天を衝け」で取り上げられた渋沢栄一。「日本資本主義の父」や「商工会議所の設立に関わった」など、カネ儲けについてはよく知られているが、養育院の存続や救護法(生活保護法)実施など、福祉面での渋沢はあまり知られていない。また、その考えを支えた水戸学(幕末に徳川慶喜に仕えていた)への思いもまた知られていない。
本書では渋沢を「水戸学で固めた男」とし、晩年の著作である『論語講義』などを紹介しながら、渋沢の思想を紐解いている。また、渋沢が幕末に仕えた最後の将軍である徳川慶喜についても、渋沢が関わった『徳川慶喜公伝』の刊行についても詳しく述べられている。明治期は謹慎していた徳川慶喜が渋沢という語り部を得たことは、後世の歴史家にとっても有意義であったと思う。
「拙著」カテゴリーアーカイブ
水戸学の入門書としても 『水戸学で固めた男・渋沢栄一』レビュー(さちひこ氏、令和3年10月20日)
水戸学の入門書としても
Youtubeで著者の動画を見て、購入しました。
2021年の大河ドラマによる「渋沢ブーム」の影響か、書店では渋沢栄一の『論語と算盤』の図解本や漫画本などをよく見かけるようになりましたが、渋沢の書いた原典、例えば『論語講義』や『青淵百話』にまで遡って手にとった人は、そう多くないのではないでしょうか。
本書の著者は、直接『論語講義』や渋沢の講演集などにあたり、彼の思想がいかに水戸学に基づいたものであるかを明らかにされています。と言っても、私は正直水戸学にはあまりなじみが無いのですが、
本書の中で関連書籍が色々と紹介されているので、この本を取っかかりに水戸学についても少し調べてみたいと思います。
B6版で120頁程の本ですが、内容はなかなか濃く、渋沢の思想と行動を、原点にまで遡って理解できるようになっています。
『論語と算盤』が書かれた背景を知りたい、という方にはぜひおすすめしたいです。
「青天を衝け」第6話のあのシーンの意味 『水戸学で固めた男・渋沢栄一』レビュー(タコライス氏、令和3年10月18日)
「青天を衝け」第6話のあのシーンの意味
3月21日に放送された「青天を衝け」第6話後半で、竹中直人演じる斉昭が慶喜と慶篤を相手に水戸藩の尊王論について厳かに語るシーンがとても印象に残っていました。本書を読んで、ようやくそのシーンの意味をよく理解することができました。慶喜は維新後に伊藤博文に次のように語ってたのですね。
「水戸は義公の時代から皇室を尊ぶということをすべての基準にしてまいりました。私の父、斉昭も同様の志を貫いておりまして、常々の教えも、……水戸家はどんな状況になっても、朝廷に対して弓を引くようなことはしてはいけない。これは光圀公以来の代々受け継がれて来た教えであるから、絶対におろそかにしたり、忘れてはいけないものである」(訳)
義公は「我が主君は天子也、今将軍は我が宗室也」(『桃源遺事』)との言葉を残し、やがて治紀(7代藩主)から斉昭に「何ほど将軍家理のある事なりとも、天子を敵と遊され候ては、不義の事なれば、我は将軍家に従ふことはあるまじ」(『武公遺事』)との言葉が残されました。
水戸学を学んでいた渋沢はこの義公の遺訓が慶喜にいたるまで脈々と継承されたことに感動したからこそ、大政奉還の真意を理解して慶喜の名誉回復のために『慶喜公伝』編纂に心血を注いだのだということがよくわかりました。それほど渋沢は義公の遺訓を大事だと考えていたのですね。改めて慶喜の尊王心についても勉強する必要があると感じました。
慶喜は大正2年に死去しましたが、追悼会で阪谷芳郎が述べた弔辞がまた感動的ですね。
「19歳の時に一橋家を相続されましたが、その時に父上の烈公より、其方はこの度一橋家を継がれるが、いかなる考えを持たれるかという簡単な問を発せられた時に、慶喜公は答えて、いかなる事があっても弓を朝廷に彎きませぬと申し上げた、問も簡単であるが答も簡単であった。しかして真にいかなる場合といえども弓を朝廷に彎かぬという心をもって、ついに徳川家三百年の忠節を全うせられて、めでたく王政維新となって、今日の開国進取の政策を立るの道を開くに至った」
生活保護法も渋沢が実現させた?!『水戸学で固めた男・渋沢栄一』レビュー(れんぢらう氏、令和3年10月18日)
生活保護法も渋沢が実現させた?!
渋沢栄一がアツイ。新しい一万円札の顔に決まった上、大河ドラマにもなったからだ。
正直歴史好きであっても、渋沢自身についてはさほどの関心はなかった。ああ、あの松下幸之助みたいにおエライ実業家が明治の頃からいたのね。…その程度の認識しかない。
ところが今回の大河では徳川慶喜が目立っている。草彅クン演じるところの最後の将軍。ほとんど主役を喰う勢いだ。もちろん慶喜はもう20年以上も昔に同じ大河でモックンが演じている。けれども最終回で大政奉還を描いたまでで、その後の人生については一筆書きで触れられた程度だ。
渋沢が主人公ともなれば、明治以降の慶喜も見られる。そんな調子で近年の大河では珍しく毎回逃さぬように観てきたわけだが、とうぜん烈公・斉昭や藤田東湖も登場。そうなれば、水戸びいきとしては半永久保存版として記録媒体に落とすしかない。
本書では、そんな渋沢栄一と水戸学との関わりがテーマ。そもそも水戸出身でも何でもない渋沢に、水戸学との接点はあったのか。いや接点なんていう生ぬるい話ではない。「水戸学で固めた男」ともなれば尋常ではない。
慶喜公の伝記を渋沢が編纂したことくらいは知っていた。肝腎の『昔夢会筆記』はツンドクだが、実業家・渋沢と水戸学というのは、とても結びつくものではない。だいいち埼玉の深谷出身とあれば、水戸藩とは一切関係ない。主君の慶喜から情報を得たのか。いや、それより遥か以前から、渋沢は「深谷の吉田松陰」と呼ばれる人物から尊攘思想を学んでいたのだ。
それがどんな人物であるか?それは本文に譲るとして、若き渋沢は、横浜で焼き討ち事件を謀るほどの筋金入りの尊攘派だったのだ。
そして、福祉事業家としての渋沢の姿。この時代の富裕層ともなれば、社会事業家として、慈善活動で名声を得ることはさほど珍しい話はない。しかし、当の渋沢にしてみれば、天皇陛下の〝大御心〟に応えたまでということになろう。
明治末期、日露戦後の弛緩した空気の緊縮を図って戊申詔書が発せられたが、その数年後に「施療済世の勅語」が出されたことは、それほど知られていない。長年の条約改正の宿願を果たした日本は、漸く医薬品を入手することすらできな困窮した国民に救いを手をさしのべようとしたのである。早くから養育院院長も務めた渋沢は、「済世勅語」を拝したことで、いっそう貧民救済事業にも奔走したのだ。大正期に火災に見舞われた知的障害児の教育施設・滝之川学園の再建に尽力したのも渋沢である。
91歳の病身を押してまで、生活困窮者の支援をめざした救護法成立をめざし、反対する政府関係者への説得にあたったのも最晩年の渋沢だった。
実は水戸学にも義公以来、藤田幽谷・東湖、会沢正志斎を経て、烈公に到るまで、「蒼生安寧」という愛民の思想が継承されていた。渋沢の「合本主義」の根柢に、こうした水戸藩の経世済民思想が流れていた―だとすれば「尊王攘夷」だけでは決して括れない水戸学の新たな一面にも光を当てたことになろう。
その他、本書では、頭山満や蓮沼門三らの愛国団体との意外な接点も掘り起こしている。
500もの企業の創設に関わったとされる渋沢だが、その後も日本では数多くの名経営者と呼ばれる事業家は登場している。しかしながら、今や多くの富裕層は私的な利益の追求が持てはやされ、まじめな経営者の方もおられるとは思うが、渋沢のいう合本主義とはほど遠い。
新政権の登場で、漸く政府も重い腰をあげて、構造改革以来長年わが国を拘束してきた新自由主義路線を見直し、「成長と分配」が掲げられるようになった。しかしながら、リーマンショック以上の経済危機に見舞われる今日、日本の格差社会は渋沢の生きた時代以上に加速化しているようにも見える。
今や「功利なき道義」と「道義なき功利」が蔓延。渋沢ブームの背後で、もはや合本主義という理念そのものが死語と化している。
本書を繙けば渋沢という人物が決して〝日本資本主義の父〟という見方では括れないことを知るだろう。
『水戸学で固めた男・渋沢栄一』書評(『通信文化新報』令和3年11月22日付)
『アジア英雄伝』前書き
一 アジアの黎明の時代
列強の植民地支配に対する民族的反抗
本書で取り上げた二五人のアジア人(金玉均、康有為、ボニファシオ、ダルマパーラ、リカルテ、孫文、李容九、ガンジー、オーロビンド・ゴーシュ、イクバール、ウ・オッタマ、クォン・デ、宋教仁、ビハリ・ボース、プラタップ、クルバンガリー、ベニグノ・ラモス、チャンドラ・ボース、ピブーンソンクラーム、スカルノ、ハッタ、アウン・サン、スハルト、マハティール、ノンチック)は、民族の独立と興亜に人生を捧げた志士たちである。その多くが命がけで民族独立闘争に挺身し、志半ばで倒れている。かつて栄華を誇ったアジアは、ヨーロッパ列強による植民地となり、その輝きを失っていた。アジア諸民族は、支配から脱して独立を勝ち取り、主体的な国づくりに向かわねばならなかった。
だが、列強の力は強大であり、幾度にもわたる反抗は空しくも抑えつけられていた。例えば、インドでは一八五七年から一八五九年に、セポイの乱と呼ばれる民族的反抗運動が試みられたが、結局鎮圧されている。また、一八八八年には、ジャワ島西端のバンテン地方で反オランダ農民反乱が起こったが、三〇日で鎮圧されている。
アジアが欧米の支配下に置かれ始めたのは、およそ五〇〇年前のことである。アジアへの進出で先んじたのは、スペインとポルトガルである。両国は、イベリア半島におけるイスラーム勢力に対する国土回復運動(レコンキスタ)を達成するや、大航海時代の先頭を切って、海外への進出を開始した。一四九四年には、ローマ教皇アレクサンドル六世がトルデシリャス条約を定め、大西洋上に西経四六度の子午線を引き、東をポルトガル、西をスペインの領土とした。一四九八年にヴァスコ・ダ・ガマがカリカットを訪れたのを契機に、ポルトガル海上帝国は沿岸部に拠点を築いていく。ポルトガルのインド総督アフォンソ・デ・アルブケルケは、一五一一年にマラッカを征服、東南アジアにおけるポルトガル海上帝国の拠点を築く。マレーシアのマハティール前首相は、この五〇〇年前の歴史を忘れてはいない。一方、スペイン艦隊は太平洋を横断し、東方からアジアに進出した。マゼランは、一五二一年にフィリピンに到達、徐々に勢力を広げ、一五七一年にはマニラ市を含む諸島の大部分を征服した。この間、スペインとポルトガルによる勢力は日本にも及んできたが、信長、秀吉らの努力によってそれを阻止している。
スペイン、ポルトガルに次いでアジアへ進出してきたのが、オランダである。オランダは、一六〇二年には東インド会社を設立、一六一九年にはバタビア(現ジャカルタ)に要塞を築き、首府とした。やがて一七世紀中ごろには、ポルトガルとイギリスの勢力を駆逐し、インドネシア全体を植民地とした。
では、イギリスの進出はどうだったのか。同国は、一八世紀半ばに南部インドの支配権をめぐってフランスと三次にわたって戦争し、最終的に勝利する。さらにインド土着軍を制圧し、インドにおける支配権を固める。一八二四年には、マレー半島を勢力下に収め、イギリス領海峡植民地が成立する。一八八六年には、ビルマがイギリス領インドに併合されている。さらに、イギリスは一八九八年に香港を獲得、清への勢力を拡大していった。この間、イギリスが清に持ち込んだ大量のアヘンによって、多くの中毒者が生み出された。
フランスは、一九世紀になって仏領インドシナなどの植民地化に成功した。
アメリカは、一八九八年の米西戦争でスペインに勝利すると、スペインの統治下にあったフィリピンを植民地化する。
また、シベリア制圧を終えたロシアは、進路は南へとり、中央アジアの多くの汗国を植民地化し、清の弱体化につけこみ満州のアムール川以北と沿海州を植民地化した。これが、欧米列強によるアジア植民地化の歴史である。アジア諸国は政治的独立を失うとともに、富を略奪されていたのである。
本書で取り上げた志士たちは、この状況を打開するために立ち上がったのである。
アジア諸国は、植民地化の過程で伝統文化を無残に破壊されていた。劣等感を植え付けられたアジア諸民族は、独自の文化への誇りを失い、人間中心主義、物質至上主義といった西洋近代の価値観を受容していった。こうして、自らの伝統文化、宗教の中の普遍性は忘却させられたのである。
植民地解放闘争の過程で再発見された伝統文化、宗教は、西洋近代文明を超克し得る文明的な意味を持っていた。やがて、第一次世界大戦が勃発すると、欧米の内側から、近代文明に対する懐疑的な見方が唱えられるようになる。シュペングラーの『西洋の没落』もその一つである。
本書で取り上げたアジアの志士たちの多くも、伝統文化と宗教の価値を普遍的なものとして信奉し、近代西洋文明を乗り越えようという志を持っていたのである。例えば、マハトマ・ガンジーは、「近代文明に対する厳しい弾劾の書」と評される『ヒンドゥー・スワラージ』において、「私たちの祖先は、機械のつくりかたを知らなかったわけではない。ただそんなものを欲したら徳性を失うだろうということも知っていた。だから熟考したうえで、できる限りのことを、手と足で行うべきであると決めた」と書いている。パキスタンのムハンマド・イクバールは、独自のイスラーム思想に基づいて、鋭い近代批判を展開した。セイロンのアナガーリカ・ダルマパーラは、「今世紀は一転して眠れる亜細亜を覚醒せざるべからず。而して欧州一流の文明よりも更に完全なる世界的文明を作らざるべからず」と語っていた。インドのビハリ・ボースは、西洋近代の物質偏重を是正し、東洋の伝統思想の復興による文明転換を目指していた。ベトナムのクォン・デもまた、近代主義に批判的なカオダイ教との連携を模索した。
後述するように、普遍的価値に基づいたアジア文明の復興というビジョンは、多くの場合、それぞれの民族思想とともに、宗教思想に裏付けられていたのである。
独立の維持を果たしたという点において、明治以来の近代化に一定の評価を与えつつも、文明転換の視点を失わなかった日本の興亜陣営と、本書で取り上げたアジアの志士たちとは、文明史的課題をも共有していたのである。
やがて、大東亜共栄圏構想が盛んに語られるに至って、西洋近代に対する批判論も、ある種の総括のときを迎える。戦時期に展開された「近代の超克」論がそれだ。昭和一七(一九四二)年七月には、小林秀雄、西谷啓治、亀井勝一郎、諸井三郎、林房雄、鈴木成高、三好達治、菊池正士、津村秀夫、下村寅太郎、中村光夫、吉満義彦、河上徹太郎らが参加して「近代の超克」の座談会が開かれた。これらの参加者は、京都学派の哲学者、日本浪漫派の文学者、『文学界』同人の三グループからなる。京都学派の高坂正顕、高山岩男、鈴木成高、西谷啓治は、ほぼ同時期の『中央公論』においても、座談会「世界史的立場と日本」を行っている。
ただし、後述する通り、列強の勢力に抗して、独立維持のために富国強兵を急いだ明治以降において、西洋近代に背を向けることは困難であった。だからこそ、竹内好は「『近代の超克』は、いわば日本近代史のアポリア(難関)の凝縮であった。復古と維新、尊王と攘夷、鎖国と開国、国粋と文明開化、東洋と西洋という伝統の基本軸における対抗関係が、……一挙に問題として爆発したのが「近代の超克」論議であった」と指摘したのである。
近代の超克という課題は、すでに解決済なのだろうか。地球環境問題の深刻化、精神的な価値の喪失感が進む中で、いよいよ大きな課題として、人類全体に突きつけられているといっても良い。
では、植民地解放という課題はどうなのか。形の上では、アジア諸国は一応は独立を果たした。しかし、中国では、チベット、内モンゴル(内蒙古自治区)、東トルキスタン(新疆ウイグル自治区)などで、民族固有の文化、宗教が制約されているとの見方もある。
その一方で、アメリカが主導するグローバリズムを新しい形の植民地主義ととらえる見方もある。一九九七年のアジア通貨危機によって、タイ、インドネシア、韓国が相次いで国際通貨基金(IMF)の金融支援を仰ぐことになった。この際、各国の主体的な経済運営が否定されたことから、マハティール首相は、新植民地主義だと激しく批判している。 続きを読む 『アジア英雄伝』前書き
徳川慶喜が伊藤博文に明かした水戸藩の遺訓継承
令和2年8月に『日本』(日本学協会発行)編集長の安見隆雄先生から、「水戸学と尾張学」というテーマで執筆する機会を頂戴いたしました。拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』を上梓したのをきっかけです。ところが、同年11月拙稿提出後、年が明けて安見先生が急逝したことを知りました。非常に大きなショックを受けるとともに、残念でなりません。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。
私が安見先生のご依頼に応え「知られざる尊皇思想継承の連携─尾張藩と水戸藩」と題して書かせていただいた原稿の結論は、尾張・水戸両藩における尊皇思想継承が一本の線でつながっているように見えるというものです。
尾張藩初代藩主・義直の遺訓「王命に依って催さるる事」の継承と、義公以来の尊皇思想の継承とが連動していたのではないかとの仮説です。一つだけ例を挙げれば、水戸においては、義公の遺訓は第6代藩主・治保(文公)に継承され、さらに文公から第7代藩主・治紀(武公)に継承されましたが、『武公遺事』には「我等は将軍家いかほど御尤の事にても、天子に御向ひ弓をひかせられなば、少(いささか)も将軍家にしたがひたてまつる事はせぬ心得なり」と書かれています。
この表現から直ちに想起されるのが、尾張藩における「王命に依って催さるる事」の継承です。尾張藩第4代藩主・吉通に仕えた近松茂矩が著した『円覚院様御伝十五ヶ条』には、「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」と書かれています。
この表現の一致にとどまらず、水戸と尾張が尊皇思想の継承・展開で協力していたことを窺わせる事実もあります。
さて、水戸藩における義公の遺訓継承を調べていた際に出会ったのが、渋沢栄一の『徳川慶喜公伝』です。渋沢が、かつて仕えた慶喜(江戸幕府最後の将軍)の伝記編纂を志したのは、明治26(1893)年頃とされています。明治維新に際して、慶喜がどのような考えで動いたのか、その真意を正しく後世に伝えたいという、熱い思いによるものでした。渋沢は、四半世紀もの歳月を費やして、ついに大正7(1918)年、『徳川慶喜公伝』全8巻を刊行しました。その第4巻には、義公の尊皇思想継承を伝える重大な記述があるのです。

〈明治34年の頃、私、渋沢栄一が大磯から帰る汽車の中で、伊藤博文公爵と出会ったとき、伊藤公爵が次のような話をされました。
「渋沢さんはいつも徳川慶喜公を誉めたたえておられますが、私は立派な大名の一人くらいに思っておりましたが、今はじめて慶喜公という方は普通の人でない非常に優れた立派な方であると言うことを知りました」
伊藤公は、なかなか人を信用し認めない方であるのに、いまこのように話されるのは、と疑問に思ったので、「なぜですか?」とたずねました所、「一昨夜、有栖川宮家で、スペインの王族の方を迎えて晩餐会があり、慶喜公も私も相客に招かれ、宴会が終わってお客が帰られた後、私は慶喜公に『維新のはじめに貴方が尊王というものを大事に考えられたのは、どのような動機からですか?』とたずねたところ、慶喜公は迷惑そうに『自分はただ昔からの家の教えを守ったに過ぎません。ご承知のように水戸は義公の時代から皇室を尊ぶということをすべての基準にしてまいりました。私の父、斉昭も同様の志しを貫いておりまして、常々の教えも、我らは三家(水戸藩・尾張藩・紀伊藩)三卿(田安家・一橋家・清水家)の一つとして、幕府をお助けすることは勿論でありますが、これから後、朝廷と徳川本家との間で争いが起きて、戦争でもするような大変なことにもならないとも限らないが、そのような場合には、水戸家はどんな状況になっても、朝廷に対して弓を引くようなことはしてはいけない。これは光圀公以来の代々受け継がれて来た教えであるから、絶対におろそかにしたり、忘れてはいけないものである。もしもの時のためにお前に言っておく。と教えられてきました。しかし、幼いときは、それほど大事な事とは考えていませんでしたが、二十に成り、(安政4年・1857)小石川の水戸家の屋敷に参りましたとき、父、斉昭は姿勢を正して、現在は黒船が来たりして大変な時代に成っている。この後、世の中はどのように変わって行くか分からない、お前も20歳になったのであるから、先祖から代々教え継がれて来た水戸家の家訓を忘れるではないぞ。と言われました。この言葉がいつも心に刻まれていましたので、ただそれに従ったまででございます』と慶喜公は答えられました。
本当に奥ゆかしい答えではありませんか。慶喜公は本当に偉大な方です。と伊藤公が言われました。私は後に慶喜公にお会いした時に、このことを尋ねましたら、「そのような事があったなあ」とおっしゃいました〉(常磐神社社務所HP現代語訳)
水戸では、この慶喜の発言を、水戸学の本義に関する重大事として重視し、慶喜に至る水戸藩における遺訓継承が探求されてきました。例えば、名越時正先生は昭和62年10月に『水戸史学』に書いた「徳川慶喜の大政奉還と義公の遺訓」(『水戸学の達成と展開』所収)で詳述しています。
水戸藩と尾張藩でともに継承された遺訓「仮にも朝廷に向うて弓を引く事ある可からず」が、明治維新成就においていかに重要な役割を果たしのたかを、改めて考えるべきだと思います。渋沢と水戸学との関係については、別の機会に書きたいと思います。
『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』書評(『有鄰』第98号、令和2年12月15日発行)
『敗戦復興の千年史』の著者で、『維新と興亜』にもご協力いただいている山本直人氏が、『有鄰』第98号(令和2年12月15日発行、東海有鄰会編集・発行)で、7ページに及ぶ拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』の紹介文を書いてくださいました。心より感謝申し上げます。
また同誌には、元愛知県立高校教諭の廣瀬重見先生の「尾張の藩訓をめぐる考察(五編)」も掲載されています。そこでも拙著について過分の紹介を賜りました。非力を顧みず尾張藩尊皇思想の継承というテーマに挑んだ甲斐があったと感じております。
拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』執筆に当たっては、廣瀬先生のほか、平泉澄先生の高弟・名越時正先生、水戸史学会理事の梶山孝夫先生、田辺裕先生の先駆的研究を活用させていただきましたが、今回廣瀬先生の論稿から、尾張藩初代藩主・義直公廟所のある定光寺の思い出を大切にされていた稲川誠一先生の事、「水戸学の偉大さは解るが、なぜ尾張の学問を尾張学と言はないのか」が口癖だった富田義孝先生の事などを知り、この分野の研究の蓄積の尊さを改めて感じました。
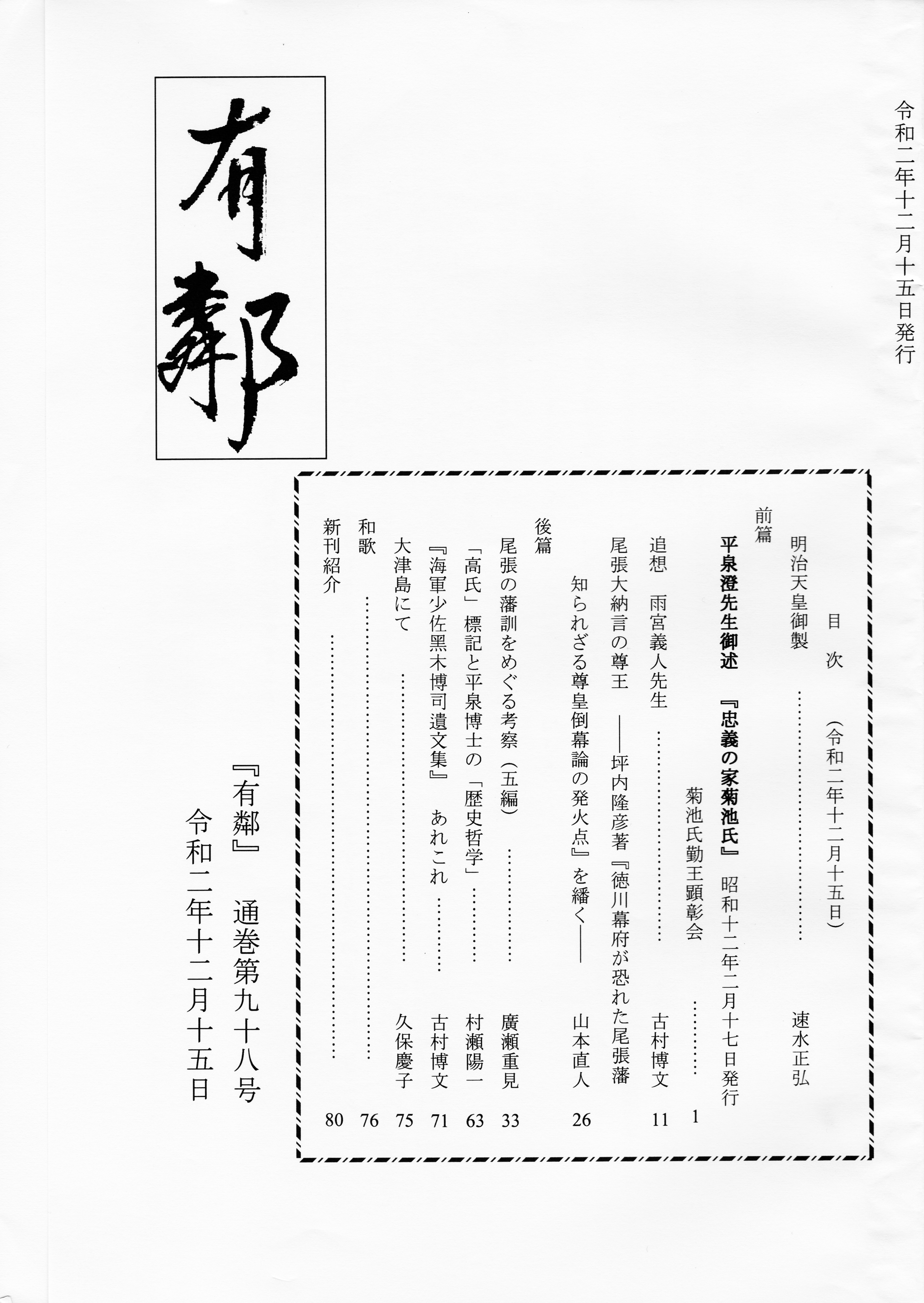
『徳川幕府が恐れた尾張藩─知られざる尊皇倒幕論の発火点』書評(『国体文化』令和2年12月号)
皇學館大学教授の松本丘先生に、『国体文化』12月号で拙著『徳川幕府が恐れた尾張藩』をご紹介いただきました。各章ごとに丁寧な紹介をしていただいた上、次のようにお書きいただきました。
〈本書は、尾張藩における勤皇思想を支へてゐたのは、崎門学・垂加神道を始め、国学・君山学派などの学問思想であり、「王命に依って催さるる事」といふ尊い精神は、「魂のリレー」によつて力強く継承されたと著者は述べる。これまで、同じ御三家において醸成された水戸学が、尊皇攘夷思想の発信源であつたことは語り尽くされてきたが、本書によつて、尾張学も大きな役割を果たしてゐたことが明らかになつた。
そして著者は、明治維新を薩長による権力奪取とする歴史観が近年横行してゐることに対しても、「尊皇排覇の思想は突然幕末になつて生まれたわけではない。江戸初期から思想家たちが命がけで築いた学問の発展と継承の上に、幕末の尊攘思想は花開いた。こうした精神的、思想的連続性を視野に置いた明治維新史を取り戻すべきではないのか。」と慨嘆されてゐるが、今後も著者によつて、維新に至る真の思想史が描き出されてゆくことを期待したい。〉
身の引き締まる思いです。誠に有難うございました。