「日本人としてもっとも銘記すべき悲劇の英雄であり、日本人が花束をささげて、永遠にその友情を忘れてはならない人物だと信ずる」
一九七一年に葦津珍彦先生は、フィリピンの志士ベニグノ・ラモスについてこのように書いた(『新勢力』)。
ラモスの人生を大きく変える事件は、一九三〇年に起こった。マニラ・ノース・ハイスクールに勤めていた、あるアメリカ人女性教師が、フィリピン人は「バナナ食いの猿のようなものだ」と侮蔑的発言をしたことが発端だ。この発言をきっかけに、市内のいくつかの高校の生徒が一斉に同盟休校し、世論が沸き立った(『アキノ家三代 下巻』)。
当時、フィリピンはアメリカの植民地だった。ラモスは、沈静化を図ろうとするマニュエル・ケソン上院議員に楯突き、官界を自ら去り、対米独立闘争の先頭に立つことを決意した。彼はフィリピン人エリート層がアメリカの権力に阿り、フィリピン民衆の利益を擁護できていないと主張、対米要求に弱腰のケソン指導部を攻撃し、即時、絶対、完全独立を要求した。また、農民の貧困問題の解決を訴えた。
彼は、一九三〇年七月、マニラのスラム街トンドで週刊新聞『サクダル』(「告発」の意)を発刊し、自らの主張を前面に出していく。民族主義を基調とするその論調は大きな反響を呼び、『サクダル』は飛ぶように売れた。最高発行部数は、七万五〇〇〇部に達したとされている(前掲書)。
ラモスは、アメリカとその代弁者たちの圧力に抗し、一九三四年にはサクダリスタ党を旗上げ、フィリピンの即時、絶対、完全独立を要求した。当時通訳としてラモスと行動をともにしていた原忠明は、「フィリピン人がアメリカの飼犬のような生活をしている間は、絶対に一人前になれない。フィリピン人は東洋人の支援によってはじめて独立出来るのだ」というのが、ラモスの口癖だったと振り返っている(『大阪毎日新聞』一九四二年四月一五日付)。
ラモスは、一八九三年二月一〇日、中部ルソンのブラカン州ブラカン町のタリプティップで生まれた。父カタリノ・ラモスは、スペイン支配に抵抗する秘密結社カティプーナンの一員として対スペイン独立戦争に参加した経歴を持つ。ラモスは、ブラカン州マロロスの高校を卒業、州庁で働いた後、同州で小学校の教師をしていた。その後、マニラに出て上院事務局に就職、やがてタガログ語詩人として知られるようになり、演説の力も認められるようになった。こうして、ケソンとともに遊説して回るようになったのである。
ラモスが民族の誇りに目覚めなければ、ケソンの右腕としてアメリカ支配下のフィリピンに安住することになったかもしれない。
一九三四年一一月、ラモスはついに日本に亡命する。ところが、横浜入港の際に、ラモスは日本官憲に逮捕されてしまった。結局、ラモスは救出されたが、このとき動いたのが頭山満だと見られている。
ところが、アメリカに配慮する外務省親米派は、ラモスと日本との関わりを否定するのにやっきになっていた。外務省情報部長の天羽英二は、記者会見でフィリピンの新政府発足を祝い、「日本政府は正統なフィリピン政府に対して叛乱を企てているいかなる外国人も支援していない」と述べ、日本がラモスを認めていないという立場を示した。
これに対し、ラモスは記者会見を開き、日本人の支援を求めるとともに、自分を祖国へ強制送還しないよう訴えている。このとき、葦津珍彦は、「比律賓独立戦争と我徒の態度─独立派志士を米国官憲に渡すな」と題した声明文(「太平洋同人」として作成)を広田外相に渡し、「国外退去させぬ」という確約を得ている。葦津は、ラモスと直接接触して、フィリピン独立運動に強い関心を示していたのである。
だが、アメリカとケソン政権に阿る日本政府は、ラモス一派に対する監視を強めた。事実、ラモスの秘書二人は、旅行先の神戸で一時逮捕されている(「民族主義思潮」)。
このとき、ラモスをマークしていた警視庁外事課長に実情を説明し、彼を守ろうとしたのが、海軍大佐の犬塚惟重であった。「サクダルのラモス」をもじって桜田茂助という表札を自宅に掲げて、身を隠させた。追放の圧力からラモスを守っていたのは、興亜陣営である。

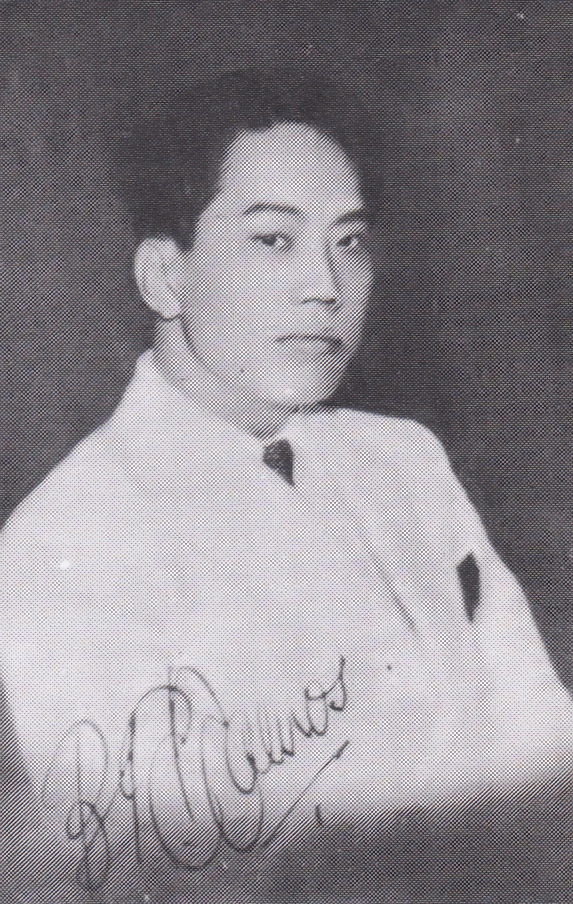
鈴木静夫の「民族主義思潮」には、ラモスの家族は芝三田南寺町(現三田四丁目)の願海寺の境内に住んでいたと書かれていた。筆者がそれを手がかりに、願海寺を訪れ、住職の森部義範氏に確認したところ、七〇年以上前にラモスの家族が住んでいた洋館風の住居は、ほぼそのままの状態で残されていることがわかった。アメリカに阿り、自分たちを厳しい監視下に置く日本当局への失望感と、対米闘争を支持する興亜陣営に対する期待感との間を揺れ動きながら、彼は四年に及ぶ日本での亡命生活を送ったのである。
ラモスは、一九三六年、維新寮(後の大東塾)を訪れ、影山正治、毛呂清輝、中村武彦らとも面会している。一九三七年一〇月には、日比谷公会堂における東洋民族大会で、フィリピン代表として、日本人に援助を懇願すべく、熱弁をふるった。
フィリピン帰国後の一九三九年一二月、ラモスはマニラのビリビッドに投獄されたが、日米開戦によって救出される。ラモスのサクダルの後継ガナップ党員たちは、日本軍に協力する姿勢を示していたにもかかわらず、日本軍はガナップ党との連帯に躊躇した。アメリカの妨害工作が効いていたと推測される。
こうした妨害を撥ね退けてラモス一派との協力に踏み切ったのは、山下奉文大将だった。一九四四年に入り、山下大将は、「比島人の大部分が日本軍に協力しない時、このような人間を重用することに、決して遠慮などすべきでない」と述べ、同年一二月八日、ガナップ党の傭員はマカピリ(フィリピン愛国同志会)として正式に編成された。だが、この決断は遅きに失した。その直後、山下兵団はバギオへの撤退を余儀なくされたのである。ラモスは山下兵団とともに後退する途中、一九四五年五月七日以降にヌエバ・ビスカヤ州内で死亡したとされている。
日本に協力したラモス一派は、アメリカによって皆殺しにされた。マカピリ構成員の家族は、中部ルソン一円でアメリカ極東軍系ゲリラの大虐殺の嵐にさらされた。見つけ出されたマカピリ構成員者は、中部ルソンのいくつかの町の広場で報復の処刑を受けた。山を下りたマカピリ構成員は、「人民法廷」でほぼ全員が無期刑を受けた。一〇年以上の服役の後、減刑されて釈放されたが、釈放後に多くの者が殺された。官公庁への就職は阻まれ、貧困のため子弟教育にもこと欠いたという。
対米自立を目指したラモスの悲劇は、いまなお続いている。
*ベニグノ・ラモスの評伝は『アジア英雄伝』に収録。
