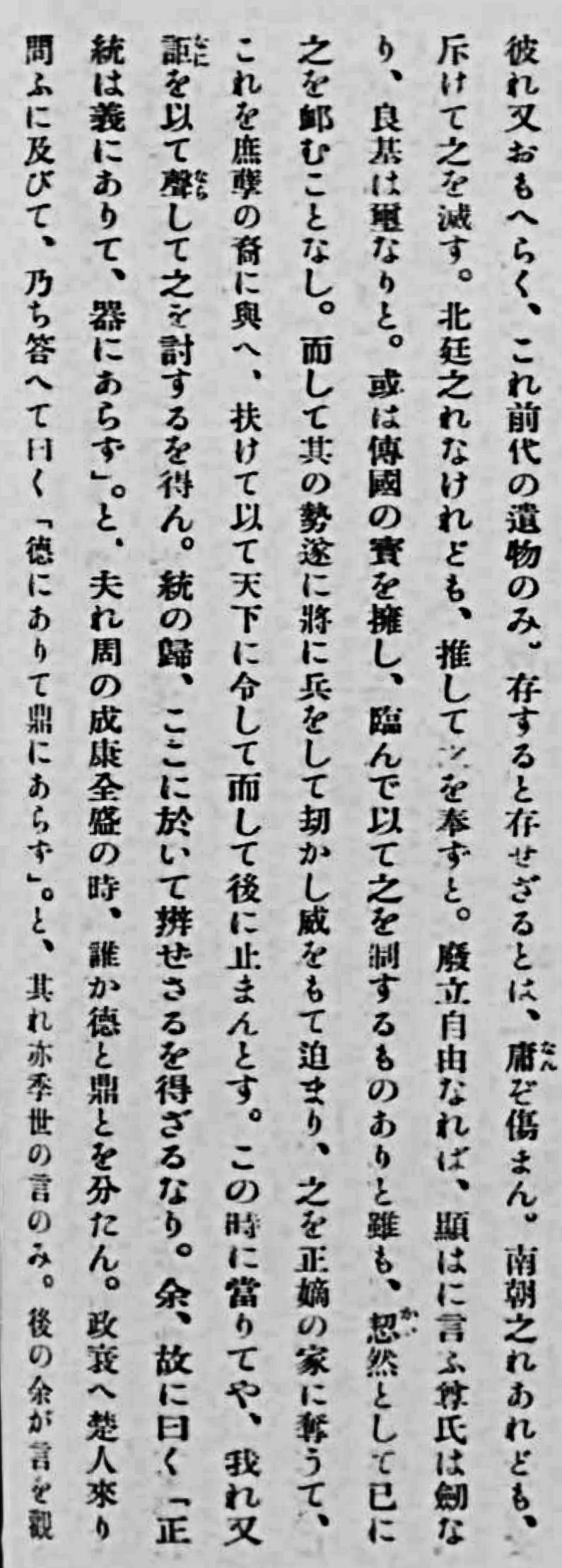 三宅緝明(観瀾)は、延宝2(1674)年に京都の町人儒者三宅道悦の子として生まれた。崎門学正統派の浅見絅斎に師事し、元禄11(1698)年に江戸に下り、翌年栗山潜鋒の推薦で水戸藩に仕えるようになった。彰考館編修となり『大日本史』編纂に従事した。
三宅緝明(観瀾)は、延宝2(1674)年に京都の町人儒者三宅道悦の子として生まれた。崎門学正統派の浅見絅斎に師事し、元禄11(1698)年に江戸に下り、翌年栗山潜鋒の推薦で水戸藩に仕えるようになった。彰考館編修となり『大日本史』編纂に従事した。
観瀾が後醍醐天皇の政治の得失を論じたのが『中興鑑言』である。ここで観瀾は、足利を批判し、吉野を正統の天子とした。その点では潜鋒と同じだったが、正統とする理由において、潜鋒とは異なっていた。潜鋒が「躬に三器を擁するを以て正と為すべし」としたのに対して、観瀾は『中興鑑言』において、「余、故に曰く、正統は義にあり、器にあらず」と書いているのだ。観瀾の考え方は、安積澹泊ら彰考館の他の同僚にも共有されていた。
これに対して、近藤啓吾先生は次のように指摘されている。
「思うに土地といひ家屋といひ、その所有を主張するものが複数であって互ひに所有の権利を争ふ時には、その土地や家屋の権利書を所持してゐるものを正しい所有者と判断せざるを得ない。されば人はみな権利書を大事にして失はぬやう盗まれぬやう、だまし取られぬやう、その保管に心を用ひるのである。神器もその性格、ある意味では権利書に似てをり、皇統分立していづれが正しい天子であるか知りがたく、人々帰趨に苦しむ時は、神器を有してをられる御方を真天子としてこの御方に忠節を尽くさねばならない。いはんや神器は権利書と異なり、その由緒からいへば大神が天孫に皇位の御印として賜与せられし神宝であり、大神の神霊の宿らるるところとして歴代天皇が奉守継承して来られた宝器であり、極言すれば、天祖・神器・今上の三者は一体にして、神器を奉持せられるところ、そこに天祖がましますのである」(「三種神器説の展開―後継者栗山潜鋒」)
「崎門学」カテゴリーアーカイブ
『崎門学報』第4号刊行
 待望の『崎門学報』第4号が平成27年7月31日に刊行された。
待望の『崎門学報』第4号が平成27年7月31日に刊行された。
堅い内容ながら、日本を救う鍵がここにあると筆者は信じている。
10カ月前の平成25年10月1日に創刊された同誌は、崎門学研究会(代表:折本龍則氏)が刊行する会報である。創刊号では、発行の趣旨について、折本氏が「いまなぜ崎門学なのか」と題して書いている。
まず、山崎闇斎を祖とする崎門学の特徴を、「飽くまで皇室中心主義の立場から朱子学的な大義名分論によって『君臣の分』と『内外の別』を厳格に正す点」にあり、「主として在野において育まれ、だからこそ時の権力への阿諛追従を一切許さぬ厳格な行動倫理を保ちえた」と説いている。
さらに、肇国の理想、武家政権による権力の壟断の歴史から明治維新に至る流れに触れた上で、戦後日本の醜態を具体的に指摘し次のように述べている。
「我が国は、今も占領遺制に呪縛せられ、君臣内外の分別を閉却した結果、緩慢なる国家衰退の一途を辿っているのであります。
そこで小生は、この国家の衰運を挽回する思想的糸口を上述した君臣内外の分別を高唱する崎門学に求め……闇斎の高弟である浅見絅斎の『靖献遺言』を読了し、更にはその感動の昂揚を禁ずること能わず、今日における崎門正統の近藤啓吾先生に師事してその薫陶を得たのでありました。最近では同じく崎門学の重要文献である栗林潜鋒の『保建大記』を有志と輪読しております」
続きを読む 『崎門学報』第4号刊行
若林強斎『雑話筆記』輪読(平成27年1月29日)
平成27年1月29日(木)、崎門学研究会で若林強斎先生の『雑話筆記』(近藤啓吾先生校注の『神道大系 論説編 13 垂加神道 下』収録)81~91頁まで輪読。ついに読了。
山崎闇斎、浅見絅斎の経歴、崎門の学風を象徴する清貧の中の困学、若林強斎の号に込められた思いなど、重要箇所が立て続けに登場。
若林強斎『雑話筆記』輪読(平成27年1月25日)
平成27年1月25日(日)、崎門学研究会で若林強斎先生の『雑話筆記』73~80頁まで輪読(近藤啓吾先生校注の『神道大系 論説編 13 垂加神道 下』収録)。
今日は、有名な一節「自分ガ学問ト云ヘバ、嘉右衛門殿ノ落穂ヲヒラフテ、其説ヲ取失ハヌヤウニスルヨリ上ノコトハナシ」の部分を読めた。「嘉右衛門」とは山崎闇斎のこと。かつて闇斎の高弟浅見絅斎は神道に沈潜する晩年の闇斎についていけなかった。やがて闇斎が病床に伏すようになっても見舞おうとせず、葬儀にも列することがなかった。後に、絅斎は闇斎に対する態度を深く悔い、香をたいて師の霊に謝した。闇斎の偉大さを改めて認識し、その精神の継承を決意するに至った絅斎の言葉が、「自分ガ学問ト云ヘバ、嘉右衛門殿ノ落穂ヲヒラフテ、其説ヲ取失ハヌヤウニスルヨリ上ノコトハナシ」にほかならない。
西郷南洲と大塩平八郎─三島由紀夫「革命の哲学としての陽明学」
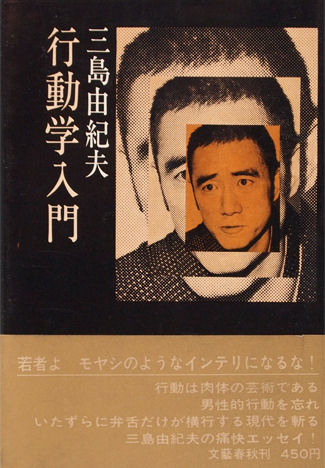
西郷南洲の思想と行動は、禅、陽明学、崎門学など多様な思想によって培われたとされている。こうした中で、南洲に陽明学の流れを見出そうとしたのが、三島由紀夫であった。
三島は、昭和45年9月の『諸君!』に発表した「革命の哲学としての陽明学」(同年10月刊『行動学入門』に収録)で、次のように指摘している。
〈西郷には「南洲遺訓」といふもう一つの著書があるが、ここにも陽明学の遠い思想的な影響は随所に見られる。たとへば「遺訓」の追加の部分の「事に当り、思慮の乏しきを憂ふることなかれ」といふ一行や、岸良眞二郎との問答の中の「猶豫狐疑は第一毒病にて害をなすこと甚だ多し」「猶豫は義心の不足より発するものなり」と言つてゐるところ、また「大丈夫僥倖を頼むべからず、大事に臨んでは是非機会は引起さずんばあるべからず、英雄のなしたる事を見るべし、設け起したる機会は、跡より見る時は僥倖のやうに見ゆ、気を付くべき所なり」などといふところがさうである。また「遺訓」の問答の「三」では「知と能とは天然固有のものなれば『無智の智は慮らずして知り、無能の能は学ばずして能くす』と。これ何物ぞや、それただ心の所為にあらずや、心明らかなれば知もまた明らかなるところに発すべし」といつてゐるが、その中の引用は王陽明の語そのままでさへある。しかしながら、西郷隆盛の言葉のうちでもつとも大塩平八郎と深い因縁を結んでゐるやうに思はれるのは、次の箇所である。
聖賢に成らんと欲する志無く、古人の事跡を見、迚(とて)も企て及ばぬと云ふ様なる心ならば、戦に臨みて逃るより猶ほ卑怯なり。朱子も自刄を見て逃る者はどうもならぬと云はれたり。誠意を以て聖賢の書を読み、其の処分せられたる心を身に体し心に験する修行致さず、唯个様の言个様の事と云ふのみを知りたるとも、何の詮無きもの也。予今日人の論を聞くに、何程尤もに論する共、処分に心行き渡らず、唯口舌の上のみならば、少しも感ずる心之れ無し。真に其の処分有る人を見れば、実に感じ入る也。聖賢の書を空く読むのみならば、譬へば人の剣術を傍観するも同じにて、少しも自分に得心出来ず。自分に得心出来ずば、万一立ち合へと申されし時逃るより外有る間敷也。(西郷南洲遺訓ノ三六)
この文章などは、われわれの中で一人の人間の理想像が組み立てられるときに、その理想像に同一化できるかできないかといふところに能力の有無を見てゐる点で、あたかも大塩平八郎の行動を想起させるのである〉
崎門の真価─平泉澄先生『明治の源流』「望楠軒」
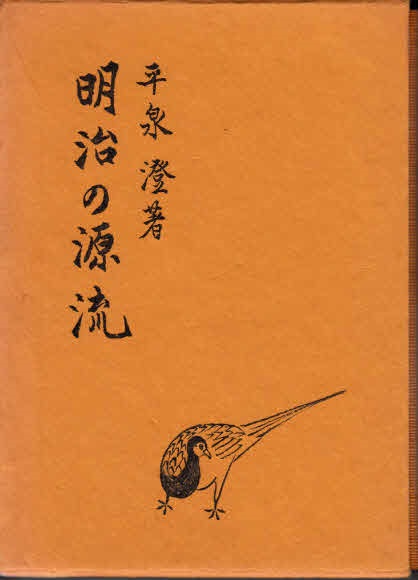 崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。
崎門学が明治維新の原動力の一つであったことを良く示す文章が、平泉澄先生の『明治の源流』(時事通信社、昭和45年)に収められた「望楠軒」の一節である。
〈ここに殆んど不思議と思はれるのは、水戸の大日本史編修と時を同じうして、山崎闇斎が倭鑑の撰述に着手した事である。一つは江戸であり、今一つは京都である。一つは水戸藩の総力をあげての事業であり、今一つは学者個人の努力である。大小軽重の差はあるが、その目ざす所は一つであり、そして国史上最も困難なる南北の紛乱を、大義を以て裁断した点も同趣同様であった。但し問題は、処士一個の事業としては、あまりに大きかった。闇斎は、明暦三年の正月より筆を執り、そして少くとも二十数年間、鋭意努力したに拘らず、完成に至らずして天和二年(西暦一六八二年)九月、六十六歳を以て歿し、倭鑑の草稿もまた散逸してしまった。只その目録のみ、門人植田玄節によって伝へられた。それによれば、後醍醐天皇を本紀に立て、光厳、光明紀を之に附載し、後村上天皇を本紀に立て、光明、崇光、後光厳、後円融、後小松紀を之に附録し、そして明徳二年十月二日、三種神器入洛の事を特筆大書したといふ。して見れば是れは、水戸の大日本史と同じ見識であったとしなければならぬ。 続きを読む 崎門の真価─平泉澄先生『明治の源流』「望楠軒」
若林強斎『雑話筆記』輪読(平成27年1月12日)
平成27年1月12日、崎門学研究会で若林強斎先生の『雑話筆記』67~72頁まで輪読(近藤啓吾先生校注の『神道大系 論説編 13 垂加神道 下』収録)。
引き続き、陰陽五行、易のこと。「山崎先生ノ、易ハ唐土ノ神代巻、神代巻ハ日本ノ易ジヤト仰ラレタガ、格言ニテ候」(72頁)
●元亨利貞(げんこうりてい)
易経で乾(けん)の卦(け)を説明する語。「元」を万物の始、善の長、「亨」を万物の長、「利」を万物の生育、「貞」を万物の成就と解し、天の四徳として春夏秋冬、仁礼義智に配する。(大辞林 第三版)
●邵康節(しょうこうせつ)=邵雍 (しょうよう)
中国,北宋の学者,詩人。共城 (河南省) の人。字,堯夫 (ぎょうふ) 。その諡によって邵康節と呼ばれることも多い。幼少から才名が高く,李之才から図書,天文,易数を学んで,仁宗の嘉祐年間に,将作監主簿に推されたが固辞し,一生を市井の学者として終った。(ブリタニカ国際大百科事典)
●河図洛書(かとらくしょ)
中国古代に黄河と洛水のなかから出現したといわれる神秘的な図で,天地の理法を象徴しているともいわれる。『易』繋辞上伝に「河,図を出し,洛,書を出し,聖人之に則 (のっと) る」とあり,また『論語』子罕編にも「河,図を出さず」の有名な語がある。(ブリタニカ国際大百科事典)
鎌倉幕府を糾弾した崎門学派─鳥巣通明『恋闕』「承久中興の本義」
 平泉澄先生門下の鳥巣通明は『恋闕』に収めた「承久中興の本義」において、皇政復古を阻んだ北条氏(鎌倉幕府)を糾弾した崎門学について次のように書いている。
平泉澄先生門下の鳥巣通明は『恋闕』に収めた「承久中興の本義」において、皇政復古を阻んだ北条氏(鎌倉幕府)を糾弾した崎門学について次のように書いている。
〈……徳川政権下にもつとも端的明確に泰時を糾弾したのは山崎闇斎先生の学統をうけた人々であつた。崎門に於いて、北条がしばしばとりあげられ批判せられたことは、たとへば、「浅見安正先生学談」に
北条九代ミゴトニ治メテモ乱臣ゾ
また、
名分ヲ立テ、春秋ノ意デミレバ北条ノ式目ヤ、足利ガ今川ノ書ハ、チリモハイモナイ
などと見えることによつても明らかである。(中略)
所謂「貞永式目の日」を 三上皇に於かせられては絶海の孤島にわびしくお過し遊されたのであるが、しかもこれほどの重大事な恐懼せず、慙愧することなくして北条の民政をたゝヘた時代がかつてあつたこと、否、それをたゝへる人々が現に史学界の「大家」として令名をほしいまゝにしてゐるのを思ふ時、それ等の人々の尊皇と民政を二元的に見る立場、不臣の行為すら「善政」によつて償はれるとする立場をきびしく批判した崎門学派の日本思想史上に占むる地位はおのづから明らかであらう。また儒学を学びつゝもその道徳哲理をわが国ぶりに於いて理解した崎門の人々、わが古典に思をひそめてふかく神道に参じた崎門の人々の学績を刻明にあとづけることを怠り、この学派の基本的性格を以で支那的名分論なりと論じさることの如何にあやまれるかも、かくて了知されるであらう。しかしてわれわれは、以上の如くその史論に於いて泰時を許さず、鎌倉幕府を否定したこの派の正系につらなる人々が、自ら生を享けし日に於いて、遂に徳川幕府及びその支配下の大名に仕へることをいさぎよしとせず、また一言半句も武家政権に阿附せず、あるひは一生処士として恋闕の至情に生きぬき、あるひは宝暦明和にはじまる排幕運動をまき起したことを、この上もなくゆかしくたふとく思ふのである〉
若林強斎『神道大意』の真髄⑤─近藤啓吾先生「日本の神」⑤
若林強斎『神道大意』第五段
「総じて神道をかたるは、ひらたうやすらかにいふがよしとなり。忌部正通の、辞を嬰児にかりて心を神聖にもとむ、といへるこれなり。あのあさはかにあどない(子供つぽい、あどけないの意)やうなる中に、きつう面白くうまい意味がある、理窟らしい事を甚だきらふ事なり。(下略)」
以下、近藤啓吾先生「日本の神」の解説
「以上第五段。忌部正通の辞とは、忌部正通の著と伝へる『神代口訣』の凡例のうちに見える語であつて、その意、「神代巻」の記述、一見荒唐無稽の如くであるが、それは古代人の未開未熟の眼をもつて見た儘を写したものであるから、我れも当時の人となりて当時の眼をもつてその荒唐の記述を見れば、おのづからその真実を知り得るであらうといふものである。そして闇斎も、初め神代の記述の不合理なるを解しがたしとしたのであるが、この辞を知るに及んで、その記述に込められた真実を理解するの道が開けたることを述懐してゐる。強斎のこの語は、闇斎のその意を受けたものに外ならない。そして強斎はその辞によつて、神道はいたづらに理窟を言ひたてるべきでなく、その説、平易なるべきであるといふのである。
以上をもつて強斎『神道大意』の紹介とその略解を終へる。読者みづからこれを熟思し、その神道説の本旨をみづから把握して頂きたい。そしてこれに因り、日本の神の特色を明らかにしてほしいと思ふ」
若林強斎『神道大意』の真髄④─近藤啓吾先生「日本の神」④
若林強斎『神道大意』第四段
「……苦々しき事は、上古神祖の教を遵(したがひ)守らせたまはぬ故と見えて、上はおそれあれば申し奉られぬ御事なり。下一統の風俗、唐の書のみ読みて、却つて我が国の道はしらず、浮屠は信じて却つて神明はたふとび奉らず、かの君上を大切に存じたてまっり、冥慮をおそるるやうなるしほらしき心は殆んどむなしくなりたり。まことに哀れむ可き事ならずや。然れども天地開闢已来、今日に至るまで、君も臣も神の裔かはらせたまはず、上古の故実もなほ残りて、伊勢神宮を初穂をもて祭らせ給はぬ内は、上様新穀をめしあがらせたまはぬの、伊勢奉幣、加茂祭の時は、上様も円座(わらふだ)にましますの、僧尼は神事にいむなどいふ類なり。さあれば末の世というて我れと身をいやしむべからず、天地も古の天地なり、日月の照臨、今にあらたなれば、面々の黒(きたな)き心を祓ひ清め、常々幽には神明を崇め祭り、明には君上を敬ひ奉り、人をいつくしみ、物をそこなはず、万事すぢめたがふ事なければ、おのれ一箇の日本魂は失墜せぬといふものなり。余所を見て悲しむ事なく、唯々我が志のつたなきことを責め、我が心身のたゞしからぬ事のみをうれひ、冥加を祈りてあらためなほすべし」
以下、近藤啓吾先生「日本の神」の解説
「以上第四段。我国に古風古儀の存するありて、天地も古の天地であり、日月の照臨も今にあらたであるから、各人それぞれの汚き心を祓ひ清めて、神を崇め君を敬ひ人をいつくしみ物をそこなはず、万事筋目たがふことがなければ、己れ一個の日本魂は失はれぬことであるから、人を見て我が足らざるを悲しむことなく、ただ我が志の拙きことを責め、我が身の正しからぬことのみを憂へて、神の冥加を祈り、我れの至らぬところを矯め改めよ。かく説くが本段の主旨である。なほ本段の用語に見える「上様」は、当時一般にその大の属する封建君主をいふものであつたのと異なり、天皇を指し奉ることであさて、強斎に於いては、上様と仰ぐは天皇御一人の外なく、この講義を聞く人、よし封建君主の家臣であつても、その人の立場を越えて天皇の直臣との立場に於いてこれを聞くことを求めたことが、この語の用法にうかがはれる」
