高嶋辰彦は、天地人の広漠複雑性に注目して西欧兵学の科学技術万能の限界を次のように説いた。
「西欧の世界は天地人共に東洋に比して矮小である。其處に発達せし尖鋭なる科学と技術とが、武力戦に於いて特に絶大の決戦力を有つことも亦当然である。ドヴエーの空軍万能論の如き其の最も極端に趨りて稍々迷妄に堕したる一例である。
東洋の武力戦に於ても、尖鋭なる科学、卓越せる技術に基く所謂近代的兵器の威力の重要なるは言を俟たない。併し此処に於ける天地人の広漠複雑性は、幾多の制約を西欧的科学、技術兵器の上に課するのである。自動火器の故障、火薬の燃焼躱避、戦車、自動車、飛行機の速かなる衰損の如き其の一例である。
東洋兵学兵制に於ける科学技術は独特の大自然に即し、西欧流のそれに対し厳密なる検討を遂げ、独自の境地を開拓して自ら完成すべきであろう」
続けて高嶋は、後方業務の重要性を次のように指摘する。
「西欧兵学に於てすら或は集中を以て戦略の主位とした。東洋戦場に於ける武力戦の困難は後方に在る。作戦兵力の輸送、集中、転用、軍備の補給、守備、治安等に関する複雑困難さは西欧と同日の比ではない。従つて之を克服することに寧ろ戦勝の決定的要素を見る。蒙古軍即ち元軍が常に其の補給点を前方に求めたるが如きは多大の示唆を含むものである。後方業務を重視し、東洋独自の新原則の確立と共に、有事に際して必ず之が圓滑を期することは東洋兵学に於ける重要課題である」
さらに高嶋は、武力偏重の西欧兵学に対して、総力戦的虚々実々の戦法の優位性を説く。
「西欧は地域矮小、民族単一、国家の総力的団結比較的鞏固である。此処に発達したる兵学が武力偏重の強制的色彩を帯ぶるは止むを得ない所である。然るに東洋の実情は大いに之と異り、前諸項と関連して総力的見地に於て到る処に虚隙を呈し、普く之を塡むることは殆んど不可能に近い。
此の処に乗じて敵の意表に出で、総力戦的優勢の発揮を、在来兵学の原則に準じて行ふの余地は東洋に於て最も大である。斯かる総力戦運用の原理は、又武力戦内部に於ける思想手段、経済手段等を以てする総力戦的虚々実々の戦法に於て多大なる開拓の前途を有して居る。正に東方兵学の高次性を発揮すべき好適の一面である」
ハイブリッド戦の時代が到来したいま、「総力戦的虚々実々の戦法」こそ、東方兵学の高次性を発揮すべき分野なのではなかろうか。
「高嶋辰彦」カテゴリーアーカイブ
「肇国の大精神を世界に顕現実践することが皇戦の目的だ」
高嶋辰彦は、昭和十三年十二月に著した『皇戦 皇道総力戦世界維新理念』(戦争文化研究所)で、次のように皇戦の目的を説いている。
「(支那)事変を体験するに伴ひ逐次認識を明にせる事項の一つは、我が国の戦争即ち皇戦の目的は、我が國體の保護宣揚、即ち我が国ごころを内外に宣べ行ふこと、更に換言すれば我が肇国の大精神を世界に顕現実践して、建国以来の真生命を達成するに在るといふことである。国防に関する一般通年たる人民、国土、資源等を外敵に対して護るとか、その危険を未然に防ぐため、予め脅威を取り除くとか、乃至は自ら力を養ふために国防力要素の不足を獲得するとかいふが如き在来の考へ方では、不知不識の間に皇戦の本義を没却するが如き重大過誤に陥る処が多いのである。……こゝで特に大切なことは、此の国ごころは決して外に対して宣揚するだけではなく、国内に対して同様の作用を必要とするといふことである。国内即ち日本全国民が先づ世界に実践の模範を示し得るだけの国ごころの体得者、実践者とならなければ、対外宣揚の資格と力とがない……」
敵将兵を味方とするような東洋兵学
支那事変以降、高嶋辰彦は東洋兵学の重要性を説くようになった。東洋兵学に対する高嶋の思いは戦後も持続した。例えば彼は、昭和三十(一九五五)年七月に「アジア政策における日本の体験と日米相互安全保障の将来」(『月刊自衛』)を著し、東洋では統率即ち人の掌握と統御指導とが兵学の第一義だと説いた。
彼は、ジンギスカンが親兵一万人の姓名を記憶していたという伝説を紹介し、兵の掌握は下士官級、でき得れば兵まで貰かれていなければならないと説いた。その上で高嶋は精神指導、心理掌握のための教育の重要性を指摘した。
さらに高嶋は、戦場や駐留地附近の現地住民の心を味方とすることが必要だと説き、朝鮮戦争に参加した際の中共軍の例を挙げる。高嶋によると、中共軍の「抗美援朝教育」は、現地住民を味方とするために徹底的な教育を行った。
そして高嶋は、東洋においては、敵に向う前に敵地の住民、敵軍の将兵、敵将の側近までみ、できる限り味方にするように工作し、敵将が孤立し、崩壌する寸前に、敵住民に歓迎されながら進軍して行くのが名将の術とさえ言われていると述べ、次のように書いている。
「これらの点でソ連や、中共の戦略、手法はアジア、東洋兵学の真髄をつかんでいる点がある」
本来、日本でもこうした兵学が維持されていたが、明治以降の兵学は多くを西欧に学んだため、現地住民、敵地住民、敵将兵を味方とする様な兵学は後退してしまった。
さらに高嶋は、西欧兵学はアジアにおける地上戦や、駐留勤務に困難を来す盲点が存するのではないかと指摘する。この高嶋の指摘は、アジア各地での反米機運の効用、ベトナム戦争でのアメリカの敗北というその後の歴史を予見しているかのようである。
高嶋辰彦「世界に冠絶する皇道兵学兵制の完成」①
令和四年十二月に策定された国家安全保障戦略には、「サイバー攻撃、偽情報拡散等が平素から生起。有事と平時の境目はますます曖昧に。安全保障の対象は、経済等にまで拡大。軍事と非軍事の分野の境目も曖昧に」と書かれている。軍事的手段と非軍事的手段を組み合わせた、いわゆる「ハイブリッド戦」の時代が到来しているということである。
まさにいま、西欧兵学兵制の限界を克服し、皇道に基づいた日本独自の兵学兵制を活用する時がきているのではないか。そこで浮かび上がってくるのが、戦前に皇道兵学兵制を説いた高嶋辰彦の思想的価値である。
同時に、わが国は欧米列強の覇道主義に抵抗する過程で、自らが覇道主義に陥り、日本軍は皇軍としての誇りを失ってしまったかに見える。それが日支事変の戦局にも暗い影を落としていたのではあるまいか。日本を取り巻く安全保障上の環境が厳しさを増す中で、自衛隊は防衛力の強化の前に皇軍としての誇りを取り戻す必要がある。そのためにも、高嶋が唱えた皇道総力戦思想に学ぶべき時である。
高嶋は、昭和十三年十月に、「世界に冠絶する皇道兵学兵制の完成」(『偕行社記事』)を著し、次のように指摘した。
「今次支那事変の体験は、東洋における於ける戦ひが、其の質に於て欧州大戦をも凌ぐ複雑多岐の一面を有し、高次なる我が皇道総力戦を以てして始めて克く之が解決を期し得べきことを明かにした。是れ此の事変の有する世代的、世界史的重大意義と、東洋の実情、我が国の特性等との然らしむる所である。
是に於て近世世界を風靡せるの感ありし西欧流の兵学、兵制も亦更に遥かに高次なる新興兵学兵制の前に、縦横に批判せられ、嶮厳なる栽きを受けざるを得ない趨勢となつて来た」
高嶋は東洋の実情と我が国の特性と西欧兵学兵制とを対比する。自然現象の活用という観点については、次のように指摘している。
〈西欧の自然は単一である。其処に発達したる兵学が地形主義万能に堕し、自然現象の活用に於て幼稚なるは言を俟たない。之に反し東洋のそれは実に千変万化、其の複雑多岐なる点に於て世界に冠たるものがある。所謂「天の時」が古来の東洋乃至日本兵挙に於て重要視せられた所以であらう。
炎熱、大旱、酷寒、氷結、大雨、颱風、洪水、飢饉、黄塵等の大規模周到なる兵学的活用は、正に東洋兵学者の究明創設すべき重要課題である〉
高嶋はこう述べて、大地の活用を指摘する。
〈西欧の大地も亦単一である。其処に発達した兵学が地形主義万能とは謂へ、尚甚だ単純なる地形を基礎としあるも亦止むを得ない。然るに東洋に於ける大地の変化は又世界に冠たるものがある。所謂「地の利」の高唱は之に因するのであらう。
大規模なる山岳、密林、濕地、湖沼、河川、平原、沙漠等及其等の内に生成する幾多の動植物は限り無き多元性を展開して居る。乃ち之に関する大局的兵学上の運用原理の開拓も亦東洋兵学の見逃すべからざる重大任務と謂ふべきであらう〉
次に高嶋は大海洋の活用を説く。
「日本を繞る海洋の広大にして複雑なるは之れ亦到底西欧の比ではない。唯々此の方面に於ては英国及最近の米国が類似の戦場を予想して居る。故に我等の努力としては、大海と複根なる小海との関連、海洋と大陸との連鎖、之に伴ふ陸海空三軍の有機的協同運用に兵学研究上の重点が指向せらるべきであらう。
次に「人の統御と操縦とに依る思想手段の重要化」についてこう述べる。
「西欧陸地上の人性は単純である。一見理窟多きが如く見ゆる徒等は、強権強力の前に、又は思想的指導の前に案外単一従順なるは歴史の示す所である。此処に発達したる兵学が「人」の統御と操縦とに関する取扱ひに於て、比較的あつさりして居ることは当然である。然るに東洋大陸に於ける人は全く之と其の選を異にする。柔なるが如くにして靭、屈したるが如くにして実は然らず。単純なる強権強力は動もすれば意外の反発に遭ひ、向背離合容易に予想すべからずして、今日の主従朋友忽ちにして明日の敵味方となる。所謂「人の和」が重要視せらるゝ所以であらう」
スメラ学塾①─日本的世界観を目指して
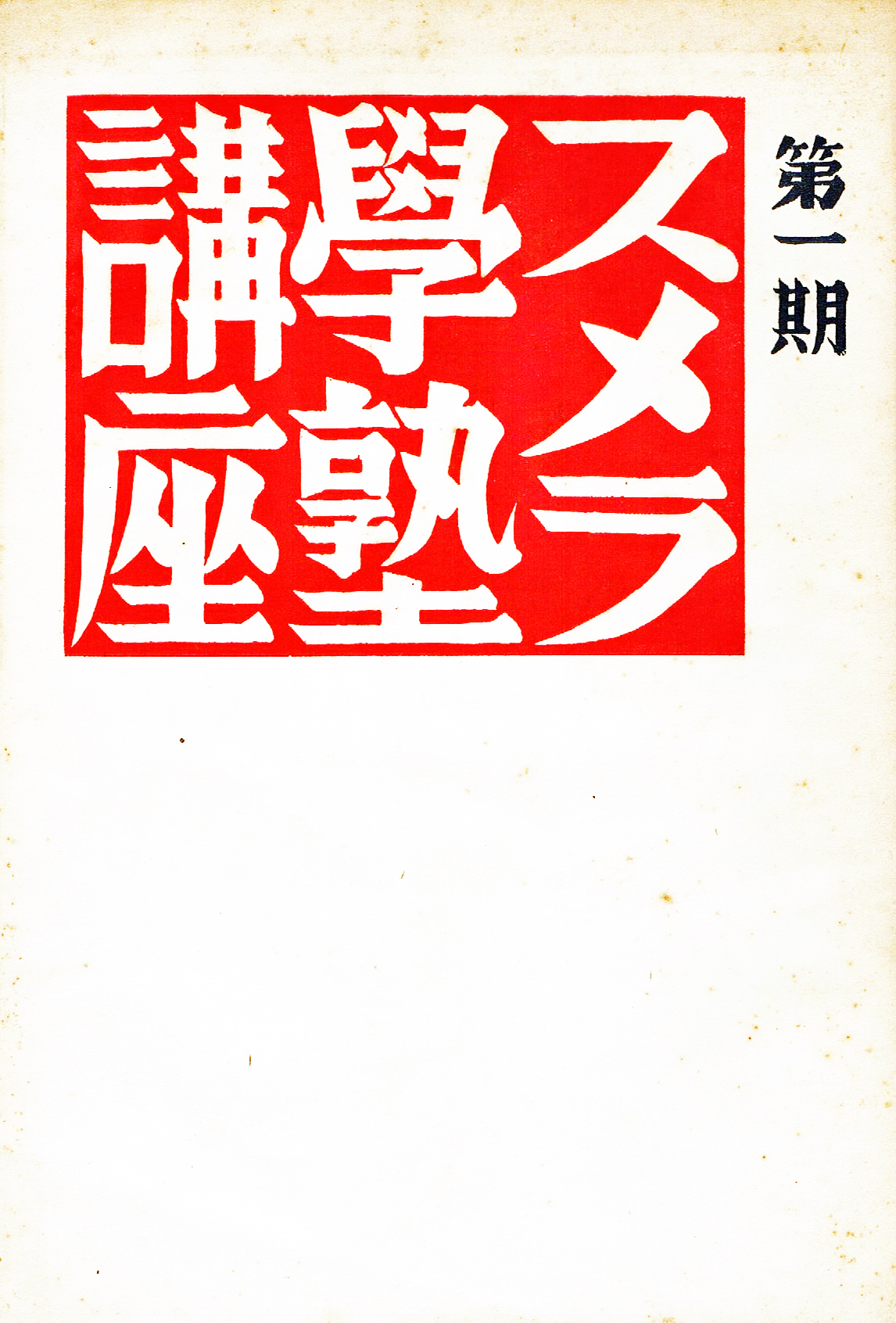 『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。
『日本百年戦争宣言』で知られる孤高のエリート軍人・高嶋辰彦に思想的影響を与えた人物の一人が、仲小路彰である。高嶋が仲小路と初めて会ったのは、昭和十三年十月二十七日のことであった。
独自の「日本世界主義」思想を展開していた仲小路らは、昭和十五年に「スメラ学塾」を立ち上げた。その講義の中核を担ったのは、国民精神文化研究所に所属していた小島威彦である。小島は、日本中心の独創的な世界史を講じた。
仲小路は、昭和十七年に『米英の罪悪史』を著し、以下のように書いている。ここには、欧米的価値観に基づいた政治システムに対する鋭い批判が示されている。
〈思へば、英米の議会主義政治、政党主義的政治は一時全く世界政治の理想の如く宣伝され、その自由主義的民主政治は、実に政治的体制の典型として偶像化されました。これを以て進歩的なりとし、それに反対するものを悉く反動的保守的として排撃し、英米はその政治的偶像をもつて他のすべての諸国を、その政治的統制の下に独裁するのでありました。あらゆる植民地国は、自らの伝統的なる政治組織をもつて全く旧きものとして廃棄し、英国的政治の体制下に編入され細胞化されるのでありました。しかももし一国が強大となるや、これを抑圧するために、米英には適し、その国には不利なる米英的憲法、法律等を制定せしめ、さらにそれを英米的世界の現状維持のみを擬護する国際法をもつてしめつけ、全くその自由を剥奪することを以て、自由主義政治と称せしめ、彼等をして全く英米化し、米英依存せしめるのでありました。しかもすでに民主主義的なる米英的世界秩序は、それ自らの中に矛盾を激化し、末期的没落に瀕するのであります。
かくして今次の大戦こそ、それ等一切の旧き民主主義的米英勢力圏を徹底的に粉砕すべき戦争であります。もしそれを為さずして、たゞ従来の米英的支配権を排撃して、それに代るに再び自らが米英的地位を占め、その搾取を繰返すことあるか、それともまた米英的なる近代国家体制、民主主義政体を植民地の独立として実施するか、或はまたソヴエート的なる民族解放理論がいかなるものなるを認識せず、帝国主義侵略を避けんとして、東亜の解放を実現せんとする如きあらば、これは全く皇軍の赫々たる戦果を無にするのみならず、却つて大東亜民族は不統一のまま殆ど救はるることなく、遂に克服すべからざる禍根を残すこととなるでありませう。まさに近代民主国家を根本的に否定し、海月なす、たゞよへる国々を修理固成するすめらみくにの国生みとしての日本世界史建設の大東亜皇化圏、すめら太平洋圏の復興を実現し、かくて大御稜威の下、アジアは渾然として、その根源的なるものに帰一するは、それ自らの本質的運命であります〉
この仲小路の言説は、英米型民主主義を絶対視する、わが国の戦後言論空間においては、理解し難いものかもしれない。しかし、我々は改めて英米型民主主義が絶対なのかを問い直すべきではないか。
戦争文化叢書
| 号 | 著者 | 書名 | 出版社 | 出版年 |
|---|---|---|---|---|
| 第1輯 | 高嶋辰彦 | 『日本百年戦争宣言』 | 戦争文化研究所 | 1939年 |
| 第2輯 | 清水宣雄 | 『植民地解放論』 | 太平洋問題研究所 | 1939年 |
| 第3輯 | 志田延義 | 『八紘一宇』 | 世界創造社(発売) | 1939年 続きを読む 戦争文化叢書 |
